- 人事が新卒の配属を決める理由
- 配属先が決まるまでのプロセス
- 希望通りにいかない場合の背景
- 配属に納得できない時の対処法
- 今後のキャリアを考える選択肢
新卒の配属はなぜ人事が決めるのか?
新卒の配属がどのように決まるのか、その理由を以下の通り解説します。会社の視点を知ることで、今の状況を理解するヒントが見つかるかもしれません。
- 会社の全体像を把握しているから
- 客観的な視点で適性を判断するため
- 長期的なキャリア育成を計画するため
- 社内の人員バランスを調整するため
各項目について、詳しく見ていきましょう。
会社の全体像を把握しているから
人事は、会社全体の状況を一番よく知っている部署です。どの部署にどんな仕事があって、今どの部署が人手を必要としているのか、会社全体の「地図」を頭に入れています。例えば、ある部署で新しいプロジェクトが始まる、あるいは退職者が出て人手が足りない、といった情報は全て人事に集まります。そうした全体の状況を見ながら、新入社員という新しい力をどこに配置するのが会社にとってベストなのかを考えているのです。個人の希望ももちろん大切ですが、会社というチーム全体がうまく機能するためには、全体を把握している人事の視点が必要不可欠になります。
客観的な視点で適性を判断するため
自分では「この仕事が向いている」と思っていても、第三者から見ると意外な才能が見つかることがあります。人事は、採用活動や研修を通じて多くの新入社員を見ているプロです。面接での話し方やグループワークでの立ち振る舞い、研修中の課題への取り組み方などから、「この人はコツコツ作業するのが得意そうだな」「リーダーシップを発揮できる場面で輝きそうだ」といった、本人も気づいていない適性を見抜こうとしています。希望とは違う配属だったとしても、それは人事が「ここならあなたの力がもっと活かせるはずだ」と考えてくれた結果なのかもしれません。
長期的なキャリア育成を計画するため
会社は、新入社員に将来的に会社の中核を担う人材に育ってほしいと考えています。そのため、目先の希望だけでなく、10年後、20年後を見据えたキャリアプランを考えて配属を決めることがあります。例えば、将来的に企画職を目指すにしても、まずは現場を知るために営業や製造の部署からスタートする、というケースは少なくありません。一見、遠回りに見えるかもしれませんが、現場での経験がなければ、お客様や世の中のニーズを本当に理解した企画は作れないからです。すぐに希望の仕事ができないのはもどかしいかもしれませんが、会社が用意してくれた成長のためのステップである可能性もあります。
社内の人員バランスを調整するため
会社は、様々な部署の協力で成り立っています。特定の部署だけに人が偏ってしまうと、会社全体の仕事がスムーズに進まなくなってしまいます。例えば、花形とされる部署に希望者が殺到しても、全員をそこに配属するわけにはいきません。一方で、会社を裏で支える重要な部署に人がいなければ、会社は機能しなくなります。人事は、各部署の重要性や必要な人数を考え、会社全体がうまく回るように人員を配置する「交通整理」の役割も担っているのです。個人の希望と、会社全体のバランスを考えた上での決定が、最終的な配属につながります。
人事が新卒の配属先を決める判断材料
人事は具体的にどのような情報をもとに配属を決めているのでしょうか。以下の通り、主な判断材料を解説します。これを知ることで、評価のポイントが理解できます。
- 採用面接での評価や発言
- エントリーシートの記載内容
- 新人研修中の様子や成績
- 適性検査の結果
詳しく解説していきます。
採用面接での評価や発言
採用面接は、人事が適性を見極める重要な場です。面接官は、志望動機や自己PRの内容はもちろん、受け答えの仕方や表情、話し方まで細かく見ています。「チームで何かを成し遂げた経験」を熱意をもって話せば「協調性があるな」と評価されますし、「粘り強く取り組んだこと」を具体的に伝えられれば「忍耐力があるな」と判断されるでしょう。面接で話した内容が、そのまま「この人はこういう強みがあるから、この部署が合いそうだ」という配属の判断材料になっているのです。
エントリーシートの記載内容
エントリーシートも、配属を決めるための大切な情報源です。特に、自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の欄は、人柄やポテンシャルを伝える絶好の機会です。例えば、「文化祭の実行委員として、イベントを成功させた」というエピソードからは、計画性や周りを巻き込む力があると判断されるかもしれません。また、「趣味のプログラミングでアプリを作った」といった経験は、IT部門への適性を示す材料になります。文章から伝わる人柄や興味の方向性も、人事はしっかり読み取って配属の参考にしています。
新人研修中の様子や成績
入社後の新人研修も、配属を決めるための最終確認の場と位置づけられています。研修では、ビジネスマナーや会社の事業内容など、社会人としての基礎を学びますが、人事はその過程を注意深く見ています。グループワークで積極的に意見を出すか、講師の話を真剣に聞いているか、課題にどのように取り組むかなど、あらゆる行動が評価の対象です。研修の成績が良いことはもちろんですが、それ以上に、学ぶ意欲や周りとの関わり方が重視されます。研修での頑張りが、希望の部署への配属を後押しするケースも少なくありません。
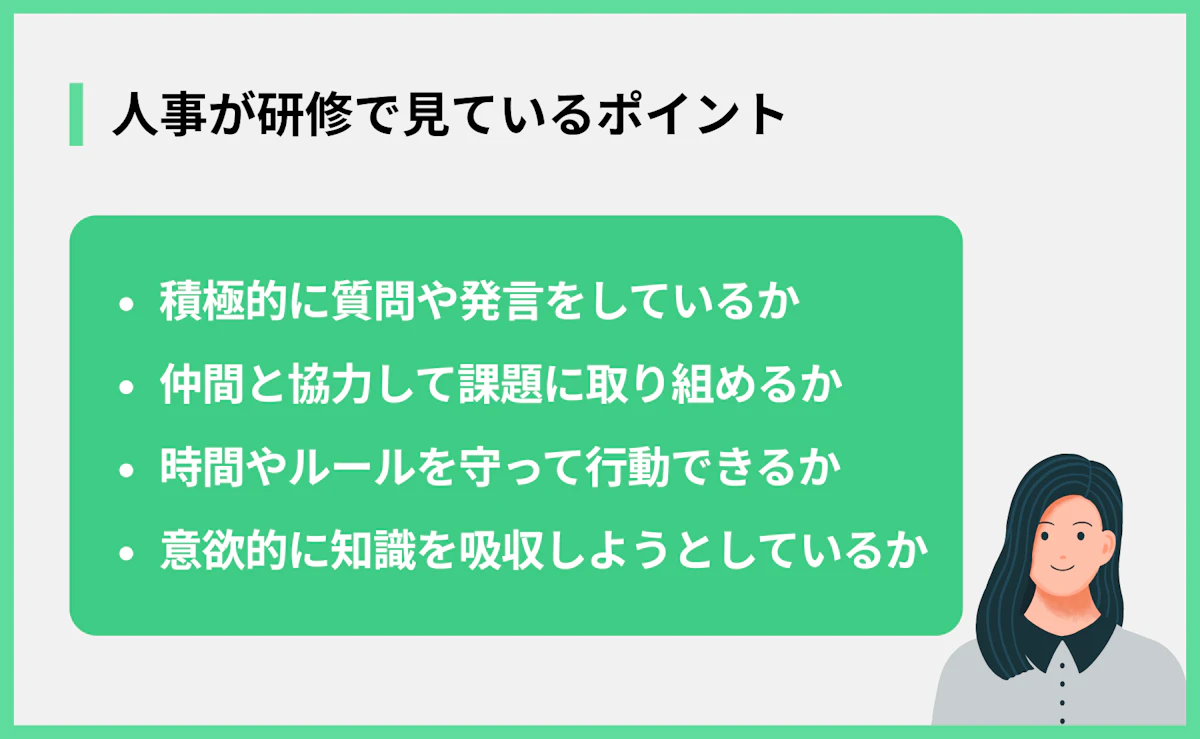
適性検査の結果
多くの会社が、客観的なデータを参考にするために適性検査を実施します。これには、能力検査(言語、計算など)と性格検査があります。能力検査で、素早く正確に作業できることが分かれば、事務処理能力が求められる部署への適性があると判断されるかもしれません。性格検査で「社交性が高い」という結果が出れば、営業や接客といった人と関わる仕事が向いていると考えられます。これらの検査結果は、面接や研修での印象と合わせて、その人の強みや特性を多角的に分析するために使われ、配属の重要な根拠の一つとなります。
希望通りの配属にならないのはなぜ?
会社側の事情は分かっても、やはり希望通りにいかないと落ち込んでしまいます。なぜミスマッチが起きてしまうのか、その理由について以下の通り解説します。
- 人気の部署に希望が集中している
- 本人が気づいていない適性がある
- 会社の事業戦略が優先される
- まずは基礎を学ぶ部署に配属される
詳しく解説していきます。
人気の部署に希望が集中している
希望通りにいかない最も多い理由の一つが、人気の部署に希望者が殺到してしまうことです。どの会社にも、花形と呼ばれる部署や楽しそうに見える仕事はあります。例えば、同期が100人いる会社で、企画部に配属されるのがたったの2人ということも珍しくありません。もし30人が企画部を希望していたら、残りの28人は希望が通らないことになります。これは、誰が優秀で誰が劣っているという話ではありません。単純に「枠」の問題なのです。会社としては、希望を叶えてあげたくても、物理的に不可能な場合があります。
本人が気づいていない適性がある
自分では営業がやりたいと思っていても、人事が面接や研修を通して「この人は分析力が高いから、データ分析の部署の方が活躍できる」と判断することがあります。これは、決して希望を無視しているわけではありません。むしろ、その人の持つ隠れた才能や強みを見つけ出し、最も輝ける場所を提供しようという親心のようなものです。最初は不本意かもしれませんが、「プロの目から見たら、自分にはこんな可能性があるのか」と前向きに捉えてみると、新しい自分を発見できるきっかけになるかもしれません。
会社の事業戦略が優先される
会社は常に成長を目指しており、その時々の事業戦略によって力を入れる部署が変わります。例えば、会社が「これからは海外展開を強化するぞ!」と決めれば、海外事業部の人員を増やす必要があります。そこに、たまたま語学が得意な新入社員がいれば、本人の希望とは関係なく「ぜひ海外事業部で力を貸してほしい」となるのは自然な流れです。個人の希望も大切ですが、会社という大きな船を動かすためには、船全体の進む方向、つまり事業戦略が最優先されるのです。これは、会社が成長し続けるために必要な判断といえます。
まずは基礎を学ぶ部署に配属される
希望する仕事が専門的な知識を必要とする場合、まずは会社全体のビジネスの流れを理解するために、別の部署に配属されることがあります。例えば、商品開発の仕事がしたいと思っても、まずは工場で製品がどう作られるのか、あるいは営業としてお客様がどんな商品を求めているのかを知らなければ、良い商品は開発できません。一見、希望と違う仕事に見えても、それは将来希望の仕事に就くための土台作りの期間と位置づけられているのです。数年後に希望部署へ異動するための、重要なステップと捉えることができます。
配属に納得できない時の気持ちの切り替え方
頭では理解できても、気持ちがついていかないこともあります。そんな時に試してほしい、前向きな気持ちの切り替え方を以下の通り紹介します。
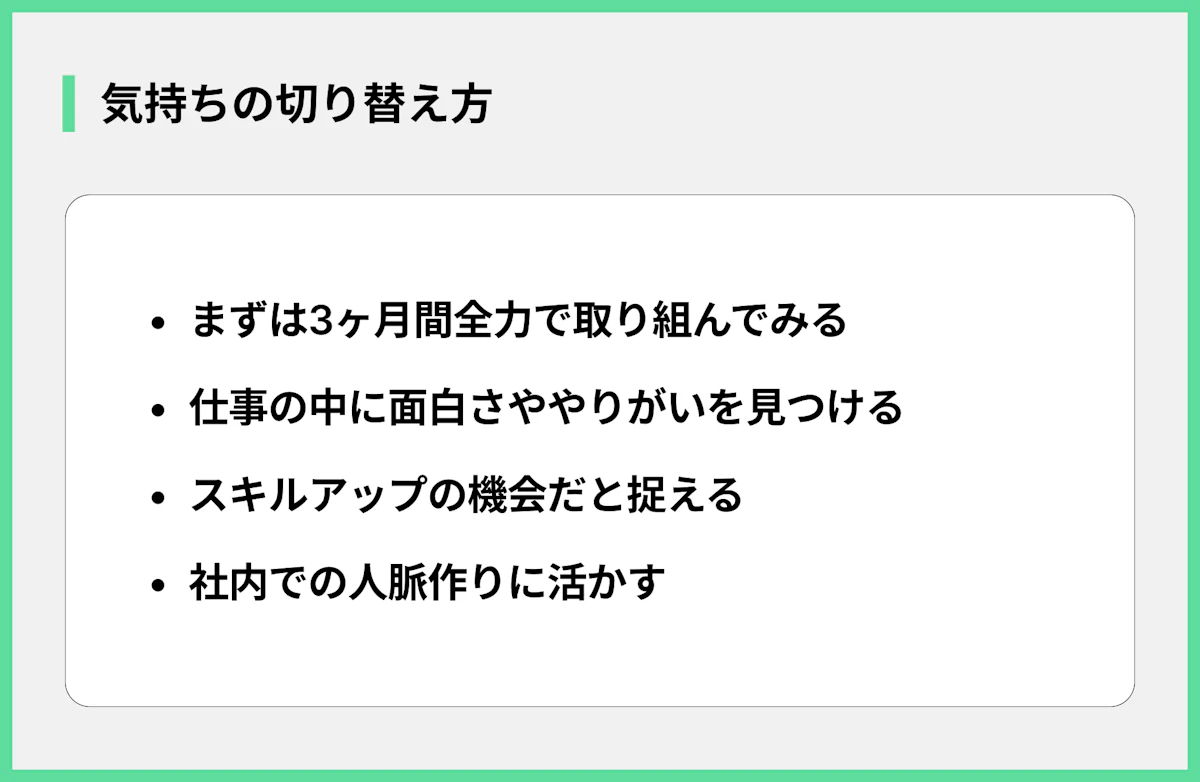
詳しく解説していきます。
まずは3ヶ月間全力で取り組んでみる
配属されてすぐに「この仕事は合わない」と決めつけるのは、非常にもったいないことです。仕事の本当の面白さや大変さは、ある程度の期間やってみないと分かりません。「石の上にも三年」ということわざがありますが、まずは3ヶ月間、とにかく目の前の仕事に全力で取り組んでみてください。最初は嫌々やっていた作業でも、慣れてきたり、できるようになったりすると、面白さを感じられるようになるかもしれません。全力でやってみた上で、それでも「違う」と感じるのであれば、その時に初めて次のステップを考えれば良いのです。
仕事の中に面白さややりがいを見つける
どんな仕事にも、必ず面白さややりがいが隠されています。ただ言われたことをこなすのではなく、「どうすればもっと効率的にできるだろう?」「お客様にもっと喜んでもらうにはどうしたらいいだろう?」と、自分なりに工夫してみましょう。例えば、単調なデータ入力の仕事でも、「どうすればミスなく、速く入力できるか」というゲームのように捉えることで、面白さを見出せるかもしれません。自分の工夫で仕事が上手くいったり、誰かに「ありがとう」と言われたりすると、それが大きなやりがいにつながります。小さな成功体験を積み重ねることが、仕事へのモチベーションを高める鍵です。
スキルアップの機会だと捉える
希望と違う部署での経験は、将来のためのスキルアップの機会と捉えることができます。今の仕事で身につくスキルが、将来希望の部署に行った時に役立つ可能性は十分にあります。例えば、営業職に配属されたなら、コミュニケーション能力や交渉力が鍛えられます。これは、将来どんな部署に行っても必ず役立つポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)です。「今は将来のためにスキルを貯金している期間なんだ」と考えることで、目の前の仕事にも前向きに取り組めるようになるでしょう。
社内での人脈作りに活かす
今の部署で働くことは、社内に人脈を広げる絶好のチャンスです。仕事で関わる先輩や同僚、他部署の人たちと良好な関係を築いておきましょう。社内の人脈は、仕事を進める上で大きな助けになります。困った時に相談に乗ってくれたり、他部署との調整役になってくれたりすることもあるでしょう。また、将来的に異動を希望する際に、その部署の人から情報を得たり、応援してもらえたりするかもしれません。希望の部署にしか知り合いがいない人よりも、様々な部署に顔が利く人の方が、会社員として長期的に見て有利に働くことが多いのです。
すぐに転職する場合のメリット
いろいろ試してみたけれど、どうしても今の仕事が合わないと感じる場合、早期の転職も一つの選択肢です。その場合のメリットを以下の通り解説します。
- 第二新卒としてポテンシャルを評価される
- 未経験の職種に挑戦しやすい
- 早い段階でキャリアの方向性を修正できる
詳しく解説していきます。
第二新卒としてポテンシャルを評価される
社会人経験が3年未満の場合、「第二新卒」として転職活動ができます。第二新卒の採用では、即戦力となるスキルよりも、社会人としての基礎的なマナーや今後の成長可能性(ポテンシャル)が重視される傾向にあります。新卒の就職活動でうまくいかなかったとしても、一度社会人経験を積んでいることはプラスに評価されます。ビジネスマナーが身についている分、新卒よりも教育コストがかからないと考える企業も多いです。この「第二新卒」という特別なカードを使えるのは、若いうちだけの特権です。
未経験の職種に挑戦しやすい
年齢を重ねてからのキャリアチェンジは難しくなる傾向がありますが、第二新卒なら未経験の職種にも挑戦しやすいという大きなメリットがあります。企業側も、第二新卒には特定のスキルよりも、柔軟性や学習意欲を求めています。「新しいことをどんどん吸収して、会社に新しい風を吹き込んでほしい」と考えているのです。「やっぱりあの仕事がしてみたい」という強い思いがあるなら、ポテンシャルを評価してもらいやすい第二新卒の期間は、キャリアチェンジの絶好のタイミングと言えるでしょう。
早い段階でキャリアの方向性を修正できる
「このままこの会社にいても、自分のやりたいことはできない」と明確に感じている場合、早い段階で行動を起こすことでキャリアを修正できます。合わない仕事で悩みながら何年も過ごしてしまうと、気力や体力が消耗し、新しい一歩を踏み出すエネルギーがなくなってしまうこともあります。また、特定の業界や職種の経験が長くなるほど、他の分野への転職が難しくなるのも事実です。貴重な20代の時間を無駄にしないためにも、早期に見切りをつけて新しい環境に飛び込むのは、賢明な判断となる場合があります。
すぐに転職する場合のデメリット
早期の転職にはメリットがある一方で、もちろんデメリットも存在します。決断する前に、以下の通りリスクもしっかりと理解しておくことが重要です。
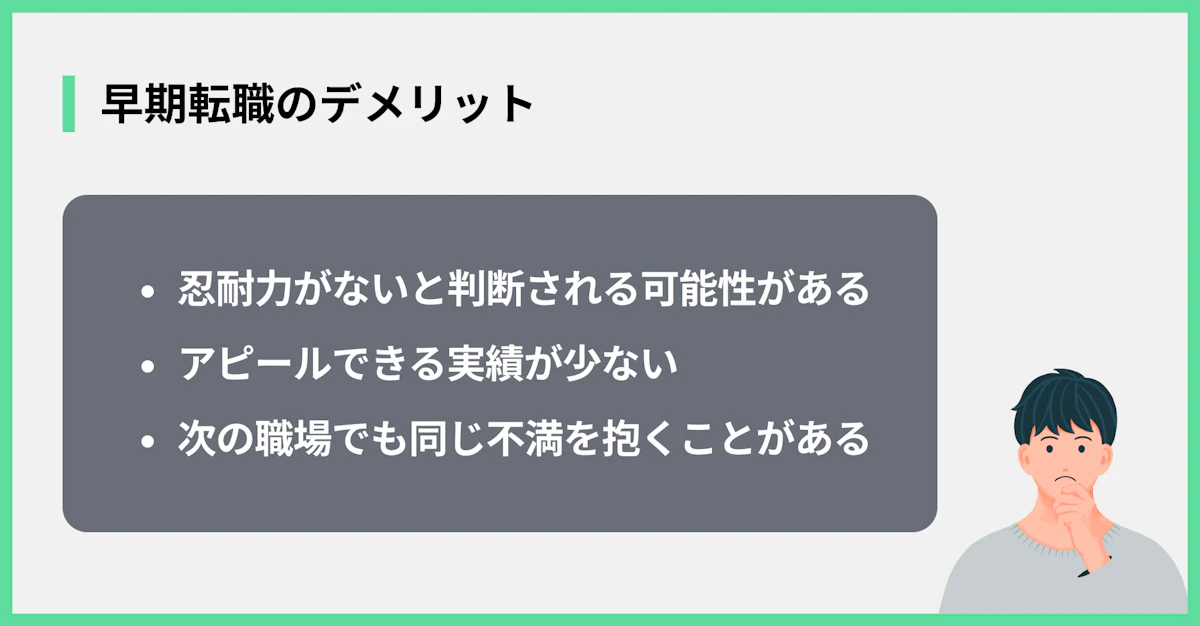
詳しく解説していきます。
忍耐力がないと判断される可能性がある
短期間での離職は、採用担当者に「またすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱かせる可能性があります。「忍耐力がない」「ストレスに弱い」といったネガティブな印象を持たれてしまうリスクは否定できません。そのため、面接では「なぜ前の会社を辞めたのか」という質問に対して、明確で前向きな理由を説明する必要があります。「仕事内容が合わなかった」というだけでなく、「その経験から何を学び、次の仕事でどう活かしたいのか」までをセットで伝えられないと、納得してもらうのは難しいでしょう。
アピールできる実績が少ない
社会人経験が短いということは、仕事での具体的な実績や成果が少ないということです。転職活動では、これまでの仕事でどんな成果を出してきたかをアピールすることが重要になります。「〇〇というプロジェクトを成功させた」「売上を〇%アップさせた」といった具体的なエピソードがないと、他の候補者との差別化が難しくなります。ポテンシャルを評価される第二新卒とはいえ、何か一つでも「これを頑張った」と胸を張って言える経験がある方が、転職活動を有利に進められます。
次の職場でも同じ不満を抱くことがある
今の職場の何が不満なのかを自己分析できていないまま転職すると、次の職場でも同じ問題に直面する可能性があります。例えば、「人間関係が嫌だ」という理由で辞めたとしても、どんな職場にも色々なタイプの人がいます。問題の原因が自分自身のコミュニケーションの取り方にあった場合、環境を変えても根本的な解決にはなりません。なぜ配属に不満を感じたのか、自分は仕事に何を求めているのかを深く考えずに転職活動を始めてしまうと、転職を繰り返すことになりかねません。
今の配属先で試せるキャリアアップ術
すぐに転職するのではなく、今の会社でもう少し頑張ってみようと考えた場合、社内でできることもたくさんあります。以下の通り、具体的なアクションを紹介します。
- 上司にキャリアプランを相談する
- 社内公募や異動希望制度を調べる
- 業務に関連する資格の勉強を始める
詳しく解説していきます。
上司にキャリアプランを相談する
まずは、直属の上司に自分のキャリアについて相談してみましょう。その際は、ただ「この仕事が嫌だ」と伝えるのではなく、「将来的には〇〇という仕事に挑戦したいと考えています。そのためには、今どんなスキルを身につければ良いでしょうか?」という前向きな形で相談するのがポイントです。上司は、部下の成長をサポートするのも仕事の一つです。真剣に相談すれば、アドバイスをくれたり、新しい仕事を任せてくれたりするかもしれません。自分の意思を伝えておかなければ、何も始まりません。はっきりと口に出して伝えることで、上司もあなたのキャリアを意識してくれるようになり、将来の異動希望が通りやすくなる可能性もあります。
社内公募や異動希望制度を調べる
会社によっては、社員が自ら希望の部署に立候補できる「社内公募制度」や、年に一度異動希望を提出できる制度があります。まずは、自分の会社にそうした制度があるかどうかを確認してみましょう。制度があれば、それは会社が社員のキャリアチェンジを応援している証拠です。希望の部署が募集をかけていたら、積極的に応募してみる価値はあります。たとえすぐに応募しなくても、どんな部署がどんな人材を求めているのかを知ることは、自分の市場価値や今後のスキルアップの方向性を考える上で非常に参考になります。
業務に関連する資格の勉強を始める
希望する仕事があるなら、その仕事に関連する資格の勉強を始めるのもおすすめです。資格は、客観的に自分のスキルや意欲を証明できる強力な武器になります。例えば、経理の仕事に興味があるなら簿記、IT業界に興味があるなら基本情報技術者試験など、目標を定めて勉強を始めましょう。資格を取得すれば、異動希望を出す際に「これだけ本気で考えています」という熱意をアピールできます。たとえ今の会社で希望が叶わなかったとしても、その資格は転職活動の際にも必ず役立ちます。自分の将来への投資だと考えて、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
どうしても合わないなら転職のプロに相談する
社内でやれることは全てやった、それでも状況が変わらない、あるいは今の環境では自分の成長が見込めない。そう感じたら、転職エージェントのようなプロに相談するのも賢い選択です。
- 自分の市場価値を客観的に把握する
- 自分に合う非公開求人を紹介してもらう
- Zキャリアのエージェントに相談してみる
詳しく解説していきます。
自分の市場価値を客観的に把握する
自分一人で悩んでいると、「自分なんてスキルもないし、転職なんて無理だ」と視野が狭くなりがちです。転職エージェントは、転職市場のプロとして客観的な視点から、あなたの強みや可能性を見つけてくれます。これまでの経験をヒアリングした上で、「その経験は、〇〇業界では高く評価されますよ」「あなたのようなタイプは、〇〇という仕事に向いていますね」といった具体的なアドバイスをもらえます。自分では気づかなかった自分の価値を知ることで、自信を持って転職活動に臨むことができるようになります。
自分に合う非公開求人を紹介してもらう
転職サイトなどには掲載されていない「非公開求人」を紹介してもらえるのも、転職エージェントを利用する大きなメリットです。企業が非公開で求人を出す理由には、「重要なポジションだから、じっくりマッチする人材を探したい」「応募が殺到するのを避けたい」などがあります。つまり、非公開求人には、条件の良い優良企業の求人が含まれている可能性が高いのです。エージェントは、あなたの希望や適性を理解した上で、膨大な求人情報の中からマッチするものを厳選して紹介してくれます。自分一人で探すよりも、効率的に理想の職場に出会える可能性が高まります。
Zキャリアのエージェントに相談してみる
配属への不満や将来への不安を一人で抱え込んでいるなら、ぜひ一度Zキャリアのキャリアエージェントに相談してみてください。私たちは、特に若年層の転職サポートを得意としており、同じような悩みを抱えた多くの方を支援してきました。何から始めたらいいか分からない、という段階でも全く問題ありません。まずはあなたの気持ちを聞かせてください。話すことで、自分の考えを整理できることもあります。私たちは、無理に転職を勧めることはありません。あなたの気持ちに寄り添い、今の会社で頑張るべきか、新しい道を探すべきか、一緒に考えていきます。あなたのキャリアにとって最善の選択ができるよう、全力でサポートさせてください。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)



