試用期間中に退職できる?
結論:通常の退職規定通り、退職届を申し出てから2週間で退職可能
試用期間中であっても、労働者は法律に基づいて退職することが可能です。日本の民法第627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも解約の申し入れをすることができ、申し入れの日から2週間が経過することで雇用関係が終了すると定められています。試用期間は法的には「解約権留保付労働契約」とされ、本採用後と変わらない労働契約の一種です。そのため、会社を辞めたいと思った場合は、退職届を提出してから最短2週間で退職が成立します。会社の就業規則にこれより長い期間が記載されていても、法律の規定が優先されます。まずは退職の意思を明確に伝えることが第一歩となります。
会社との話し合いで即日の退職が認められれば試用期間中であっても即日退職が可能
法律では退職の申し入れから2週間が必要とされていますが、これはあくまで最短期間の定めです。会社との話し合いで双方が合意すれば、2週間を待たずに即日退職することも不可能ではありません。これを「合意退職」と呼びます。例えば、引き継ぎの必要がほとんどない場合や、会社側が早期の退職を認める状況であれば、話し合いによって退職日を早めることができます。ただし、これは会社の合意があって初めて成立するものです。一方的に即日退職を主張するのではなく、「ご迷惑をおかけして申し訳ないのですが、本日付けでの退職をご相談させていただけないでしょうか」と、丁寧にお願いする姿勢が重要です。円満な退職を目指すためにも、まずは直属の上司に相談してみましょう。
会社の就業規則で退職1ヶ月前の申告等が規定されていても法律が優先される
多くの会社の就業規則には「退職を希望する場合、1ヶ月前までに申し出ること」といった規定が設けられています。しかし、これは法的な強制力を持つものではなく、あくまで会社のルールです。前述の通り、民法第627条では2週間前の申し出で退職できると定められており、就業規則よりも法律が優先されます。したがって、法的には2週間前に退職届を提出すれば問題ありません。ただし、円満退職を目指すのであれば、可能な限り就業規則に従うことが望ましいでしょう。引き継ぎや人員補充など、会社側にも準備期間が必要なため、就業規則を守ることで、余計なトラブルを避け、スムーズに退職手続きを進めることができます。自分の状況と会社の規則を天秤にかけ、最適なタイミングを判断しましょう。
そもそも試用期間とは何?
労働者が本採用に適さないと企業側が判断した場合に解雇できる権利を保有している期間
そもそも試用期間とは、企業が本採用を決定する前に、労働者の勤務態度やスキル、適性などを見極めるために設けられた期間のことです。法的には「解約権留保付労働契約」と呼ばれ、企業側は試用期間中に労働者が自社の社員として不適格であると判断した場合、本採用を拒否(解雇)する権利を持っています。ただし、この解雇権の行使は無制限に認められるわけではありません。客観的に見て合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合に限られます。例えば、経歴詐称が発覚した場合や、無断欠勤を繰り返すといったケースが該当します。企業側が労働者を評価するための期間と言えるでしょう。
試用期間であっても労働者側の退職の自由が制限されるものではない
試用期間は企業が労働者を評価する期間ですが、同時に労働者側が企業を見極める期間でもあります。入社前に聞いていた話と実際の労働条件が違う、社風がどうしても合わないなど、働き続けることが困難だと感じた場合、労働者は自らの意思で退職することができます。試用期間中であるからといって、労働者の「退職の自由」が制限されることは一切ありません。企業側に解雇の権利があるのと同様に、労働者側にも退職の権利があります。自分自身のキャリアや心身の健康を守るために、合わない環境から離れるという選択は決して間違いではありません。遠慮することなく、自身の正直な気持ちを優先して判断することが大切です。
試用期間は通常3ヶ月〜半年程度
試用期間の長さは法律で明確に定められているわけではありませんが、一般的には3ヶ月から6ヶ月程度に設定する企業が多いです。この期間は、労働契約書や就業規則に明記されているため、入社前に必ず確認しておくべき重要な項目の一つです。あまりにも長すぎる試用期間(例えば1年以上)は、公序良俗に反し無効と判断される可能性もあります。企業は、業務内容や職種に応じて、労働者の適性を判断するために必要かつ合理的な期間を設定する必要があります。もし自分の試用期間がどのくらいか不確かな場合は、雇用契約書を再確認するか、人事部に問い合わせてみましょう。この期間が、今後の働き方を考える一つの目安となります。
試用期間で「会社と合わない」と感じた場合は退職すべき?
短期離職となるのでできることをした上で退職すべき
試用期間での退職は、職務経歴上「短期離職」となります。短期離職の経歴は、次の転職活動において採用担当者から「またすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱かれやすく、不利に働く可能性があります。そのため、「会社と合わない」と直感的に感じたとしても、すぐに退職を決断するのは得策ではありません。まずは、なぜ合わないと感じるのか、その原因を冷静に分析し、状況を改善するために自分にできることはないか試してみることが重要です。例えば、上司や同僚とのコミュニケーションの取り方を変えたり、仕事の進め方を工夫したりするなどです。できる限りの努力をした上で、それでも状況が変わらない場合に、初めて退職という選択肢を具体的に考えるべきでしょう。
試用期間で「会社と合わない」と感じた場合にすべきこと
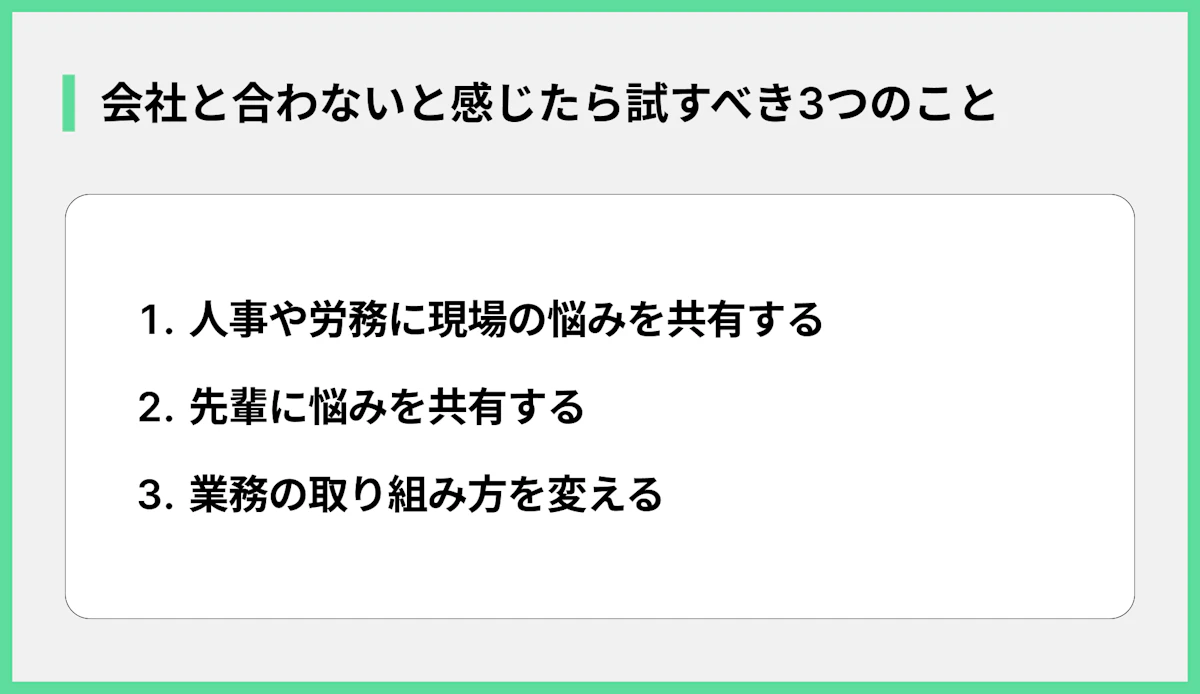
人事や労務に現場の悩みについて共有する
直属の上司に直接悩みを相談しにくい、あるいは相談しても解決しないという場合は、人事部や労務部といった部署に相談するのも一つの有効な手段です。これらの部署は、従業員の労働環境を管理し、社内の人間関係やハラスメントなどの問題に対応する役割を担っています。現場の直属の上司とは異なる、より客観的で中立的な立場から話を聞いてくれるでしょう。相談することで、部署異動や業務内容の調整など、自分では思いつかなかった解決策を提案してもらえる可能性もあります。一人で抱え込まず、会社組織の中の相談窓口を積極的に活用することで、状況が好転するかもしれません。退職を決める前に、一度試してみる価値は十分にあります。
先輩に悩みを共有する
同じ部署やチームで働く先輩社員に悩みを相談してみるのも良い方法です。自分と同じような経験をしていたり、社内の事情に詳しかったりするため、より具体的で実践的なアドバイスをもらえる可能性があります。上司や人事部には話しにくいような、現場のリアルな雰囲気や人間関係の悩みについても、共感を得ながら聞いてもらえるでしょう。「自分も入社したての頃は同じことで悩んだよ」といった一言が、精神的な支えになることもあります。また、先輩がどのようにして困難を乗り越えてきたのかを知ることは、今後の働き方のヒントにもなります。堅苦しく考えず、ランチや休憩時間などに「少しご相談があるのですが」と気軽に声をかけてみてはいかがでしょうか。
業務の取り組み方を変える
「仕事が合わない」と感じる原因が、実は自分自身の業務への取り組み方にある場合もあります。退職を考える前に、一度仕事の進め方を見直してみましょう。例えば、タスクの優先順位付けがうまくいかず、常に時間に追われているのであれば、ToDoリストを作成したり、ポモドーロテクニックのような時間管理術を試したりするのも一つの手です。また、指示の受け方や報告・連絡・相談の仕方を変えるだけで、上司や同僚とのコミュニケーションが円滑になり、仕事が進めやすくなることもあります。いきなり大きな変化を目指すのではなく、小さな工夫から始めてみましょう。自分でコントロールできる範囲で改善努力をしてみることで、仕事に対する見方や手応えが変わり、やりがいを感じられるようになるかもしれません。
試用期間で退職すべき場合に注意すべきこと
転職先を決めてから退職する
試用期間中に退職を決意した場合でも、すぐに退職届を出すのではなく、まずは在職しながら転職活動を始めることを強く推奨します。次の職場が決まっていない状態で退職してしまうと、収入が途絶え、経済的な不安から焦りが生じます。その焦りが原因で、次の転職先をじっくりと吟味することなく、安易に決めてしまい、再び同じようなミスマッチを繰り返してしまうリスクが高まります。在職中であれば、安定した収入を得ながら、精神的な余裕を持って企業研究や自己分析に取り組むことができます。納得のいく転職を実現するためにも、まずは次のステージを確保してから、現在の職場を退職するという手順を踏むことが賢明です。
転職先を決めずに退職しない方がいい理由
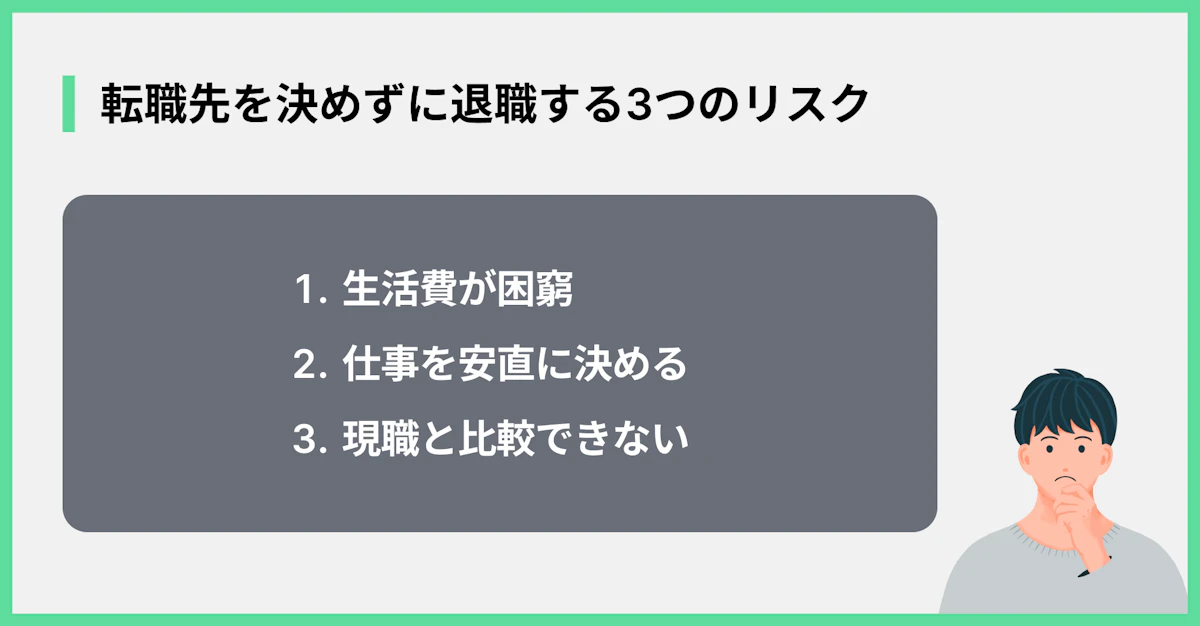
生活費が困窮する
転職先を決めずに退職した場合に直面する最大のリスクは、経済的な困窮です。毎月の収入が途絶えるため、家賃や食費、光熱費などの支払いは、すべて貯蓄に頼ることになります。失業保険の給付もありますが、自己都合退職の場合は待機期間があり、すぐには受け取れません。また、給付額も在職中の給与よりは少なくなります。貯蓄がみるみる減っていく状況は、大きな精神的ストレスとなり、「早く次の仕事を見つけなければ」という焦りを生み出します。この焦りは冷静な判断力を鈍らせ、本来であれば選ばないような条件の良くない求人にも飛びついてしまう原因となりかねません。安定した生活基盤があってこそ、余裕を持った転職活動ができるのです。
次の仕事を安直に決めてしまう可能性が高まる
無職の期間が長引くことへの焦りは、転職活動において非常に危険な罠となります。経済的なプレッシャーや社会から取り残されたような孤独感から、「どこでもいいから早く内定が欲しい」という心理状態に陥りやすくなります。そうなると、企業の理念や文化、業務内容、労働条件などを十分に吟味することなく、内定が出たという理由だけで安直に入社を決めてしまうリスクが高まります。その結果、入社後に「こんなはずではなかった」と再びミスマッチを感じ、短期離職を繰り返してしまう悪循環に陥る可能性があります。今回の退職の経験を次に活かすためにも、焦らず、自分の軸をしっかりと持って転職活動に臨むことが不可欠です。そのためには、在職中に活動することが望ましいのです。
現職と転職先の比較ができなくなる
在職しながら転職活動を行うことの大きなメリットの一つに、現職と転職候補先の企業を客観的に比較検討できる点が挙げられます。現在の職場の給与、福利厚生、労働時間、人間関係、仕事内容などを基準として、「次の職場では何を改善したいのか」「どんな条件を優先したいのか」を明確にすることができます。しかし、退職してしまうと、比較の基準となる現職がなくなってしまいます。記憶の中の現職と求人情報を比べることになりますが、時間が経つにつれて記憶は曖昧になりがちです。また、「無職」という状況が判断を曇らせることもあります。リアルな比較対象があるうちに活動することで、より冷静かつ的確に、自分にとって最適な転職先を見極めることができるでしょう。
試用期間中に退職する場合の伝え方
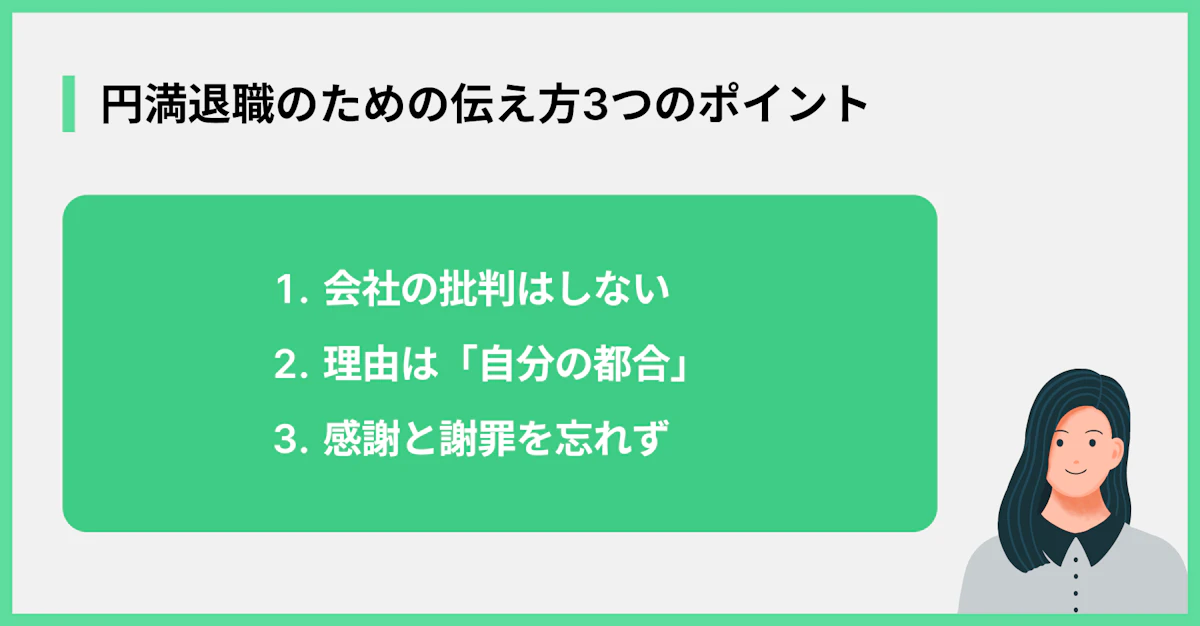
会社の批判は絶対にしない
退職理由を伝える際、たとえ会社に不満があったとしても、それをストレートにぶつけるのは避けるべきです。上司や会社の批判、同僚への不満などを口にすることは、円満退職から最も遠ざかる行為です。感情的になって不満を伝えても、状況が改善されるわけではありませんし、むしろ「社会人としてのマナーがなっていない」という悪印象を残すだけです。狭い業界であれば、悪い評判が次の転職先に伝わってしまうリスクもゼロではありません。後味の悪い別れ方をしても、誰にとっても良いことは一つもありません。立つ鳥跡を濁さずという言葉の通り、これまでお世話になった感謝の気持ちを伝え、お互いに気持ちよく次のステップへ進めるように心がけることが、大人の対応と言えるでしょう。
理由は「自分の都合」として説明する
退職理由を伝える際は、「一身上の都合により」と説明するのが最も一般的で無難な方法です。法律上、労働者は退職理由を詳細に説明する義務はありません。上司から詳しい理由を尋ねられた場合でも、正直にすべてを話す必要はありません。もし何か答えるのであれば、会社の批判ではなく、あくまで自分自身のキャリアプランに関わるポジティブな理由を伝えると良いでしょう。例えば、「自身のキャリアを見つめ直した結果、以前から興味のあった〇〇の分野に挑戦したいという思いが強くなりました」といったように、前向きな姿勢を示すことで、相手も納得しやすく、応援する気持ちで送り出してくれる可能性が高まります。
感謝と謝罪の気持ちを忘れない
試用期間という短い期間であったとしても、採用していただき、仕事を教えてもらったことに対して、まずは感謝の気持ちを伝えることが大切です。そして、会社が期待を寄せて採用し、教育してくれたにもかかわらず、早期に退職することになってしまった事実に対して、誠実に謝罪の意を示しましょう。「短い間でしたが、大変お世話になりました。ご期待に沿えず、このような形となり大変申し訳ございません」といった言葉を添えるだけで、相手に与える印象は大きく変わります。感謝と謝罪を伝えることは、円満な退職を実現するための基本的なマナーです。これにより、余計なトラブルを避け、スムーズに退職手続きを進めることができます。最後まで社会人としての礼儀を忘れずに対応しましょう。
試用期間で辞めると迷惑をかけてしまわない?
確かに迷惑はかかっているが、自分の人生を優先すべき
試用期間で退職することに対して、「会社に多大な迷惑をかけてしまう」と罪悪感を抱く人は少なくありません。確かに、企業は採用や教育にコストと時間をかけているため、早期離職は損失となり、迷惑がかかることは事実です。しかし、だからといって自分に合わない環境で無理に働き続けることは、心身の健康を損ない、貴重な時間を無駄にしてしまうことにつながります。長い目で見れば、それはあなたにとっても会社にとっても不幸な結果を招きかねません。会社への申し訳ない気持ちは持ちつつも、最終的にはあなた自身の人生を最優先に考えるべきです。合わない場所から早期に離れ、自分に合った環境で生き生きと働くことの方が、結果的に社会にとってもプラスになるという視点を持ちましょう。
新たな転職先選びのコツ
自分の適性にあった職種を選ぶ
次の転職で失敗しないためには、今回の退職理由を深く掘り下げ、自己分析を徹底することが不可欠です。「なぜ会社と合わなかったのか」を具体的に言語化してみましょう。仕事内容、人間関係、企業文化、労働条件など、何が一番の要因だったのかを明確にすることで、次に選ぶべき職場の姿が見えてきます。そして、自分の得意なこと、苦手なこと、やりがいを感じる瞬間、大切にしたい価値観などを洗い出し、自分の適性を正しく理解することが重要です。この自己分析が、次の職種選びや企業選びの揺るぎない軸となります。表面的な情報だけでなく、自分の内面と向き合うことで、今度こそ長く働ける天職に巡り会える可能性が高まります。
どんな風に働きたいのかのビジョンを決める
自己分析で自分の適性が見えてきたら、次は「どのような働き方を実現したいか」という具体的なビジョンを描きましょう。例えば、「プライベートの時間を大切にしたいので、残業が少なく、年間休日が多い会社がいい」「専門スキルを磨きたいので、研修制度が充実している環境で働きたい」「チームで協力しながら目標を達成することに喜びを感じる」など、できるだけ具体的にイメージすることが大切です。給与、勤務地、企業の規模、キャリアパスといった条件面だけでなく、自分が働く上での「譲れない価値観」を明確にすることで、企業選びの優先順位が定まります。このビジョンが羅針盤となり、数多くの求人情報の中から、本当に自分に合った企業を見つけ出す手助けをしてくれるでしょう。
働き方のビジョンや自分に合った仕事がわからない...
知人や友人に相談してみよう
自分一人で自己分析やキャリアプランを考えると、どうしても主観的になり、視野が狭くなってしまうことがあります。そんな時は、信頼できる知人や友人に相談してみるのがおすすめです。あなたのことをよく知る第三者の視点から、「あなたはこういう作業が得意だよね」「〇〇な雰囲気の職場が合っているんじゃない?」といった、自分では気づかなかった強みや適性を指摘してくれるかもしれません。客観的なフィードバックをもらうことで、より深く自己理解を進めることができます。また、自分の考えを言葉にして誰かに話すこと自体が、頭の中を整理する良い機会にもなります。一人で抱え込まず、身近な人の力を借りてみましょう。
知人や友人に相談できる人がいなければキャリアアドバイザーに相談するのがおすすめ
身近にキャリアの相談ができる相手がいない、あるいは友人には話しにくいと感じる場合もあるでしょう。そんな時は、転職のプロであるキャリアアドバイザーに相談するのが非常に有効な選択肢です。キャリアアドバイザーは、転職市場の動向や様々な業界・職種に関する深い知識を持っています。何よりも、数多くの求職者の悩みを聞き、転職を成功に導いてきた実績があります。その豊富な経験に基づき、客観的かつ専門的な視点から、あなたに合ったキャリアの方向性を一緒に考え、具体的なアドバイスを提供してくれます。自分一人では見つけられなかった新たな可能性に気づかせてくれる、心強いパートナーとなるでしょう。
キャリアアドバイザーに相談するメリット
豊富な職業相談経験から最適な職種を紹介してもらえる
キャリアアドバイザーは、いわば「キャリアの専門家」です。日々、多くの求職者と面談し、それぞれのスキル、経験、価値観、そして悩みと向き合っています。その膨大な相談経験の蓄積があるからこそ、あなたの漠然とした希望や不安を丁寧にヒアリングし、言語化する手助けをしてくれます。そして、あなた自身も気づいていない潜在的な強みや適性を見出し、それを活かせる最適な職種を提案してくれます。「どんな仕事が向いているかわからない」という段階からでも、対話を通じて具体的なキャリアパスを描き出してくれるのが、プロに相談する大きなメリットです。一人で悩むよりも、はるかに効率的かつ効果的に、自分に合った仕事を見つけられるでしょう。
豊富な求人から最適な会社を紹介してもらえる
転職エージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有しています。これらは、企業が特定のスキルを持つ人材をピンポイントで探している場合や、競合他社に知られずに採用活動を進めたい場合などに利用される求人です。キャリアアドバイザーに相談することで、こうした自分一人ではアクセスできない優良な求人に出会えるチャンスが広がります。また、アドバイザーは企業の内部情報(社風や残業時間の実態、部署の雰囲気など)にも精通していることが多く、求人票だけではわからないリアルな情報を提供してくれます。数多くの選択肢の中から、あなたの希望や適性に本当にマッチした、ミスマッチの少ない会社を紹介してもらえる点も大きな魅力です。
Zキャリアなら転職まで無料でキャリアアドバイザーのサポートを受けられる
Zキャリアでは、これらすべてのサポートを無料で受けることができます。経験豊富なキャリアアドバイザーが、あなたの悩みや希望を丁寧にヒアリングし、自己分析のお手伝いから最適な求人の紹介、さらには履歴書・職務経歴書の添削、面接対策まで、転職活動のあらゆるプロセスをマンツーマンで徹底的にサポートします。入社後のフォローアップもあり、安心して新しいキャリアをスタートできる体制が整っています。試用期間での退職に悩み、次のステップに不安を感じているなら、まずはZキャリアに相談してみませんか。あなたのキャリアの可能性を最大限に引き出すお手伝いをします。登録は簡単3分で完了します。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)



