- 人事評価に納得いかない時の冷静な対処法
- 退職を考える前に知っておくべきメリット・デメリット
- 後悔しないための転職活動の進め方
- 評価の悩みを相談できる専門家の存在
人事評価に納得いかず退職を考える前に確認すること
人事評価に納得がいかず、すぐに「退職」を考えるのは少し早いかもしれません。まずは冷静に自分の状況を確認することが大切です。具体的な確認事項は以下の通りです。
- なぜ評価に不満を感じるのか理由を整理する
- 会社の評価基準を改めて確認する
- 感情的に行動するリスクを理解する
- 周囲の信頼できる人に相談してみる
各項目について、詳しく見ていきましょう。
なぜ評価に不満を感じるのか理由を整理する
まずは、評価への不満を具体的に書き出すことから始めましょう。「なんとなく納得できない」というモヤモヤした気持ちのままでは、解決の糸口は見つかりません。
例えば、「同期のA君と同じくらい頑張ったのに、自分だけ評価が低かった」「大きなプロジェクトを成功させたのに、給料に全く反映されなかった」など、具体的な出来事を思い出して紙に書き出してみてください。
そうすることで、自分が何に対して不満を感じているのかがハッキリと見えてきます。上司に相談する際にも、感情的にならずに具体的な事実を伝えられるようになりますし、今後の自分の行動を決める上でも重要な判断材料になります。
会社の評価基準を改めて確認する
次に、会社の評価基準がどうなっているのかを改めて確認してみましょう。自分の「頑張り」と、会社が「評価するポイント」がズレている可能性もあります。
就業規則や社内の資料に、評価項目や基準が書かれているはずです。例えば、工場勤務であれば「生産目標の達成率」や「ミスの少なさ」、営業職であれば「売上金額」などが明確な基準になっていることが多いです。
もし評価基準が曖昧だったり、見つけられなかったりした場合は、上司や人事部に直接聞いてみるのも一つの手です。評価のルールを知ることで、なぜ今回の評価になったのか、次に何を頑張れば評価されるのかが見えてくるかもしれません。
感情的に行動するリスクを理解する
納得できない評価を受けると、「もう辞めてやる!」と感情的になってしまう気持ちもわかります。ですが、勢いで退職を決めてしまうと後悔につながるケースも少なくありません。
次の仕事が決まっていないまま退職すると、収入が途絶えてしまい、焦りから自分に合わない会社を選んでしまう可能性があります。また、一度「辞めます」と伝えてしまうと、撤回するのは非常に難しいです。
まずは一呼吸おいて、冷静になる時間を作りましょう。感情的になっている時の大きな決断は避けるのが賢明です。自分の将来を考え、計画的に行動することが、結果的に良い方向へ進むためのカギとなります。
周囲の信頼できる人に相談してみる
一人で悩みを抱え込んでいると、考えが堂々巡りになってしまいがちです。信頼できる第三者の意見を聞くことで、新しい視点や解決策が見つかることがあります。
家族や親しい友人など、社外の人に話してみるのがおすすめです。会社の人間関係に縛られずに、客観的なアドバイスをくれるでしょう。ただし、会社の同僚に相談する場合は、話が変に広まってしまわないように相手を慎重に選ぶ必要があります。
誰かに話すことで、自分の気持ちが整理されるだけでも、心の負担は軽くなります。一人で抱え込まず、周りの人を頼ることも大切です。
人事評価への不満を上司に伝える際のポイント
自分の気持ちや状況を整理した上で、やはり納得できないと感じるなら、上司に直接伝えてみるのも一つの方法です。伝え方次第では、評価が見直される可能性もあります。
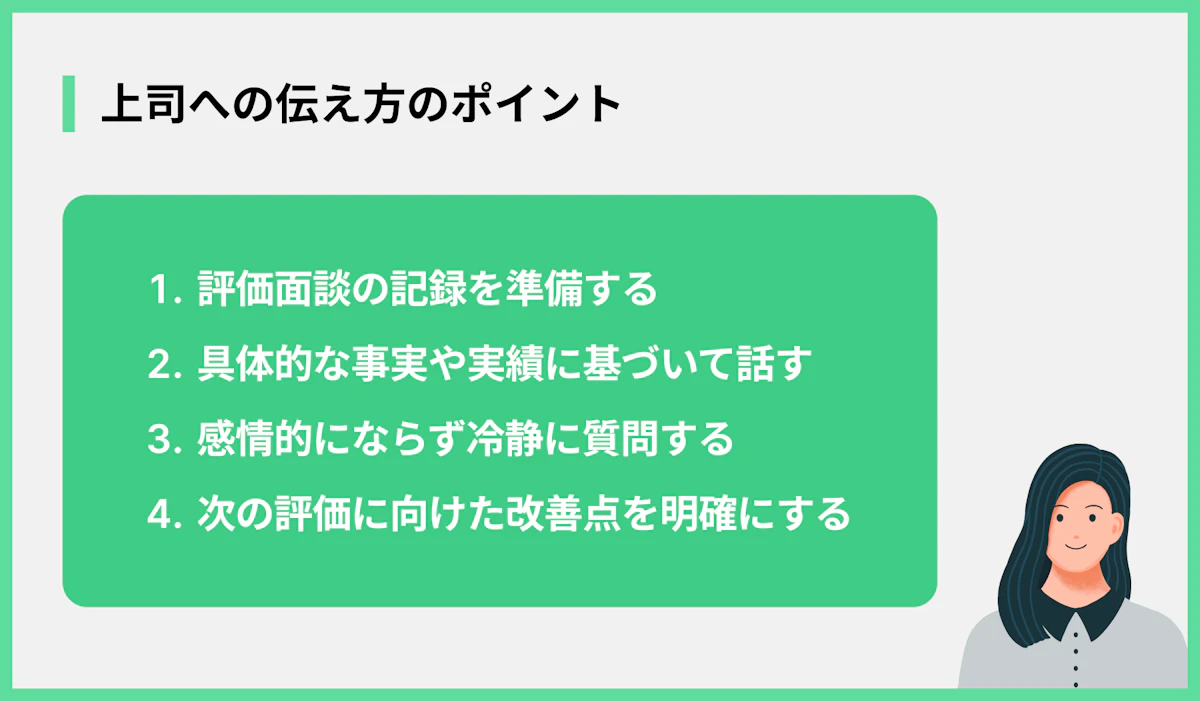
詳しく解説していきます。
評価面談の記録を準備する
もし評価面談の際にメモを取っていたら、それを見返してみましょう。面談でのやり取りを思い出すことが、話の土台になります。
上司からどのようなフィードバックがあったか、どのような点を評価され、どのような点を課題として指摘されたかなどを確認します。もし記録がなければ、覚えている範囲で書き出してみましょう。
「面談の際には〇〇と伺いましたが、今回の評価について、もう少し詳しく教えていただけますか?」というように、面談内容を基に質問することで、話がスムーズに進みやすくなります。客観的な記録は、冷静な話し合いのための重要なツールです。
具体的な事実や実績に基づいて話す
上司に話す際は、「頑張ったのに」といった抽象的な表現ではなく、誰が見てもわかる具体的な実績を伝えることが重要です。
例えば、「〇〇というプロジェクトで、不良品率を5%改善しました」「新しい作業手順を提案し、チーム全体の作業時間が10%短縮されました」のように、数字を使って説明すると説得力が増します。
自分の仕事の成果を客観的なデータとして示すことで、上司も評価を見直すきっかけを掴みやすくなります。感情論ではなく、事実に基づいた話し合いを心がけましょう。
感情的にならず冷静に質問する
不満を伝える際、攻撃的な口調にならないように注意しましょう。「どうして評価が低いんですか!」と感情的に問い詰めても、相手は心を閉ざしてしまいます。
「今回の評価について、自分なりに振り返ってみたのですが、自己評価と少し差があるように感じました。今後のために、どの点が評価に繋がらなかったのか、具体的に教えていただけますでしょうか?」のように、あくまで「教えてほしい」という姿勢で質問するのがポイントです。
冷静に、そして前向きに改善したいという意欲を見せることで、上司も真剣に話を聞いてくれる可能性が高まります。
次の評価に向けた改善点を明確にする
ただ不満を伝えるだけでなく、今後のためにどうすれば良いかを一緒に考えてもらう姿勢が大切です。
「次の評価でA評価をいただくためには、具体的にどのような点を改善すればよろしいでしょうか?」といった形で、未来に向けた質問をしてみましょう。これにより、上司はあなたの成長意欲を高く評価してくれるかもしれません。
具体的な目標や改善点が明らかになれば、仕事へのモチベーションも再び湧いてくるはずです。今回の話し合いを、自分自身の成長の機会と捉えることができれば、不満だけの時間で終わらせずに済みます。
不当な人事評価はパワハラに該当する?
あまりにも理不尽な評価が続く場合、「これはパワハラではないか?」と疑問に思うこともあるでしょう。人事評価がパワハラと見なされるケースについて解説します。
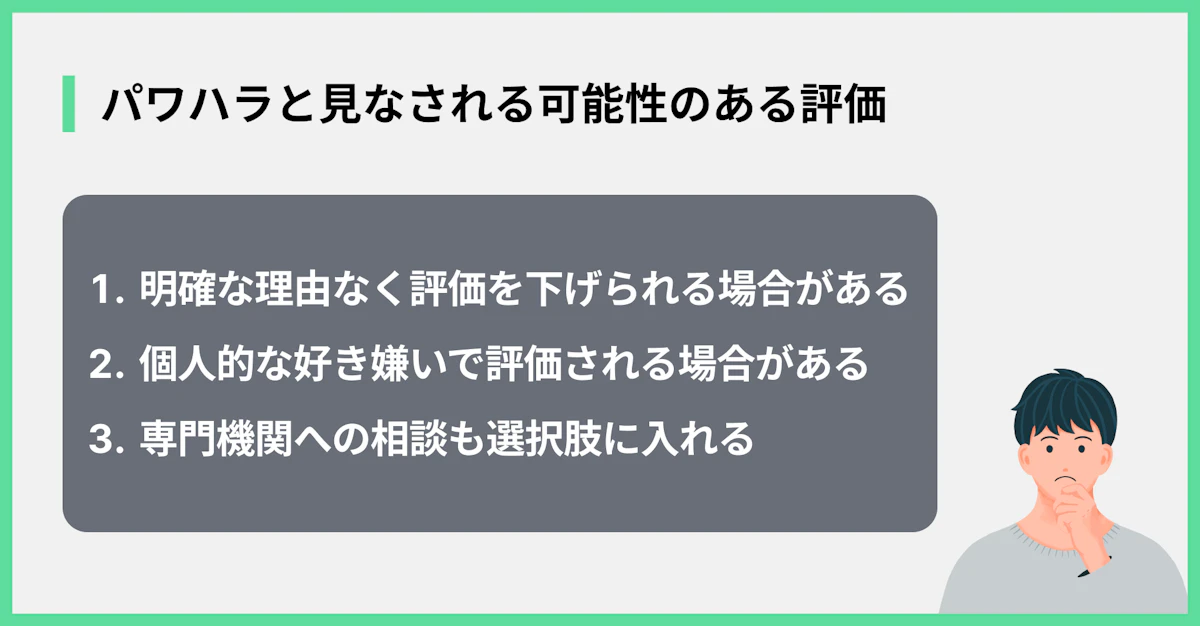
詳しく解説していきます。
明確な理由なく評価を下げられる場合がある
合理的な説明がなく評価を著しく下げることは、パワハラに該当する可能性があります。
例えば、他の社員と比べて明らかに高い成果を出しているにもかかわらず、何の理由も示されずに最低評価をつけられたり、これまで問題なくこなしてきた業務について、突然「能力不足」というレッテルを貼られたりするケースです。
会社の人事評価には、ある程度の裁量が認められていますが、それが社会通念上、許される範囲を逸脱していると判断されれば、不当な評価と見なされることがあります。
個人的な好き嫌いで評価される場合がある
上司の個人的な感情によって評価が左右される場合も、パワハラと判断される可能性があります。
「あいつは気に入らないから」といった理由で、仕事の成果とは無関係に低い評価をつけたり、逆に気に入っている部下だけを贔屓して高く評価したりするのは、公平な評価とはいえません。
他にも、飲み会の誘いを断ったことへの腹いせや、プライベートな関係のもつれなどを理由に評価を下げることも、評価権の濫用と見なされることがあります。
専門機関への相談も選択肢に入れる
もし、社内の相談窓口や人事部に相談しても解決しない場合や、相談すること自体が難しい状況であれば、社外の専門機関に相談することも一つの方法です。
各都道府県の労働局にある「総合労働相談コーナー」では、解雇やいじめ、パワハラなど、労働に関するあらゆる問題について無料で相談に乗ってくれます。
法的な問題に発展しそうな場合は、弁護士に相談することも考えられますが、まずは公的な窓口で専門家の意見を聞いてみるのが良いでしょう。一人で抱え込まず、客観的なアドバイスを求めることが大切です。
人事評価が原因でやる気をなくした時のサイン
納得できない評価は、仕事へのモチベーションを大きく低下させます。自分でも気づかないうちに、心や行動にサインが出ているかもしれません。以下の項目に当てはまらないか確認してみましょう。
- 仕事へのモチベーションが湧かなくなる
- 必要最低限の業務しか行わなくなる
- スキルアップへの意欲が低下する
- 職場でのコミュニケーションを避けるようになる
詳しく解説していきます。
仕事へのモチベーションが湧かなくなる
朝、会社に行くのが憂鬱になるなど、以前は感じなかったネガティブな気持ちが続くのは、モチベーションが低下しているサインです。
「頑張ってもどうせ評価されない」という諦めの気持ちが生まれると、仕事に対する情熱や楽しさを感じられなくなってしまいます。以前はやりがいを感じていた仕事も、ただの「作業」のように感じられるようになるでしょう。
このような状態が続くと、精神的にも辛くなってしまいます。自分の心の状態を無視せず、早めに対処することが大切です。
必要最低限の業務しか行わなくなる
「言われたことだけやればいい」という考えになり、自発的な行動をしなくなるのも危険なサインです。これは「サイレント退職」とも呼ばれる状態に近いかもしれません。
以前なら「もっとこうすれば良くなるかも」と考えて改善提案をしたり、頼まれていない仕事も率先して手伝ったりしていたのに、今は定時で帰ることしか考えていない、という場合は要注意です。
このような働き方は、短期的には楽かもしれませんが、長期的には自身の成長の機会を失うことにつながります。
スキルアップへの意欲が低下する
仕事へのやる気がなくなると、新しい知識を学んだり資格を取ったりする意欲も薄れていきます。
「この会社で頑張っても無駄だ」と感じると、その会社で役立つスキルを身につけようという気持ちが起きなくなります。勉強会への参加や、関連書籍を読むといった自己投資をしなくなるでしょう。
スキルアップを止めてしまうと、将来的に転職を考えた際に、アピールできる強みがなく不利になってしまう可能性もあります。自分の市場価値を維持するためにも、学び続ける姿勢は重要です。
職場でのコミュニケーションを避けるようになる
同僚との雑談やランチを避けるようになったり、会議で全く発言しなくなったりするのも、モチベーション低下のサインの一つです。
会社への不満や不信感が、職場の人との関わりを面倒に感じさせる原因になります。周りから見ると「付き合いが悪い」「やる気がない」と誤解され、さらに孤立してしまうという悪循環に陥ることもあります。
良好な人間関係は、仕事を円滑に進める上で重要です。コミュニケーションを完全に断ってしまう前に、なぜそうなってしまったのか、自分の心と向き合う時間が必要です。
評価が不満でも今の会社に留まるメリット
退職や転職にはエネルギーが必要です。評価への不満はあっても、今の会社に留まることのメリットを冷静に考えてみることも大切です。
- 安定した収入や環境を維持できる
- 慣れた人間関係や業務内容で働ける
- 転職活動にかかる手間やリスクを避けられる
詳しく解説していきます。
安定した収入や環境を維持できる
今の会社で働き続ける最大のメリットは、毎月決まった給料がもらえる安心感でしょう。生活の基盤が安定していることは、精神的な余裕にもつながります。
転職活動中は収入が不安定になるリスクがありますし、新しい職場がすぐに決まるとも限りません。また、福利厚生や労働条件など、今の環境が実は恵まれているという可能性もあります。
評価以外の部分、例えば給与、休日、勤務地、福利厚生など、労働条件全体を客観的に見つめ直してみましょう。
慣れた人間関係や業務内容で働ける
長年勤めていると、気心の知れた同僚や仕事の進め方など、働きやすい環境が整っていることが多いです。
新しい職場では、人間関係を一から築き、仕事のやり方も全て覚え直さなければなりません。これは想像以上にストレスがかかることです。
評価に不満はあっても、職場の人間関係が良好であったり、仕事内容自体は好きだったりする場合、安易に環境を変えることが必ずしも良い結果になるとは限りません。
転職活動にかかる手間やリスクを避けられる
転職活動は、時間も労力もかかる大変な作業です。働きながらの活動となるとなおさらです。
履歴書や職務経歴書の作成、企業研究、面接対策など、やるべきことはたくさんあります。面接のために仕事を休む必要も出てくるかもしれません。
また、転職したからといって、必ずしも今より良い会社に出会える保証はありません。こうした転職のリスクや手間を考えれば、今の会社で評価を上げる努力をする方が、結果的に近道になる可能性もあります。
評価への不満から退職する場合のデメリット
一方で、評価への不満を理由に退職・転職する場合には、デメリットやリスクも存在します。決断する前に、マイナス面もしっかりと理解しておきましょう。
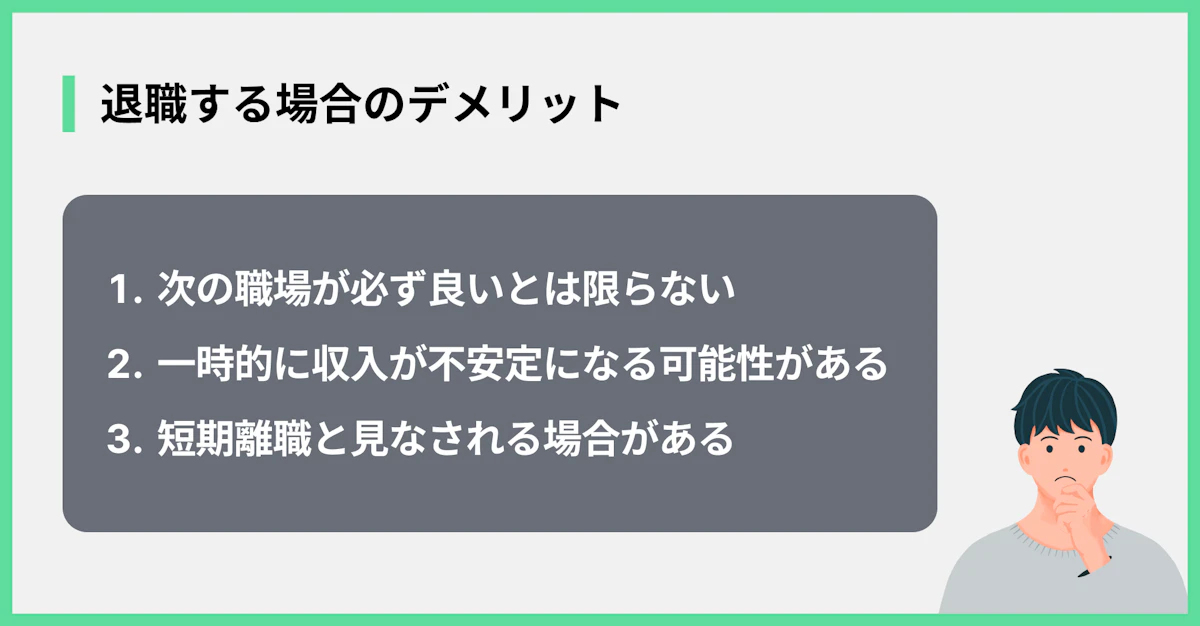
詳しく解説していきます。
次の職場が必ず良いとは限らない
転職活動で一番気をつけたいのが、隣の芝生が青く見えてしまうことです。求人情報や面接だけでは、その会社の内情を全て知ることはできません。
「評価制度がしっかりしている」と聞いて入社したのに、実際は上司のさじ加減で決まっていたり、人間関係がギスギスしていたりする可能性もゼロではありません。
今の会社への不満から逃げるためだけの転職は、同じような失敗を繰り返す原因になります。次の会社に何を求めるのか、企業選びの軸をしっかり持つことが大切です。
一時的に収入が不安定になる可能性がある
すぐに転職先が決まるとは限らないため、退職後の生活費については計画的に考えておく必要があります。
在職中に転職活動を進めるのが理想的ですが、もし退職してから活動を始める場合は、少なくとも3ヶ月分程度の生活費を貯金しておくと安心です。
収入がない状態での転職活動は、「早く決めなければ」という焦りを生み、妥協した会社選びにつながりやすくなります。金銭的な不安は、冷静な判断を鈍らせる大きな要因になることを覚えておきましょう。
短期離職と見なされる場合がある
特に、入社してから短い期間で退職する場合、採用担当者に「またすぐに辞めてしまうのではないか」という印象を与えてしまう可能性があります。
一般的に、3年未満での離職は「短期離職」と見なされやすい傾向があります。もちろん、退職理由をきちんと説明できれば問題ありませんが、採用に慎重になる企業があるのも事実です。
「評価に納得できなかったから」というネガティブな理由だけを伝えるのではなく、それをバネに「次はこうなりたい」という前向きな意欲をアピールすることが重要になります。
納得のいく転職を実現するための準備
退職・転職を決意したなら、次は後悔しないための準備を始めましょう。計画的に進めることが、成功へのカギとなります。
- 転職理由を前向きな言葉でまとめる
- 自分の市場価値を客観的に把握する
- 企業選びで譲れない条件を明確にする
- 在職中に転職活動を始める
詳しく解説していきます。
転職理由を前向きな言葉でまとめる
面接で必ず聞かれるのが転職理由です。その際に、前の会社の不満だけを話すのはNGです。
「人事評価に納得できなかった」という事実を、「頑張りを正当に評価してくれる環境で、自分の実力を試し、もっと成長したいと考えたため」のように、ポジティブな言葉に変換しましょう。
採用担当者は、転職理由からあなたの仕事への姿勢や向上心を見ています。不満をバネに、次へ進もうとする前向きな姿勢をアピールすることが大切です。
自分の市場価値を客観的に把握する
今の会社での評価は一旦横に置いて、世の中から見て自分にどれくらいの価値があるのかを知ることは非常に重要です。
これまでに経験してきた業務内容や、身につけたスキル、取得した資格などを全て書き出してみましょう。自分では「当たり前」だと思っていた経験が、他の会社では高く評価されることもあります。
もし自分一人で判断するのが難しければ、転職エージェントなどのプロに相談してみるのがおすすめです。客観的な視点から、あなたの強みや市場価値を教えてくれるでしょう。
企業選びで譲れない条件を明確にする
「給料が高い」「休みが多い」など、漠然とした希望だけでは、自分に合った会社を見つけるのは難しいです。転職先に何を求めるのか、優先順位をつけることが大切です。
「頑張りが給与に反映される評価制度」「未経験からでもスキルアップできる研修制度」「チームで協力し合う社風」など、自分が働く上で絶対に譲れない条件を3つほどリストアップしてみましょう。
この「軸」がしっかりしていれば、求人情報に惑わされることなく、本当に自分に合った企業を選び抜くことができます。
在職中に転職活動を始める
できる限り、今の会社に在籍しながら転職活動を進めることを強くおすすめします。
先にも述べた通り、収入が途絶えるリスクを避けられるのが最大のメリットです。金銭的な余裕は、心の余裕につながり、焦らずにじっくりと企業を選ぶことができます。
また、「現職で働きながらも、次のステップのために努力している」という姿は、採用担当者にもポジティブな印象を与えます。忙しくて大変な面もありますが、リスクを最小限に抑えるための賢い選択といえるでしょう。
人事評価の悩みは転職のプロに相談する
人事評価の悩みや、それをきっかけとした転職活動は、一人で進めるには不安なことも多いでしょう。そんな時は、転職のプロである転職エージェントに相談するのがおすすめです。
- 自分の強みを客観的に評価してもらえる
- 評価制度が整った企業を紹介してもらえる
- 面接での効果的なアピール方法がわかる
詳しく解説していきます。
自分の強みを客観的に評価してもらえる
今の会社では評価されなかった経験やスキルも、プロの視点から見れば大きな強みになることがあります。
キャリアアドバイザーとの面談を通して、自分では気づかなかったアピールポイントを発見できます。客観的な自己分析は、自信を持って転職活動に臨むための第一歩です。
今の会社の評価が全てではありません。世の中には、あなたの価値を正しく評価してくれる場所が必ずあります。
評価制度が整った企業を紹介してもらえる
転職エージェントは、各企業の内部情報に詳しいのが強みです。求人票だけではわからない、リアルな評価制度や社風について教えてもらえます。
「成果がきちんと給与に反映される会社」「頑張ったプロセスも評価してくれる会社」など、あなたの希望に合った評価制度を持つ企業を紹介してもらえるため、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
もう評価で悩みたくない、という気持ちに寄り添った企業探しを手伝ってくれる、心強いパートナーです。
面接での効果的なアピール方法がわかる
人事評価への不満を、面接でどのように伝えれば好印象になるか、具体的なアドバイスをもらえます。
職務経歴書の書き方から、面接での受け答えの練習まで、選考を突破するためのサポートをトータルで受けられます。ネガティブになりがちな転職理由も、プロの手にかかれば強力なアピール材料に変わります。
一人で対策するよりも、はるかに効率的かつ効果的に転職活動を進めることができるでしょう。
Zキャリアのエージェントに相談してみよう
人事評価に納得できず、退職や転職を考えているなら、ぜひ一度Zキャリアのエージェントに相談してみてください。
Zキャリアは、特にZ世代のノンデスクワーカーの転職支援に強みを持っています。あなたのこれまでの頑張りや経験を丁寧にヒアリングし、その価値を正しく評価してくれる企業を一緒に探します。
登録も相談も全て無料です。一人で悩み続ける前に、まずは一歩を踏み出してみませんか。あなたの新しいキャリアのスタートを、全力でサポートします。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)



