- 休めない会社で働き続けるデメリット
- 休めない状況から抜け出すための対処法
- しっかり休めるホワイトな会社の見つけ方
ブラック企業で休めないのはなぜ?考えられる5つの原因
「休みを取りたい」と伝えても、なぜかいつも休めない。その背景には、会社側が抱える構造的な問題が隠されていることが多いです。具体的な原因として、以下の項目が考えられます。
- 代わりがいないと言われ断れない
- 常に人手不足で業務が回らない
- 1人勤務体制が常態化している
- 休むことは悪だという風潮がある
- 上司からのパワハラで休むに休めない
各項目について、詳しく見ていきましょう。
代わりがいないと言われ断れない
「君が休むと仕事が回らない」「代わりの人がいないからお願い」といった言葉で、責任感に訴えかけられて休めないケースは非常に多いです。特に真面目で責任感の強い人ほど、自分が休むことで周りに迷惑がかかると思い、無理をして出勤してしまいがちです。
ですが、本来は従業員がいつでも休めるように人員を調整するのが会社の責任です。一人の従業員が休んだだけで業務が滞ってしまう状態は、会社の体制そのものに問題があると言えます。個人の責任ではないため、過度に罪悪感を抱える必要は全くありません。
常に人手不足で業務が回らない
慢性的な人手不足も、休みが取れない大きな原因の一つです。求人を出しても人が集まらない、または採用してもすぐに辞めてしまうといった理由で、常にギリギリの人数で仕事を回している職場です。
このような状況では、一人ひとりの業務負担が非常に重くなります。誰かが休むとその人の仕事が他の人にのしかかるため、お互いに休みづらい空気が生まれてしまうのです。これも会社のマネジメントの問題であり、従業員が我慢して解決すべきことではありません。
1人勤務体制が常態化している
店舗勤務や小規模な事業所などで、シフトによっては勤務する従業員が一人だけという状況も、休みを取りにくくする要因です。いわゆる「ワンオペ」と呼ばれる状態で、自分が休むことはお店や事業所を閉めることに直結してしまいます。
これでは、急な体調不良や家庭の事情があっても、代わりの人を見つけない限り休むことができません。精神的なプレッシャーが大きく、常に緊張を強いられる働き方と言えるでしょう。会社は、緊急時にも対応できるような複数人体制を整える義務があります。
休むことは悪だという風潮がある
「体調管理も仕事のうち」「みんな頑張っているのだから、休むのは甘えだ」といった、根性論や精神論が根付いている職場も存在します。このような会社では、有給休暇を取得すること自体に罪悪感を抱かせるような雰囲気が蔓延しています。
風邪を引いても出社するのが当たり前、プライベートな用事で休むなんてもってのほか、という空気が職場全体を支配しているのです。このような環境では、心身ともにリフレッシュすることができず、徐々に疲弊していくことになります。
上司からのパワハラで休むに休めない
休みを申請した際に、上司から嫌味やプレッシャーをかけられるパワハラも深刻な問題です。例えば、「なんで休むの?」「その理由、本当に休む必要があるの?」としつこく問い詰められたり、「休むなら、その分の仕事は終わらせてからにして」と無理な要求をされたりするケースです。
このような言動は、労働者の正当な権利である休暇の取得を妨害する行為であり、れっきとしたパワーハラスメントに該当する可能性があります。上司の顔色をうかがわないと休めないような職場は、健全な環境とは言えません。
その休めない状況、法律的にはどうなっている?
「休めないのが当たり前」という空気に慣れてしまうと忘れがちですが、休みを取ることは法律で認められた労働者の権利です。会社のルールや雰囲気よりも、法律が優先されます。具体的な法律上のポイントは、以下の通りです。
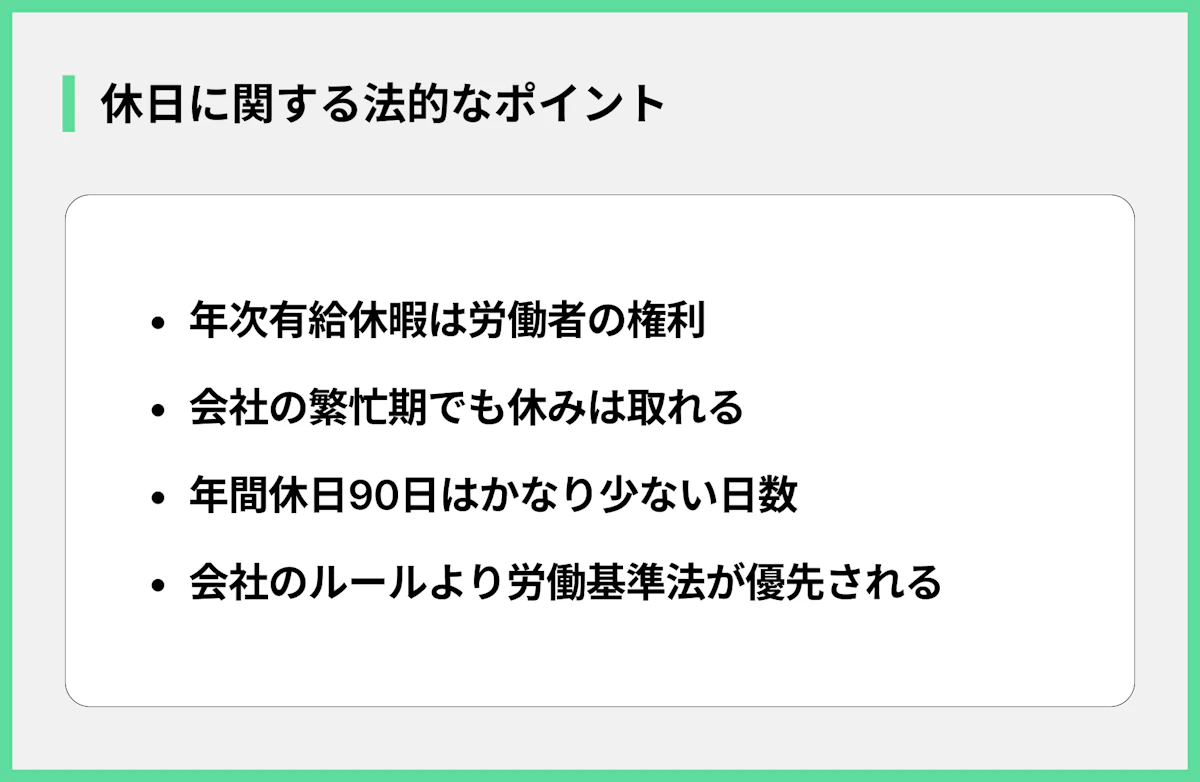
各項目について、詳しく見ていきましょう。
年次有給休暇は労働者の権利
年次有給休暇(有給)は、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を送るために法律で定められた労働者の権利です。一定の条件を満たしたすべての労働者に与えられ、会社は原則として、労働者が希望した日に有給を取得させなければなりません。
有給を取得する際に、会社に理由を詳しく説明する義務もありません。「私用のため」で十分であり、会社側が取得を拒否したり、取得したことで不利益な扱いをしたりすることは違法です。当然の権利として、堂々と申請して問題ありません。
会社の繁忙期でも休みは取れる
会社には「時季変更権」という権利があり、労働者が希望した日に有給を与えると「事業の正常な運営を妨げる」場合に限り、取得日を変更してもらうことが認められています。ですが、これはよほどのことがない限り認められません。
単に「忙しいから」「代わりの人がいないから」といった理由だけで、会社が一方的に有給取得を拒否することはできません。時季変更権が認められるのは、同じ日に多くの従業員が休みを希望するなど、極めて例外的なケースに限られます。
年間休日90日はかなり少ない日数
労働基準法では、休日について「毎週少なくとも1回」または「4週間を通じて4日以上」と定めています。これに加えて、労働時間の上限(1日8時間、週40時間)を守るためには、年間休日は最低でも105日必要になります。
つまり、年間休日が90日というのは、法律で定められた最低ラインを大きく下回っている可能性が高いです。もし、この休日数で時間外労働(残業)代も支払われていないのであれば、明確な法律違反と言えるでしょう。しんどいと感じるのは当然の環境です。
会社のルールより労働基準法が優先される
会社には就業規則という独自のルールがありますが、その内容が労働基準法などの法律を下回っている場合、その部分は無効となります。例えば、就業規則に「有給休暇は会社の許可がなければ取得できない」と書かれていても、法律が優先されるため、労働者は自由に有給を取得できます。
「うちの会社は昔からこうだから」という言い分は通用しません。法律は、労働者を守るための最低限のルールです。自分の働く環境がおかしいと感じたら、一度法律ではどうなっているのかを調べてみることも大切です。
休めない会社で働き続けることのデメリット
休めない会社で我慢して働き続けることは、給料をもらうためとはいえ、多くのデメリットを伴います。心と体の健康だけでなく、将来のキャリアにも悪影響を及ぼす可能性があります。具体的には、以下のデメリットが考えられます。
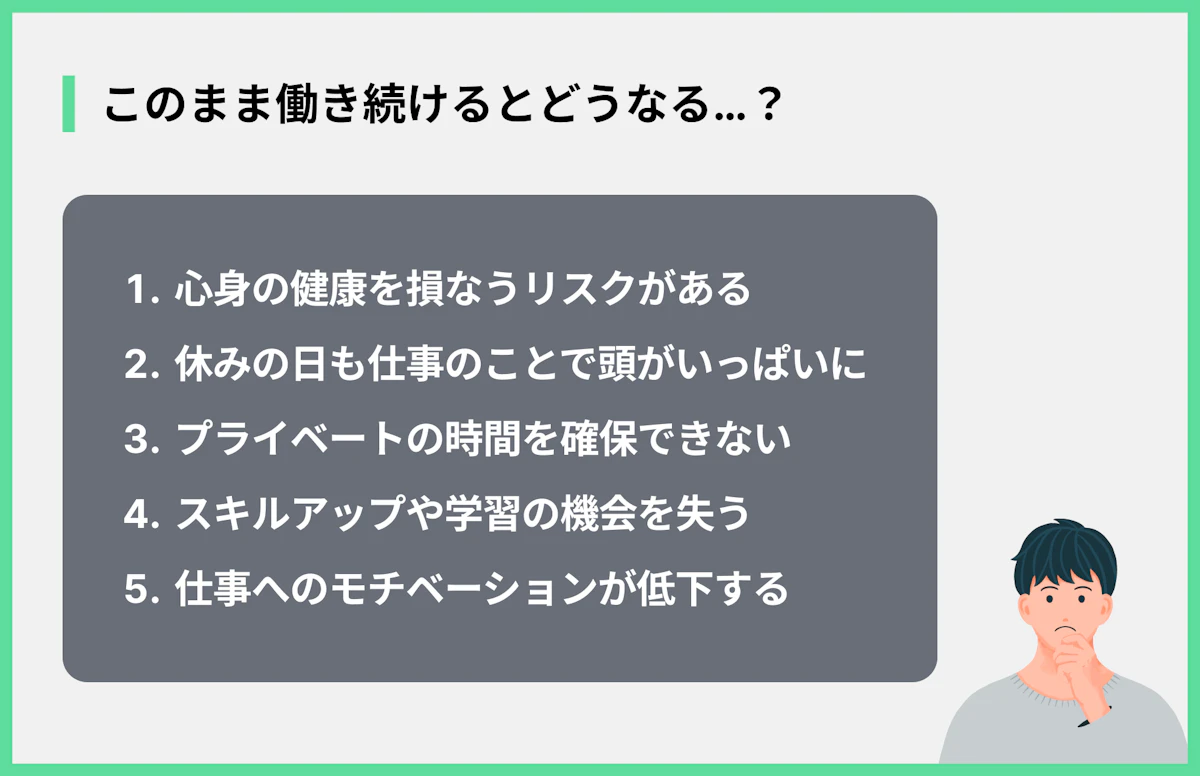
各項目について、詳しく見ていきましょう。
心身の健康を損なうリスクがある
十分な休息が取れないと、心と体の両方に不調をきたすリスクが高まります。体力的には、慢性的な疲労、頭痛、めまいなどの症状が現れることがあります。精神的には、常に緊張状態が続くことでストレスが蓄積し、不安やイライラを感じやすくなるでしょう。
最悪の場合、燃え尽き症候群(バーンアウト)やうつ病といった精神疾患につながることもあります。一度心身のバランスを崩してしまうと、回復には長い時間が必要です。健康は何にも代えがたい財産であり、仕事のために犠牲にするべきではありません。
休みの日も仕事のことで頭がいっぱいになる
せっかくの休日なのに、仕事のプレッシャーから解放されないのも大きなデメリットです。「明日の仕事、大丈夫かな」「上司から連絡が来るかも」といった不安が頭をよぎり、心からリラックスできません。
休日にもかかわらず会社のパソコンを開いたり、仕事用のスマートフォンを常に気にしたりする生活では、休んでいることになりません。オンとオフの切り替えができない状態が続くと、脳は常に疲労したままになり、仕事のパフォーマンスもかえって低下してしまいます。
プライベートの時間を確保できない
休みが取れなければ、友人や家族、恋人と過ごす時間がなくなってしまいます。周りが楽しそうに過ごしているのを見ると、孤独感や疎外感を覚えてしまうこともあるでしょう。趣味や好きなことに打ち込む時間もなくなり、日々の生活から彩りが失われていきます。
仕事は人生の一部ではありますが、すべてではありません。プライベートな時間を充実させることは、人生を豊かにし、仕事への活力を生み出すためにも非常に重要です。その大切な時間を奪われてしまうのは、大きな損失と言えます。
スキルアップや学習の機会を失う
将来のキャリアを考えると、新しいスキルを身につけたり、資格の勉強をしたりする時間は不可欠です。ですが、日々の仕事に追われ、休日も疲れて寝るだけ、という生活では、自己投資のための時間を確保することは困難です。
周りがスキルアップしていく中で自分だけが取り残されてしまうと、将来的に転職を考えた際に不利になる可能性もあります。休めない環境は、長期的な視点で見ると、自分の市場価値を高める機会を奪っていることにもつながるのです。
仕事へのモチベーションが低下する
どれだけ好きな仕事でも、休みなく働き続ければやりがいや楽しさは失われていきます。ただ目の前の業務をこなすだけの日々になり、「何のために働いているのだろう」という虚しさを感じるようになるかもしれません。
仕事へのモチベーションが低下すると、ミスが増えたり、生産性が落ちたりと、悪循環に陥りがちです。会社への不満や不信感も募り、働くこと自体が苦痛になってしまいます。意欲的に仕事に取り組むためにも、適切な休息は絶対に必要です。
休めない現状から抜け出すための具体的な対処法
「このままではいけない」と感じたら、勇気を出して行動に移すことが大切です。現状を変えるためには、いくつかのアクションプランが考えられます。段階的に試せる具体的な対処法は、以下の通りです。
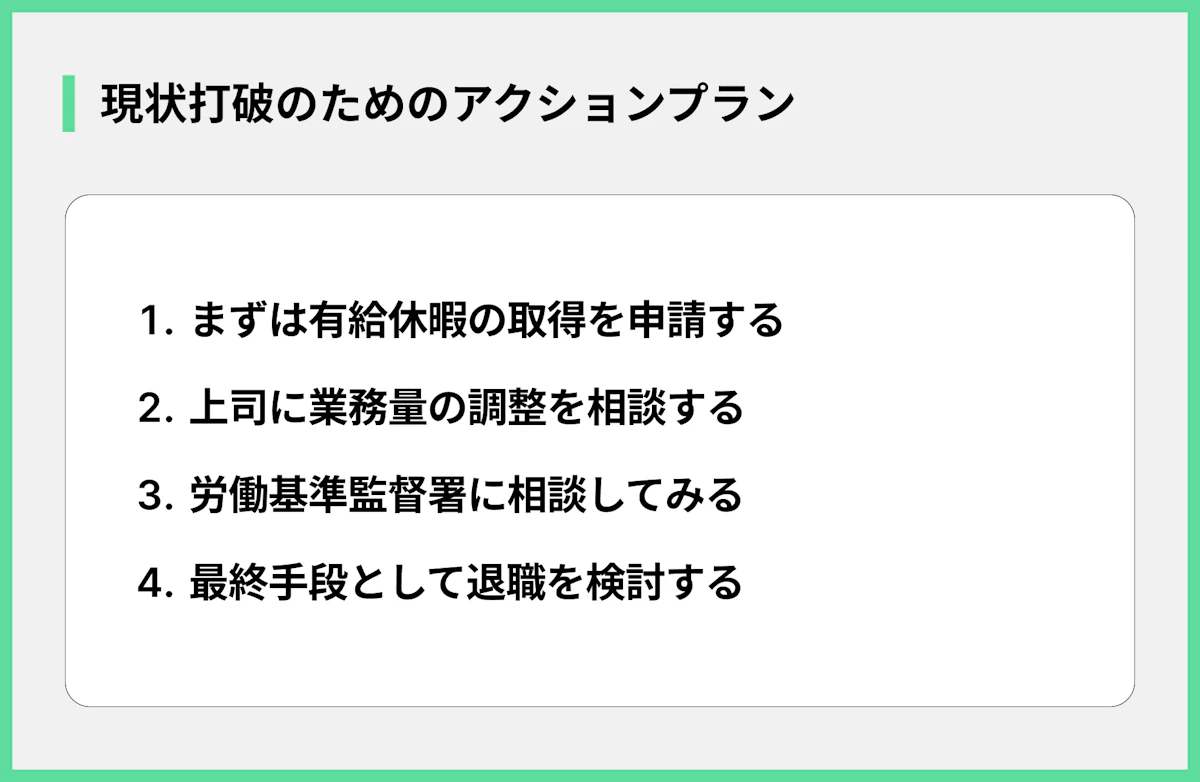
各項目について、詳しく見ていきましょう。
まずは有給休暇の取得を申請する
現状を変えるための第一歩は、勇気を出して有給休暇を申請してみることです。これまで言い出せなかったとしても、権利として主張してみましょう。メールや社内の申請システムなど、書面に残る形で申請するのがおすすめです。
もし理由を聞かれたら「私用のため」とだけ伝えれば問題ありません。ここで申請がすんなり通るようであれば、状況が改善する可能性があります。もし不当に拒否されたり、嫌味を言われたりした場合は、その事実が次のステップに進むための証拠になります。
上司に業務量の調整を相談する
休みが取れない原因が、明らかに多すぎる業務量にある場合は、一度上司に相談してみるのも一つの手です。感情的に「休めなくて辛いです」と訴えるのではなく、「この業務量では、どうしても時間内に終わらせることが難しいです」といったように、客観的な事実を伝えるのがポイントです。
相談することで、業務の分担を見直してくれたり、人員を補充する動きにつながったりする可能性もゼロではありません。ただし、ここで真摯に取り合ってくれないようであれば、その上司や会社に期待するのは難しいかもしれません。
労働基準監督署に相談してみる
会社に直接訴えても改善が見られない場合は、国の機関である労働基準監督署に相談するという選択肢があります。労働基準監督署は、会社が労働基準法などの法律を守っているかを監督する機関です。
匿名での相談も可能で、法律違反の疑いが強いと判断されれば、会社に対して調査や指導が入ることがあります。給料明細やタイムカードの記録、上司とのやり取りの記録など、具体的な証拠があると相談がスムーズに進みます。すぐに解決するとは限りませんが、強力な味方になってくれる可能性があります。
最終手段として退職を検討する
何をしても状況が変わらない、あるいは心身の限界が近いと感じるなら、その会社を辞める(退職する)ことが最も有効な解決策です。自分の健康や人生を犠牲にしてまで、働き続ける必要はありません。
「辞めたら次の仕事が見つからないかも」と不安に思う気持ちも分かります。ですが、世の中には従業員を大切にし、しっかりと休める会社がたくさんあります。自分の心と体を守ることを最優先に考え、新しい環境に飛び込む決断も必要です。
転職で失敗しないためのホワイトな会社の見つけ方
退職を決意し、新しい職場を探すなら、二度と同じ過ちを繰り返さないようにしたいものです。休みをしっかりと確保できる、いわゆる「ホワイト企業」を見つけるためには、いくつかのポイントがあります。具体的な見つけ方は以下の通りです。
- 求人票の年間休日数や福利厚生を確認する
- 企業の口コミサイトでリアルな情報を集める
- 面接で休日や残業について質問する
- 転職エージェントから内部情報を得る
各項目について、詳しく見ていきましょう。
求人票の年間休日数や福利厚生を確認する
求人票をチェックする際は、まず「年間休日」の項目に注目しましょう。目安として「年間休日120日以上」と記載があれば、土日祝日が休みである可能性が高く、比較的休みが多い企業と言えます。逆に105日を下回る場合は注意が必要です。
また、「完全週休2日制(毎週2日の休み)」と「週休2日制(月に1回以上、週2日の休みがある)」の違いもしっかりと確認しましょう。そのほか、夏季休暇や年末年始休暇、リフレッシュ休暇といった特別な休暇制度が整っているかも、働きやすさを測る良い指標になります。
企業の口コミサイトでリアルな情報を集める
実際にその会社で働いていた、あるいは現在働いている人たちのリアルな声が投稿されている口コミサイトも、非常に参考になります。求人票だけでは分からない、社内の雰囲気や有給休暇の取得しやすさといった内部情報を得られる可能性があります。
ただし、口コミは個人の主観で書かれているため、一つの意見を鵜呑みにするのは危険です。良い口コミと悪い口コミの両方を読み比べ、できるだけ多くの情報を集めて総合的に判断することが大切です。
面接で休日や残業について質問する
面接は、企業側が応募者を見極める場であると同時に、応募者が企業を見極める絶好の機会でもあります。休日や残業に関する疑問があれば、臆せずに質問してみましょう。
ただし、聞き方には少し工夫が必要です。「残業はありますか?」と直接的に聞くよりも、「皆さんは、普段どのくらいの時間帯に退社されることが多いですか?」といったように、柔らかい表現で尋ねるのがおすすめです。質問に対して、採用担当者が誠実に答えてくれるかどうかも、企業の体質を見抜くポイントになります。
転職エージェントから内部情報を得る
自分一人での情報収集には限界があります。そこでおすすめなのが、転職のプロである転職エージェントを活用することです。転職エージェントは、多くの企業と直接やり取りをしており、求人票には載っていない独自の内部情報を持っていることがあります。
例えば、実際の残業時間や有給消化率、職場の雰囲気、離職率といった、応募者にとっては非常に価値のある情報を提供してくれる場合があります。ミスマッチを防ぎ、本当に自分に合った会社を見つけるための強力なサポーターとなってくれるでしょう。
今の職場を辞めることに不安を感じるなら
「辞めたいけど、次が見つかるか不安…」「自分にはスキルがないから…」と、退職や転職に対して一歩を踏み出せない気持ちは、誰にでもあるものです。ですが、その不安とどう向き合うかが重要です。不安を解消するための考え方は、以下の通りです。
- 無理に働き続ける必要はない
- 自分の市場価値を客観的に把握する
- 転職のプロに相談して選択肢を広げる
- 次のキャリアプランを一緒に考えてもらう
各項目について、詳しく見ていきましょう。
無理に働き続ける必要はない
まず一番に伝えたいのは、自分の心と体を壊してまで、無理に働き続ける必要はないということです。仕事は、あくまで生活を豊かにするための一つの手段です。その仕事のせいで人生が辛いものになってしまっては、本末転倒です。
今の会社がすべてではありません。世の中には星の数ほど会社があり、自分に合う職場は必ず見つかります。「辞める」という選択は、逃げではなく、自分を守り、より良い未来を手に入れるための前向きな一歩です。
自分の市場価値を客観的に把握する
「自分にはアピールできるスキルや経験がない」と思い込んでいませんか。ですが、自分が当たり前だと思ってやってきた仕事が、他の会社では高く評価されるケースは少なくありません。例えば、人手不足の職場で多様な業務をこなしてきた経験は、「対応力」や「忍耐力」としてアピールできます。
自分では気づいていない強みや価値(市場価値)を客観的に知ることで、転職に対する自信が生まれます。一度キャリアの棚卸しをしてみたり、転職エージェントに相談して自分の市場価値を診断してもらったりするのも良いでしょう。
転職のプロに相談して選択肢を広げる
転職活動を一人で進めようとすると、求人サイトで見つけられる情報しか入ってきません。ですが、世の中には一般には公開されていない「非公開求人」というものが数多く存在します。優良企業や人気のある求人は、非公開で募集されていることが多いです。
転職エージェントに登録すれば、こうした非公開求人を紹介してもらえる可能性があります。自分一人では出会えなかったような、思わぬ優良企業との接点が生まれるかもしれません。相談することで、見える世界の幅がぐっと広がります。
次のキャリアプランを一緒に考えてもらう
「次に何をしたいか分からない」という漠然とした不安も、転職をためらう大きな理由の一つです。そんな時も、転職のプロであるキャリアアドバイザーが力になります。これまでの経験や興味、価値観などを丁寧にヒアリングし、一緒に将来のキャリアプランを考えてくれます。
自分では思いつかなかったような職種や業界を提案してくれたり、長期的な視点でキャリアを築いていくためのアドバイスをくれたりします。一人で悩むよりも、専門家と対話することで、自分の進むべき道が明確になっていくでしょう。
休めない悩みは専門家への相談で解決しよう
休めない職場環境に悩み、転職を考えても、一人で活動するのは不安で心細いものです。そんな時は、転職の専門家である転職エージェントに頼るのが、悩みを解決する一番の近道です。専門家に相談するメリットは、以下の通りです。
- 今の職場環境が異常か客観的に判断できる
- 非公開求人から優良企業を紹介してもらえる
- 面接対策や退職交渉のサポートを受けられる
各項目について、詳しく見ていきましょう。
今の職場環境が異常か客観的に判断できる
長く同じ環境にいると、「このくらい普通なのかな?」と感覚が麻痺してしまうことがあります。転職エージェントに相談すれば、今の職場環境が客観的に見てどうなのかを、プロの視点から判断してもらえます。
多くの労働者や企業を見ているエージェントだからこそ、その会社の問題点を的確に指摘してくれます。「辛いと感じるのは当たり前ですよ」と言ってもらえるだけで、心が軽くなり、次のステップに進む勇気が湧いてくるはずです。
非公開求人から優良企業を紹介してもらえる
転職エージェントは、Webサイトなどには掲載されていない「非公開求人」を多数保有しています。これらの中には、労働環境が整備された優良企業の求人や、これから成長が見込める企業の求人などが含まれています。
自分の希望やスキルを伝えることで、膨大な求人の中から最適な会社をピックアップして紹介してくれます。自分一人で探すよりも、効率的に、かつ質の高い求人に出会える確率が格段に高まります。
面接対策や退職交渉のサポートを受けられる
転職活動で不安なのが、履歴書や職務経歴書の作成、そして面接です。転職エージェントは、応募する企業に合わせた書類の添削や、模擬面接といったサポートを無料で行ってくれます。企業の採用担当者に響くアピールの仕方を教えてくれるので、選考の通過率アップが期待できます。
また、内定が出た後の退職交渉がスムーズに進むようなアドバイスもしてくれます。入社までの一連の流れをトータルでサポートしてくれるので、安心して転職活動に臨むことができます。
悩んだらZキャリアのエージェントに相談してみよう
もし、今の「休めない」状況に少しでも悩みや不安を感じているなら、一度私たちZキャリアのエージェントに相談してみませんか。Zキャリアは、若年層のノンデスクワーカーの転職支援に特化しており、皆さんの気持ちに寄り添ったサポートを何よりも大切にしています。
相談したからといって、必ず転職する必要はありません。まずは今の悩みを話してみるだけでも、気持ちの整理がついて、次の一歩が見えてくるはずです。あなたの心と体が壊れてしまう前に、勇気を出して、新しい未来への扉をノックしてみてください。私たちが全力でサポートします。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)



