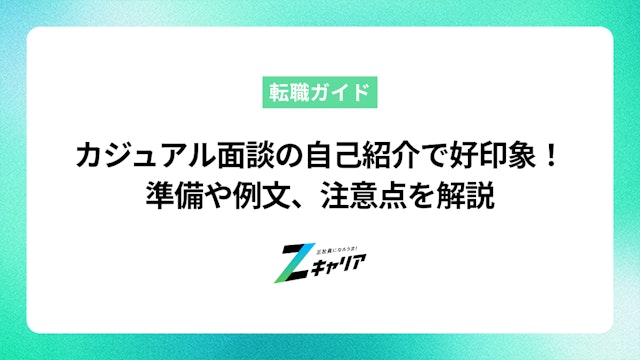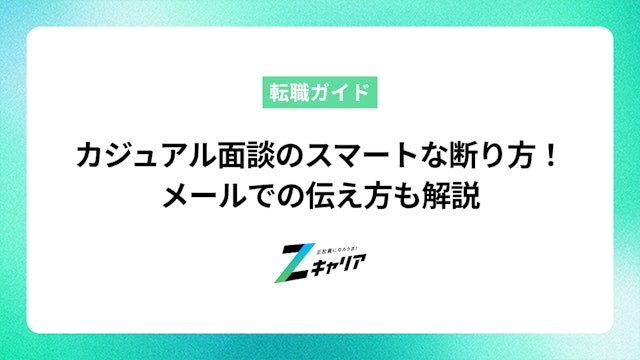「御社」「貴社」の使い分け

「御社(おんしゃ)」は話し言葉で面接や電話、商談など、口頭でコミュニケーションをとる際に使用する
「御社(おんしゃ)」は、相手の会社への敬意を示す敬語表現で、主に話し言葉として使用されます。具体的には、面接や電話、会社説明会、OB・OG訪問、商談といった、対面または口頭でコミュニケーションをとる場面で使います。「御」という漢字には、相手への尊敬や敬意を表す意味が込められています。面接官と話す際には「御社の〇〇という企業理念に共感し、志望いたしました」のように、自然に使えるように準備しておきましょう。
発音する際に、同音異義語である「恩赦」や「音写」と区別しやすく、聞き間違いを防ぐというメリットもあります。ビジネスシーンでの円滑なコミュニケーションの第一歩として、まずはこの「御社」を正しく使えるようにすることが重要です。
「貴社(きしゃ)」は書き言葉で履歴書やメール、手紙など、文章で表現する際に使用する
一方、「貴社(きしゃ)」は、書き言葉で相手の会社への敬意を表す際に用いる表現です。履歴書や職務経歴書、エントリーシート、お礼状、メールなど、文章を作成する際には「貴社」を使いましょう。「貴」という漢字も「御」と同様に、相手を敬い、高める意味を持っています。
なぜ話し言葉で「きしゃ」を使わないかというと、「記者」「汽車」「帰社」など多くの同音異義語があり、聞き間違いや混乱を招く可能性があるためです。文章であれば前後の文脈から意味を正確に判断できるため、書き言葉では「貴社」が適切とされています。「貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます」といった形で、ビジネス文書の定型句としても頻繁に使われるため、覚えておきましょう。
「御社」「貴社」はどっちでもいいというのは本当?
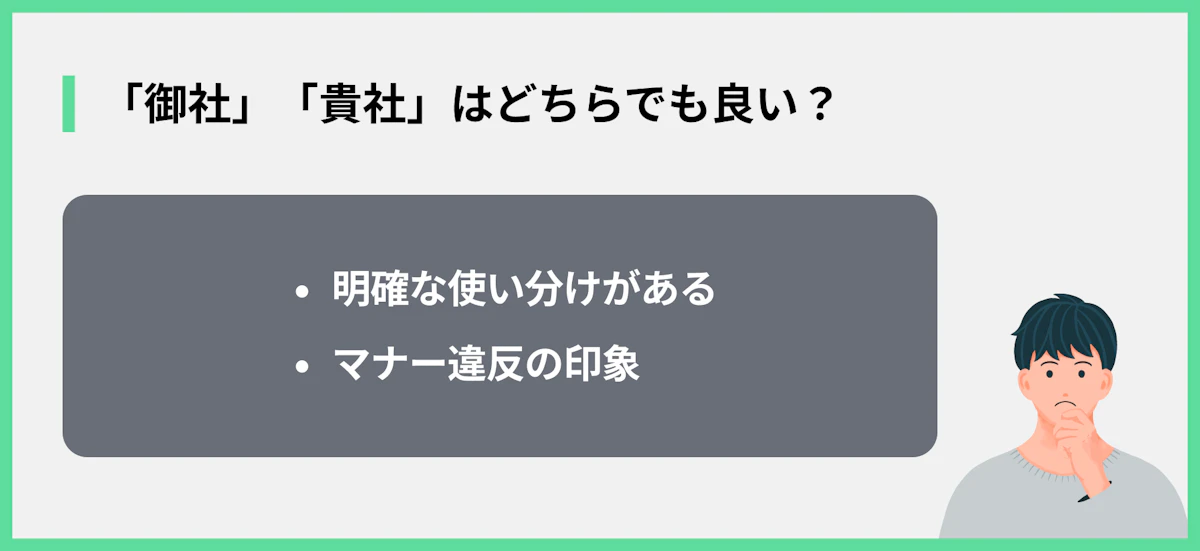
結論:「ビジネスシーンでは明確な使い分けがある」
「御社」と「貴社」はどちらを使っても良いという考えは誤りです。結論として、ビジネスシーンでは明確な使い分けが存在します。前述の通り、「御社」は話し言葉、「貴社」は書き言葉として使い分けるのが、社会人としての基本的なマナーです。このルールを知らない、または軽視していると、ビジネスマナーを理解していないと判断されかねません。
特に、企業の採用担当者や取引先の相手は、日々多くの人と接しているため、こうした言葉遣いに敏感です。使い分けができることは、相手への配慮と敬意を示すことにつながり、あなたの社会人としての信頼性を高める要素となります。就職・転職活動においては、第一印象を左右する重要なポイントであると認識しておきましょう。
使い分けを誤ると基本的なビジネスマナーがなっていないという印象を与えてしまう
もし「御社」と「貴社」の使い分けを誤ってしまうと、相手に「基本的なビジネスマナーが身についていない」というマイナスの印象を与えてしまう可能性があります。例えば、面接の場で「貴社では…」と発言したり、履歴書に「御社を志望します」と記載したりすると、採用担当者は「社会人としての常識を知らないのかもしれない」「入社後の教育が大変そうだ」と感じるかもしれません。
特に、礼儀やマナーを重んじる業界や企業では、こうした細かな点も評価の対象となることがあります。言葉遣い一つで、あなたの能力や熱意が正しく伝わらなくなるのは非常にもったいないことです。正しい知識を身につけ、自信を持って使い分けることで、相手に安心感と信頼感を与えましょう。
「御社」「貴社」の使い方を間違えた場合の対処法

落ち着いて誠実に対応することが大切
「御社」と「貴社」の使い分けを間違えてしまった場合、最も大切なのは落ち着いて誠実に対応することです。誰にでも間違いはあります。面接官も、一度の間違いであなたの人格や能力のすべてを判断するわけではありません。
むしろ、ミスをしてしまった後にどのように振る舞うかを見て、あなたの対応能力や誠実さを評価しています。パニックになって黙り込んだり、間違いに気づかないふりをしたりするのは避けましょう。間違いを素直に認め、真摯に謝罪する姿勢を見せることで、かえって好印象を与えることもあります。ミスは誰にでもあるということを念頭に置き、冷静さを保って次の行動に移ることが重要です。
面接など会話中に間違えた場合その場で気づいたら、すぐに訂正して謝罪するのがベスト
面接や電話など、会話の途中で「御社」と「貴社」の使い分けを間違えたことに気づいたら、その場ですぐに訂正し、簡潔に謝罪するのが最善の対応です。例えば、「先ほど貴社と申し上げましたが、正しくは御社です。大変失礼いたしました」のように、はっきりと訂正の意思を伝えましょう。長々と謝罪する必要はありません。すぐに会話の本筋に戻ることで、スムーズなコミュニケーション能力があることをアピールできます。
間違いを放置したり、ごまかしたりするよりも、その場で誠実に対応する方が、正直で責任感のある人物であるという印象を与えられます。間違いを恐れすぎず、もしもの時は冷静に訂正することを心がけてください。
メールや書類など文章で間違えた場合【ケース1】選考の初期段階・間違いに後から気づいた場合
エントリーシートや履歴書など、選考の初期段階で提出した書類で「御社」と「貴社」の使い分けを間違えてしまったことに後から気づいた場合、基本的には何もしなくても問題ありません。選考の初期段階では、採用担当者は非常に多くの応募書類に目を通しているため、敬称の間違い一つひとつを問題視することは稀です。
間違いを訂正するためだけに連絡をすると、かえって相手の手間を増やし、「細かいことを気にしすぎる」「優先順位の判断ができない」といったネガティブな印象を与えてしまう可能性もあります。それよりも、次の選考(面接など)に進んだ際に、口頭での言葉遣いを徹底する方が重要です。
メールや書類など文章で間違えた場合【ケース2】どうしても訂正したい・最終面接のお礼メールなど重要な場面の場合
最終面接のお礼メールや内定承諾書など、選考の重要な局面で「御社」と「貴社」を間違えてしまった場合、どうしても気になるのであれば、訂正の連絡を入れることも選択肢の一つです。その際は、再送するメールの件名と本文を以下のようにしましょう。
- 件名
【再送】〇〇大学の〇〇です(〇月〇日の面接のお礼)
- 本文
先ほどお送りしたメールにて、敬称の誤りがございました。正しくは『貴社』とすべきところを『御社』と記載しておりました。大変失礼いたしました。改めて、面接の機会をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。
以上のような形で、簡潔に謝罪と訂正を行いましょう。ただし、これも必須ではありません。基本的には、一度のミスが致命的になることはないと考えて良いでしょう。
「御社」と「貴社」の使い分けは大切なビジネスマナーですが、一度の間違いが合否を決定づける確率は非常に低い
「御社」と「貴社」の使い分けは、社会人としての基本的なマナーであり、正しく使えるに越したことはありません。しかし、万が一間違えてしまったからといって、それだけで不採用になることは稀です。言葉遣いのミスを取り返すことは可能ですが、それ以上にあなたの熱意やポテンシャル、人間性が評価されていることを忘れないでください。
一つのミスに固執せず、自己PRや志望動機など、より重要な部分で自分をアピールすることに集中しましょう。大切なのは、ミスから学び、次に活かそうとする前向きな姿勢です。
「弊社」「当社」「自社」の使い分け
「弊社(へいしゃ)」は自分の会社を表す謙譲語で、会話でも文書でも使える
「弊社(へいしゃ)」は、自分が所属する会社をへりくだって表現する謙譲語です。社外の人、つまり顧客や取引先に対して、自分の会社を指すときに使用します。「弊社」は丁寧な印象を与えるため、会話でも文書でも使うことができ、ビジネスシーンで最も一般的に使われる表現です。
例えば、商談の場では「弊社のサービスをご利用いただき、ありがとうございます」、メールでは「弊社の製品に関する資料をお送りします」のように使います。
相手への敬意を示す場面では、基本的に「弊社」を使うと覚えておけば間違いありません。企業とのやり取りではマナーが一層重視されるため、正しい言葉遣いが不可欠です。
「当社(とうしゃ)」は弊社よりも丁寧さが少し下がる
「当社(とうしゃ)」も自分の会社を指す言葉ですが、「弊社」と比較すると丁寧さの度合いは少し下がります。「弊社」が相手を立てる謙譲語であるのに対し、「当社」は自分の会社を単に指し示す丁重語とされています。
そのため、社外の相手に使う場合でも、自社の事業内容や方針を客観的かつ毅然と説明するプレスリリースやプレゼンテーション、あるいは自社が相手と同等以上の立場にある場合などに使われることがあります。
また、社内の会議や朝礼など、社員同士で話す際に使われることも多いです。「当社は今年度、〇〇を目標に掲げています」のように、社内向けのコミュニケーションで使うのが一般的だと覚えておくと良いでしょう。
「自社(じしゃ)」は社外の人には使わず、自分の会社の中で使う
「自社(じしゃ)」は、文字通り「自分の会社」という意味で、社内の人間同士で話す際に使う言葉です。「他社」や「競合他社」との比較で使われることが多く、客観的な表現として用いられます。
例えば、「自社の強みは〇〇であり、他社との差別化を図る必要がある」といった文脈で使用します。この言葉には「弊社」や「当社」のような丁寧なニュアンスは含まれていないため、顧客や取引先など社外の人に対して使うのは失礼にあたります。
「自社」はあくまで社内用語であると明確に認識し、社外の人とのコミュニケーションでは「弊社」を使うように徹底しましょう。この使い分けを誤ると、相手に横柄な印象を与えてしまう可能性があるので注意が必要です。
「御中」と「様」の使い分け
「御中」と「様」の基本的な違い
「御中(おんちゅう)」と「様(さま)」は、どちらも宛名に用いる敬称ですが、対象が異なります。「御中」は会社や部署、課といった「組織・団体」に対して使う敬称です。一方、「様」は特定の「個人」に対して使います。この違いが最も基本的なルールです。
例えば、企業の「人事部」という部署宛てに書類を送る場合は「〇〇株式会社 人事部 御中」となり、人事部の「山田太郎さん」という個人宛てに送る場合は「〇〇株式会社 人事部 山田太郎 様」となります。組織か個人か、どちらに宛てているのかを明確に意識することで、間違うことはありません。この二つは同時に使うことができないため、宛先の最終的な対象が何かを考えて使い分けることが重要です。
具体的な使い分けと記入例
会社や部署など、組織に送る場合 → 「御中」
採用担当者の個人名がわからない場合や、部署全体に書類を送付する際には「人事部 御中」のように、組織名の後ろに「御中」を付けます。「御中」は「その中のどなたかへ」という意味を持つ敬称です。ビジネス文書の基本として、個人宛てには「様」、組織宛てには「御中」と、正確に使い分けることを徹底しましょう。
特定の個人に送る場合 → 「様」
採用担当者の氏名が分かっている場合は、必ず個人名に「様」を付けて送付します。会社名、部署名、役職、そして氏名の順に記載し、最後に「様」を付けます。例えば、「〇〇株式会社 人事部 部長 山田太郎 様」のようになります。
個人名が分かっているにもかかわらず「人事部 御中」としてしまうと、採用担当者に「自分の名前を確認してくれていないのか」という印象を与えかねません。相手への配慮を示すためにも、担当者名は正確に記載することが大切です。もし役職名が分かっている場合は、氏名の前に記載しますが、役職名自体が敬称にあたるため「山田太郎 部長様」のように役職に「様」を付けるのは間違いです。
担当者の名前は分からないが、個人宛に送りたい場合 → 「ご担当者様」
書類の送付先が部署までしかわからず、担当者の個人名が不明な場合もあるでしょう。その際、部署宛ての「御中」でも問題ありませんが、「採用に関わる方に読んでほしい」という意図を明確にしたい場合は、「採用ご担当者様」という宛名を使うのが一般的です。
これは、「(部署の中にいる)採用担当のどなたか」という個人を指すため、「御中」ではなく「様」を使います。「人事部 御中」とするよりも、開封してくれる可能性が高まるかもしれません。ただし、「採用ご担当者様」のように「御」を付けるのは過剰な敬語となり不自然なため、「ご担当者様」と表記するのが適切です。状況に応じて「御中」と「ご担当者様」を使い分けましょう。
よくある間違いと注意点
「御中」と「様」の併用はNG!
宛名の敬称で最もよくある間違いの一つが、「御中」と「様」の併用です。例えば、「〇〇株式会社 人事部 御中 山田太郎 様」のような書き方は完全に誤りです。前述の通り、「御中」は組織に、「様」は個人に付ける敬称です。宛名の最終的な対象が個人であれば「様」を、組織であれば「御中」を使います。
個人名が記載されている時点で、宛先は個人に特定されるため、「御中」は不要になります。もし併用してしまうと、ビジネスマナーを全く理解していないと判断されてしまうでしょう。どちらか一方のみを使う、という基本ルールを徹底してください。これは封筒の宛名書きだけでなく、メールの宛先でも同様です。
役職名に「様」を付ける位置
役職名と個人名を併記する場合、「様」を付ける位置に注意が必要です。正しい書き方は「代表取締役 〇〇 様」や「人事部長 〇〇 様」のように、氏名の後に「様」を付けます。「〇〇 代表取締役様」や「〇〇 人事部長様」のように、役職名に「様」を付けてしまうのは間違いです。役職名そのものが敬称の一種であるため、「様」を付けると敬称が重複してしまいます。
また、会社名、部署名、役職名、氏名の順で書くのが一般的です。小さなことですが、正しい順序と敬称の使い方をマスターすることで、細やかな配慮ができる人材であるという印象を与えることができます。
返信用封筒の「行」「宛」の書き換え
企業から送られてくる返信用封筒には、自社の宛名に「〇〇株式会社 人事部 行」や「〇〇 宛」と書かれていることがほとんどです。「行」や「宛」は、こちら側(差出人)への敬意を表すものではないため、返信する際には二重線で消し、敬称に書き換えるのがマナーです。 宛名が組織名(部署名など)で終わっている場合は、「行」を二重線で消し、その隣か下に「御中」と書きます。宛名が個人名の場合は、「行」または「宛」を二重線で消し、隣か下に「様」と書き加えます。
この一手間をかけることで、相手への敬意とビジネスマナーの知識を示すことができます。修正テープや修正液で消すのはマナー違反なので、必ず二重線を使いましょう。
その他ビジネスの言葉遣いで注意すべきもの〜敬意の方向を間違えやすい言葉〜
NG表現「了解しました」→適切な表現「承知いたしました / かしこまりました」
「了解しました」という言葉は、同僚や目下の人に対して使うのが一般的であり、目上の人や顧客に使うのは失礼にあたるとされています。「了解」には相手の事情を理解し、許可するというニュアンスが含まれるため、目上の方に使うと見下しているような印象を与えかねません。
目上の人に対しては、相手の依頼や指示を受け入れたことを敬意を込めて示す「承知いたしました」や「かしこまりました」を使いましょう。「承知いたしました」は指示や依頼を理解し、引き受けるという意味で、幅広く使えます。「かしこまりました」はさらに敬意が高く、特に顧客や役員など、非常に敬うべき相手に対して使うとより丁寧な印象になります。
NG表現「ご苦労様です」→適切な表現「お疲れ様です」
「ご苦労様です」は、本来、目上の人が目下の人をねぎらう際に使う言葉です。そのため、部下や後輩が上司や先輩に対して使うのはマナー違反とされています。社内の上司や先輩、あるいは社外の取引先に対しては、立場に関係なく使える「お疲れ様です」を使いましょう。
「お疲れ様です」は、相手の労働や尽力に感謝とねぎらいの気持ちを示す便利な言葉で、社内ですれ違った際の挨拶や、電話の第一声、メールの書き出しなど、様々なビジネスシーンで活用できます。社外の人から自社の社員の労をねぎらってもらった際に、「ご苦労様です」と言われた場合は、「ありがとうございます」や「恐れ入ります」と返しましょう。
NG表現「参考になりました」→適切な表現「大変勉強になりました」
上司や取引先からアドバイスをもらった際に、「参考になりました」と返答するのは避けた方が無難です。「参考にする」という言葉には、「自分の考えを決める際の足しにする」という意味合いがあり、相手によっては「上から目線で評価されている」と感じてしまう可能性があるからです。感謝と敬意をより明確に伝えるためには、「大変勉強になりました」という表現を使いましょう。
この言葉には、「新しい知識を得て、自分の身になった」という謙虚な気持ちが込められており、相手を立てることができます。さらに、「〇〇という点が特に勉強になりました。今後の業務に活かしてまいります」のように、具体的に何がどう勉強になったのかを付け加えると、より感謝の気持ちが伝わり好印象です。
NG表現「なるほどですね」→適切な表現「おっしゃる通りですね / さようでございますか」
相槌として便利な「なるほどですね」は、一見丁寧な言葉に聞こえますが、実は敬語として正しくありません。「なるほど」は相手を評価するニュアンスを含むため、目上の人に対して使うのは失礼にあたります。それに丁寧語の「です」と助詞の「ね」を付けた「なるほどですね」は、俗にいう「若者言葉」であり、ビジネスシーンには不適切です。
相手の話に同意や納得を示したい場合は、「おっしゃる通りですね」や「さようでございますか」といった正しい敬語を使いましょう。「左様でございますか」と驚きや感心のニュアンスを加えたり、「はい、よくわかりました」と理解したことを伝えたりするのも良いでしょう。安易に相槌を打つのではなく、相手への敬意を示す言葉を選ぶことが大切です。
NG表現「感心しました」→適切な表現「大変勉強になりました / 素晴らしいですね」
「感心しました」という言葉も、目上の人に対して使うべきではありません。「感心」は、目上の人が目下の人やその行いに対して、優れていると評価する際に使う言葉だからです。そのため、上司や顧客の仕事ぶりや発言に対して「感心しました」と言うと、相手を見下している、評価していると捉えられ、大変失礼にあたります。このような場合は、「参考になりました」と同様に「大変勉強になりました」という表現が適切です。
また、相手の能力や成果を素直に称賛したいのであれば「素晴らしいですね」や「さすがでございます」といった言葉を選ぶと、敬意が伝わりやすくなります。相手を敬う気持ちを、正しい言葉で表現することが重要です。
NG表現「すみません」→適切な表現「申し訳ございません / 恐れ入ります」
「すみません」は非常に便利な言葉で、謝罪、感謝、依頼など様々な場面で使われますが、ビジネスシーン、特に目上の人に対しては多用を避けるべきです。軽い謝罪のニュアンスが強く、フォーマルな場面では誠意が伝わりにくいことがあります。謝罪する場合は、「申し訳ございません」を使いましょう。これが最も丁寧な謝罪の表現です。
感謝の気持ちを伝えたい場合は「ありがとうございます」、相手に何かを依頼したり、呼びかけたりするクッション言葉としては「恐れ入ります」が適切です。「恐れ入りますが、少々お時間をいただけますでしょうか」のように使います。場面に応じてこれらの言葉を使い分けることで、より丁寧でプロフェッショナルな印象を与えることができます。
NG表現「(相手に)~をご持参ください」→適切な表現「~をお持ちください / ~をご持参願います」
相手に何かを持ってきてもらうよう依頼する際に、「ご持参ください」という表現を使うのは間違いです。「持参」は「持って参る」という謙譲語であり、自分や身内の行為に使う言葉です。相手の行為に対して使うのは不適切であり、失礼にあたります。相手に持ってきてもらうようお願いする場合は、尊敬語である「お持ちください」を使うのが正しい表現です。より丁寧な表現を使いたい場合は、「~をお持ちいただけますでしょうか」といった形にすると良いでしょう。
例えば、面接の案内メールで「履歴書をご持参ください」と書かれていたら、その企業の言葉遣いに対する意識が低い可能性がありますが、自分が使う際は正しい敬語を心がけましょう。
NG表現「役不足」→適切な表現「力不足」
「役不足」は、本来「その人の力量に対して役目が軽すぎること」を意味する言葉です。自分の能力が足りないことを謙遜して伝えたい場面で使うと、逆の意味に捉えられ、傲慢な印象を与えかねません。この場合は「力不足」や「未熟者ですが」といった表現が適切です。
こうした言葉の誤用は、基本的な知識が不足していると判断される一因にもなり得ます。ビジネスシーンでは、言葉の本来の意味を正しく理解し、TPOに合わせた表現を心がけることが、信頼関係を築く上で不可欠です。
その他ビジネスの言葉遣いで注意すべきもの〜二重敬語・過剰な敬語〜
NG表現「拝見させていただく」→適切な表現「拝見します」
「拝見させていただく」は、二重敬語の典型的な例です。「拝見する」は「見る」の謙譲語、「~させていただく」も相手の許可を得て何かをさせてもらう謙譲語です。謙譲語が二つ重なっているため、過剰で回りくどい印象を与えます。この場合はシンプルに「拝見します」と言うのが正しい表現です。
例えば、相手から受け取った資料に目を通す際は、「資料を拝見します」と伝えましょう。「拝読します」(書物などを敬意を払って読む)という言葉もありますが、一般的なビジネス文書であれば「拝見します」で十分です。敬語は丁寧であればあるほど良いというわけではなく、簡潔で分かりやすい表現を心がけることが大切です。
NG表現「おっしゃられる」→適切な表現「おっしゃる」
「おっしゃられる」もよくある二重敬語の一つです。「おっしゃる」は「言う」の尊敬語であり、それ自体で相手への敬意を十分に表しています。これに尊敬の助動詞「~られる」を付けてしまうと、敬語が重複してしまいます。正しい表現は「おっしゃる」です。
例えば、上司や顧客の発言を引用する際に、「〇〇様がおっしゃられる通り」ではなく、「〇〇様がおっしゃる通り」とするのが適切です。言葉遣いを丁寧にしようと意識するあまり、無意識に二重敬語を使ってしまうことがあります。特に会話の中では気づきにくい間違いなので、「おっしゃる」で十分敬意が示せることを覚えておきましょう。
NG表現「お越しになられる」→適切な表現「お越しになる / いらっしゃる」
「お越しになられる」も「おっしゃられる」と同様の二重敬語です。「お越しになる」が「来る」の尊敬語として正しい形です。これにさらに尊敬の助動詞「~られる」を付けてしまうと、過剰な敬語表現となります。この場合の正しい表現は「お越しになる」、または同じく「来る」の尊敬語である「いらっしゃる」です。
例えば、来客の予定を確認する際に、「何時ごろお越しになられますか?」と尋ねるのではなく、「何時ごろお越しになりますか?」や「何時ごろいらっしゃいますか?」と尋ねるのが適切です。シンプルで正しい敬語を使うことで、洗練された印象を与えることができます。
NG表現「~様でございますね」→適切な表現「~様でいらっしゃいますね」
「~様でございますね」という表現は、一見すると非常に丁寧に聞こえますが、実は文法的に少し不自然な敬語です。「ございます」は「ある」の丁寧語であり、人を対象にするのには適していません。人を主語にする場合は、尊敬語を使うのが適切です。この場合、存在を示す尊敬語である「いらっしゃる」を使い、「~様でいらっしゃいますね」とするのが正しい敬語表現です。
例えば、電話の相手を確認する際に「田中様でございますね」ではなく、「田中様でいらっしゃいますね」とすることで、相手への敬意をより正確に示すことができます。細かい違いですが、知っておくとコミュニケーションの質が向上します。
NG表現「お体をご自愛ください」→適切な表現「ご自愛ください」
メールや手紙の結びの言葉としてよく使われる「お体をご自愛ください」は、実は重複表現です。「自愛」という言葉自体に「自分の体を大切にする」という意味が含まれています。そのため、「お体をご自愛ください」とすると、「お体を自分の体を大切にしてください」という意味が重なってしまいます。
正しい表現は、シンプルに「ご自愛ください」です。季節の変わり目などに相手の健康を気遣う気持ちを伝えたい場合は、「時節柄、どうぞご自愛ください」や「くれぐれもご自愛ください」のように使うと、スマートで知的な印象を与えます。
その他ビジネスの言葉遣いで注意すべきもの〜させていただくの多用〜
NG表現「資料を送付させていただきます。」→適切な表現「資料を送付いたします。」
「~させていただきます」は、相手の許可を得て何かを行う際に使う謙譲語です。しかし、許可を得る必要がない場面で多用すると、回りくどく、主体性がない印象を与えてしまいます。資料を送るという行為は、通常、相手の許可を必要としません。そのため、「資料を送付させていただきます」ではなく、自分側の行為として丁重に伝える「資料を送付いたします」が適切です。
「いたします」は「する」の謙譲語・丁寧語であり、この場面で使うのにふさわしい表現です。何でも「~させていただきます」と表現するのではなく、その行為が相手の許可を必要とするか、相手に恩恵があるかを考えて使い分けることが重要です。
NG表現「本日はお休みをいただいております。」→適切な表現「本日は休んでおります。」
担当者が不在であることを伝える際に「本日はお休みをいただいております」という表現をよく耳にしますが、これも「~いただく」の誤用です。休みを取ることは会社の制度や許可に基づくものであり、電話をかけてきた社外の相手から許可を得て休んでいるわけではありません。この場合、事実を丁寧に伝える「(〇〇は)本日は休んでおります」で十分です。
もし、相手に迷惑をかけることへの配慮を示したいのであれば、「申し訳ございません。あいにく〇〇は本日、休暇を取得しております」のように、クッション言葉を添えるとより丁寧な印象になります。「~させていただく」と同様に、「~いただく」の乱用は避け、状況に応じた適切な表現を心がけましょう。
NG表現「ご説明させていただきます。」→適切な表現「ご説明いたします。」
プレゼンテーションや会議の冒頭で「ご説明させていただきます」と言うのも、よくある誤用の一つです。説明をすることは、多くの場合、相手の許可を必要とする行為ではありません。むしろ、説明する機会を与えられている状況です。したがって、ここでも謙譲語の「いたします」を使い、「ご説明いたします」とするのが簡潔で適切な表現です。
聞き手にとっても、シンプルで分かりやすい言葉の方が内容は頭に入りやすいものです。「~させていただきます」という言葉に頼りすぎず、自信を持って「~いたします」と言い切ることで、堂々としたプロフェッショナルな印象を与えることができます。
その他ビジネスの言葉遣いで注意すべきもの〜いわゆる「バイト敬語」「話し癖」〜
NG表現「~になります」→適切な表現「~でございます」
「こちら、〇〇になります」という表現は、飲食店や小売店などでよく使われるため「バイト敬語」の代表例として知られています。「~になる」は本来、何かが別の状態に変化する際に使う言葉です(例:信号が青になる)。単に物を提示したり、事実を述べたりする場面で使うのは不適切です。正しくは、丁寧な断定の助動詞である「~でございます」を使います。
例えば、資料を渡す際は「こちらの資料が、本日お配りするものでございます」のように表現します。電話で名乗る際も「わたくし、〇〇の佐藤になります」ではなく、「わたくし、〇〇の佐藤でございます」と言うのが正しいマナーです。
NG表現「~のほう」→適切な表現「(「ほう」を削除する)」
「資料のほう、お持ちしました」「お値段のほう、〇〇円です」のように、「~のほう」という言葉を多用する話し癖も、ビジネスシーンでは避けるべきです。この「ほう」は、本来、二つ以上のものを比較して一方を指し示す際に使う言葉です(例:コーヒーと紅茶、どちらにしますか?→コーヒーのほうをお願いします)。比較対象がないのに使うと、表現が曖昧になり、幼稚な印象を与えてしまいます。
多くの場合、単純に「ほう」を削除するだけで、すっきりと分かりやすい表現になります。「資料をお持ちしました」「お値段は〇〇円です」のように、余計な言葉を削ぎ落とし、的確に情報を伝えることを心がけましょう。
NG表現「よろしかったでしょうか?」→適切な表現「よろしいでしょうか?」
注文内容の確認などで使われる「よろしかったでしょうか?」は、過去形にする必要がない場面で過去形を使う、いわゆる「バイト敬語」の一つです。相手の意向を確認するのは、今現在のことであり、過去のことではありません。したがって、正しくは現在形の「よろしいでしょうか?」を使います。
例えば、会議の日程を調整する際に「この日程でよろしかったでしょうか?」と聞くのは間違いで、「この日程でよろしいでしょうか?」と尋ねるのが適切です。過去形を使うことで丁寧さが増すわけではありません。文法的に正しい言葉遣いをすることが、相手への敬意の基本です。
NG表現「~円からお預かりします」→適切な表現「~円、お預かりします」
会計の際に「1万円からお預かりします」という言葉をよく聞きますが、これも厳密には正しくありません。助詞の「から」は、起点を示す言葉であり、受け取った金額そのものを指すのには不適切です。「1万円という金額から(何かを引いて)お預かりします」というような、おかしな意味になってしまいます。
この場合は、助詞の「から」を抜いて、シンプルに「〇〇円、お預かりします」と言うのが正しい表現です。あるいは「1万円、頂戴いたします」という言い方もあります。細かい点ですが、こうした日常的な言葉遣いにも気を配ることで、丁寧で正確なコミュニケーション能力をアピールすることができます。
Zキャリアであれば面接対策を無料でできる
書類や面接対策をして転職してみよう
これまで解説してきたビジネスマナーは、転職活動における重要な対策の一つです。しかし、驚くべきことに、転職活動において特に対策を行っていない人は66.1%と過半数に達しています。これは、しっかりとした準備をすることで、他の候補者と大きく差をつけるチャンスがあることを意味します。
Zキャリアのような転職エージェントを活用すれば、専門のキャリアアドバイザーが無料で面接練習や書類添削を行ってくれます。正しい言葉遣いはもちろん、あなたの強みを最大限にアピールする方法を一緒に考え、自信を持って選考に臨むためのサポートを受けることができます。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)