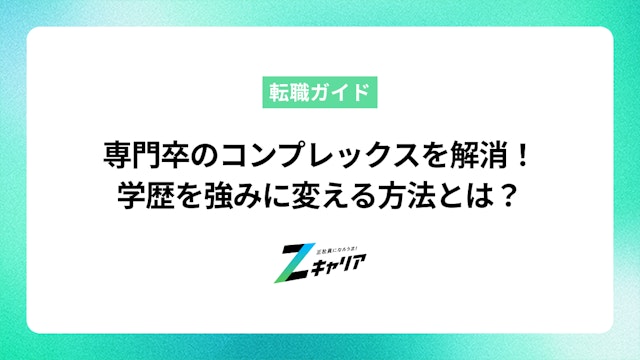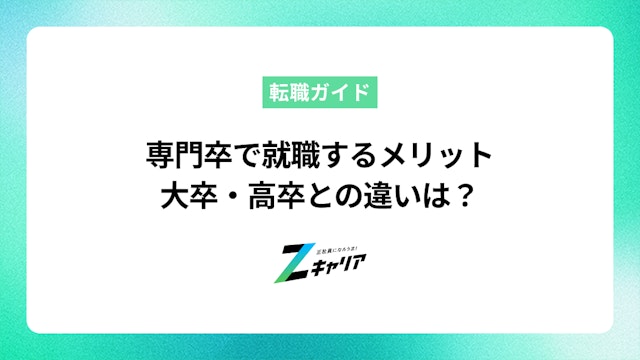- 専門卒と高卒の扱いの違い
- 専門卒で就職・転職するメリット
- 専門卒が注意すべきデメリット
- 専門性を活かして転職を成功させる方法
専門卒は高卒と同じ扱いをされるの?
専門卒が高卒と同じ扱いをされるのか、気になるポイントは以下の通りです。
- 法律上の学歴は「専門士」で高卒ではない
- 給与や待遇は企業の規定によって変わる
- 求人によっては高卒と同じ区分の場合もある
各項目について、詳しく解説していきます。
法律上の学歴は「専門士」で高卒ではない
まず知っておきたいのは、「専門士」という正式な称号が法律で認められていることです。これは、修業年限が2年以上などの要件を満たした専門学校の卒業者に与えられるもので、高校卒業とは明確に区別されています。そのため、履歴書の学歴欄には「高等学校 卒業」とは別に、「〇〇専門学校 卒業」と堂々と記載することができます。法律上、専門卒は高卒と同じ扱いではない、ということを覚えておきましょう。
給与や待遇は企業の規定によって変わる
給与や待遇については、企業の給与テーブルで決まることがほとんどです。多くの企業では、「高卒」「専門・短大卒」「大卒」のように、学歴別に給与のスタートラインを設定しています。この場合、専門卒は高卒よりも高い給与が設定されていることが一般的です。ですが、企業によっては学歴の区分が少なく、「高卒以上」として専門卒も高卒と同じ給与テーブルに含まれるケースもあります。これが、「専門卒は高卒扱い」と言われることがある理由の一つです。
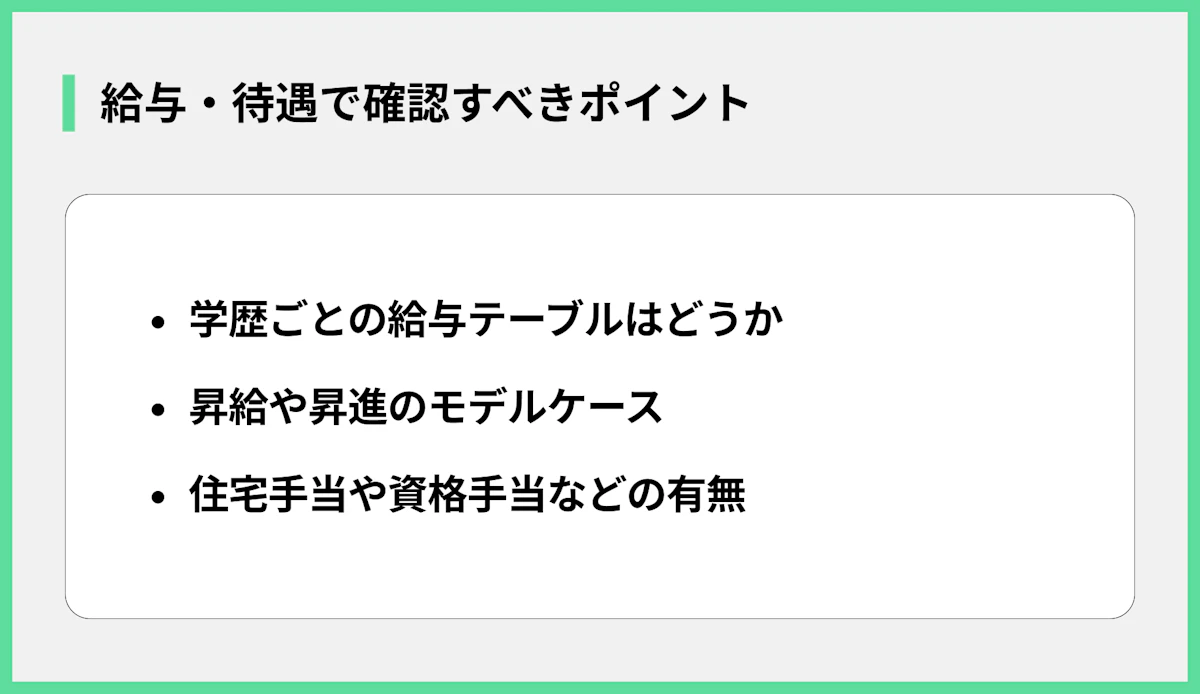
求人によっては高卒と同じ区分の場合もある
求人票の応募資格欄に、応募資格が「高卒以上」と書かれているのを見たことがあるかもしれません。この場合、専門学校卒業者ももちろん応募できますが、選考のスタートラインが高卒者と同じになることを意味します。学歴でフィルターをかけられることはありませんが、同じ土俵で選考が進むため、「高卒と同じ扱いだ」と感じてしまうことがあります。逆に「専門卒以上」を条件とする求人もあり、その場合は専門スキルが有利に働くこともあります。
専門卒だからこそ得られる就職のメリット
専門卒と高卒の扱いの違いが分かったところで、専門卒ならではのメリットを見ていきましょう。具体的なメリットは以下の通りです。
- 専門スキルが即戦力として評価される
- 実務に近い学習経験をアピールできる
- 資格取得でキャリアの選択肢が広がる
各項目について、詳しく解説していきます。
専門スキルが即戦力として評価される
専門卒の最大の強みは、実践的なスキルが身についていることです。特定の分野に特化して2年またはそれ以上学習しているため、企業にとっては、基礎から教える手間が省け、すぐに現場で活躍してくれる「即戦力」として非常に魅力的です。例えば、IT、デザイン、調理、美容、医療事務といった分野では、専門知識が直接仕事に結びつきます。面接でも「〇〇ができます」と具体的にアピールできるため、採用担当者にもスキルが伝わりやすいでしょう。
実務に近い学習経験をアピールできる
専門学校のカリキュラムには、実習や制作の経験が豊富に盛り込まれています。机の上での勉強だけでなく、実際に手を動かして学んだ経験は、就職活動において強力な武器になります。例えば、IT系ならプログラミング演習、デザイン系なら作品制作、調理系なら調理実習など、具体的なエピソードを交えて話すことで、自分のスキルレベルを効果的に証明できます。ポートフォリオ(作品集)を用意しておくと、さらに説得力が増すでしょう。
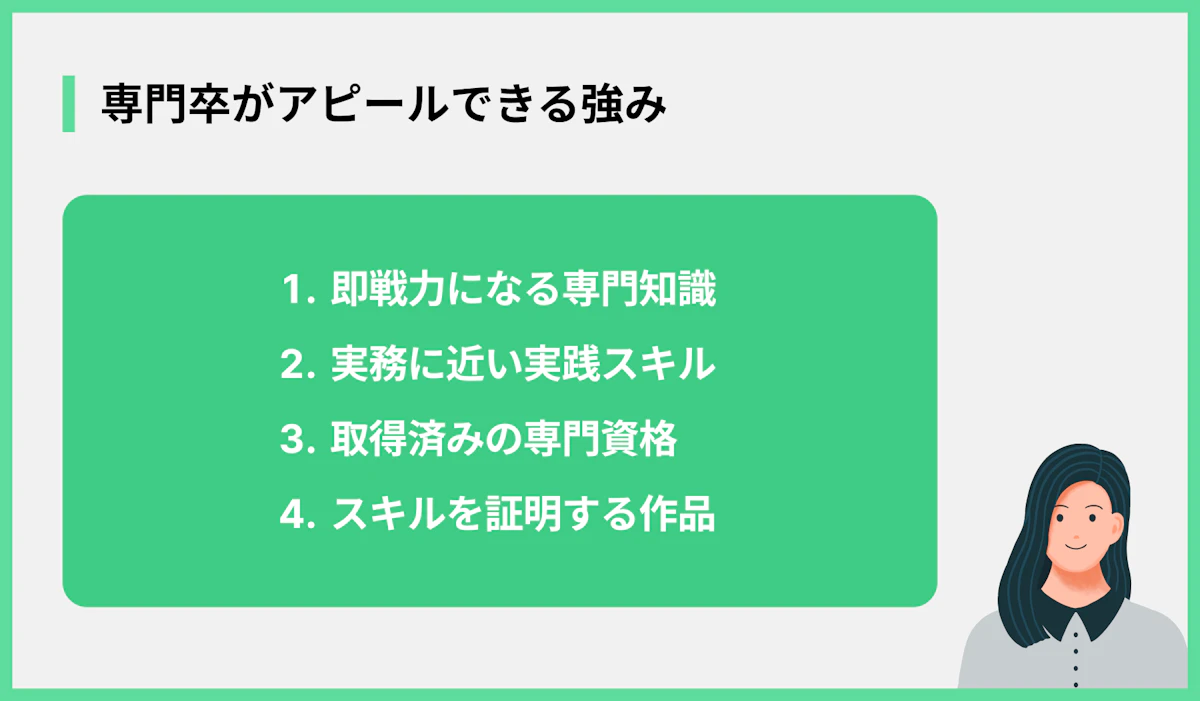
資格取得でキャリアの選択肢が広がる
専門学校を卒業することで、特定の職種に就くために必須の資格の受験資格を得られたり、資格そのものを取得できたりします。これは、キャリアを考える上で非常に大きなメリットです。例えば、調理師、美容師、理学療法士、保育士といった仕事は、資格がなければ就くことができません。専門学校で学ぶことで、こうした専門職への道が開かれます。目標とする仕事が明確な場合、専門学校で学ぶことは夢への最短ルートと言えるでしょう。
知っておきたい専門卒の就職でのデメリット
メリットがある一方で、知っておきたいデメリットもあります。以下の点を理解しておくことで、事前に対策を立てることができます。
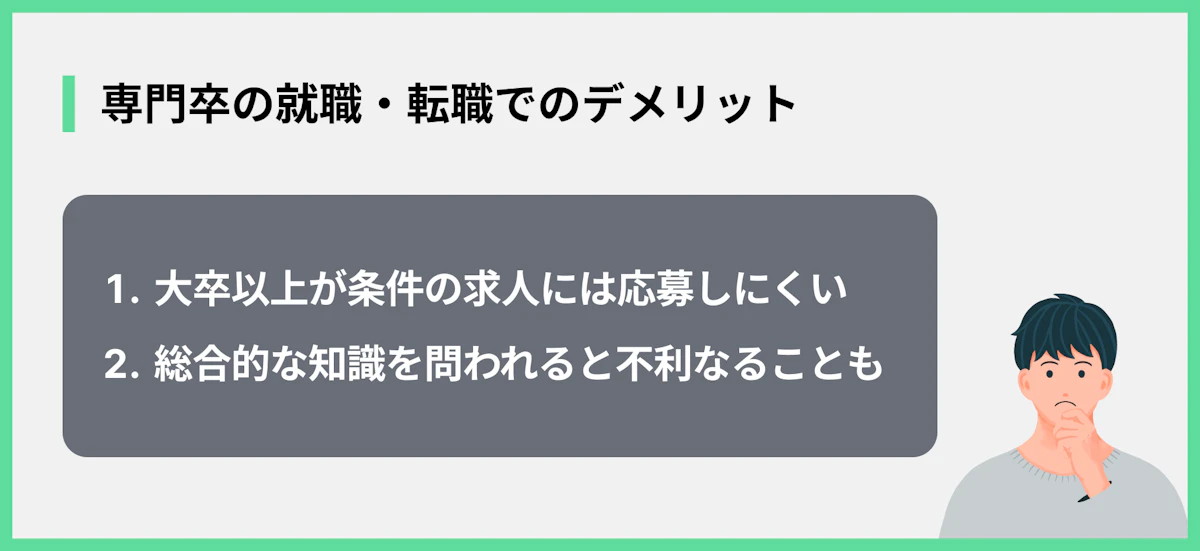
各項目について、詳しく解説していきます。
大卒以上が条件の求人には応募しにくい
残念ながら、一部の企業、特に大手企業の総合職などでは、大卒向けの求人には応募できないことがあります。応募資格を「大卒以上」と定めている求人には、挑戦すること自体が難しいのが現実です。そのため、大卒者と比較すると、応募できる求人の選択肢が狭まってしまう可能性があります。ただし、これはあくまで一部の求人の話です。世の中には「学歴不問」や「専門卒歓迎」の求人も数多く存在します。自分の専門性を求めている企業に目を向けることが大切です。
総合的な知識を問われると不利になることも
専門分野の知識では誰にも負けない自信があっても、専門分野以外の知識で差がつく場面があるかもしれません。大学では、専門分野以外にも幅広い一般教養を学びます。そのため、総合的な知識や思考力が求められる職種では、大卒者と比較されて不利に感じることがあるかもしれません。ですが、これは入社後の意欲や学習で十分にカバーできる部分です。自分の専門性を活かしつつ、新しい知識も積極的に吸収していく姿勢を見せることができれば、問題になることは少ないでしょう。
専門卒の強みを活かして転職を成功させる方法
最後に、専門卒の強みを最大限に活かして、就職・転職を成功させるための具体的な方法を紹介します。ポイントは以下の通りです。
- 身につけた専門性を明確に言語化する
- 職務経歴書で実績を具体的に示す
- 専門知識を活かせる業界や職種を選ぶ
各項目について、詳しく解説していきます。
身につけた専門性を明確に言語化する
まずは、自分が何を学んできたのか、そして「何ができるのか」を具体的にする作業から始めましょう。「〇〇を学びました」というだけでは、採用担当者にはスキルが伝わりません。「〇〇の知識を活かして、△△というツールを使えます」「〇〇の実習を通して、△△の作業を一人で完結できます」といったように、具体的な動詞を使って説明できるように準備することが重要です。自己分析をしっかり行い、自分のスキルを棚卸ししてみましょう。
職務経歴書で実績を具体的に示す
自分のスキルを言葉で説明できるようになったら、それを書類で証明する必要があります。特に、作品や成果物を提示するポートフォリオは、スキルの強力な証明になります。ITやデザイン系であれば制作したWebサイトやデザイン、それ以外の分野でも、実習で作成したものや、成果がわかるレポートなどをまとめておくと良いでしょう。職務経歴書や面接でそれらを見せることで、言葉だけでは伝わらない実力をアピールできます。
専門知識を活かせる業界や職種を選ぶ
自分の強みを最大限に発揮するためには、やはり学んだ分野と関連性の高い仕事を選ぶのが一番の近道です。自分の専門性が評価されれば、やりがいを感じながら働くことができますし、キャリアアップもしやすくなります。全く違う分野に挑戦することも可能ですが、まずは自分の専門性を軸に仕事を探してみることをお勧めします。企業研究をしっかり行い、自分のスキルが本当に活かせる環境かを見極めることが、入社後のミスマッチを防ぐカギとなります。専門卒は、決して高卒扱いではありません。専門学校で身につけた知識やスキルは、社会で必ず役立つ強力な武器になります。大切なのは、自分の強みを正しく理解し、それを求めている企業に対して効果的にアピールすることです。もし、自分のキャリアプランに悩んだり、就職・転職活動の進め方に不安を感じたりしたら、一人で抱え込まないでください。Zキャリアのキャリアアドバイザーは、いつでもあなたの味方です。あなたの専門性を最大限に活かせる職場探しを、私たちが全力でサポートします。
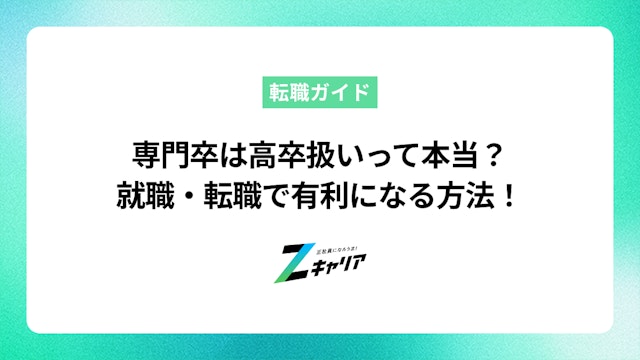
.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)