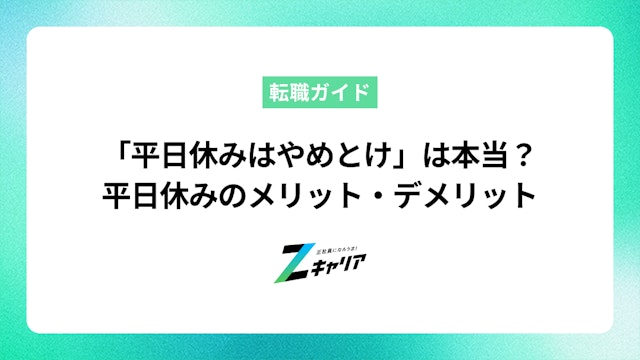- 会社が「原則出社」を求める本当の理由
- 上の世代が出社にこだわる背景
- フル出社のメリットとデメリット
- どうしても出社が無理な時の対処法
- リモートワーク転職を成功させるコツ
原則出社なのはなぜ?会社が出社を求める5つの理由
「リモートでも仕事はできるのに、どうして出社しないといけないの?」と疑問に思うかもしれません。会社が原則出社を求めるのには、いくつかの理由があります。具体的には以下の5つの理由について解説します。
- 社員の連携を強化しチームの一体感を高めるため
- 新人や若手社員への教育体制を整えるため
- 何気ない会話から新しいアイデアを生み出すため
- 勤怠管理や情報漏洩のリスク管理を徹底するため
- 公平性を保ち社員の不満をなくすため
各項目について、詳しく見ていきましょう。
社員の連携を強化しチームの一体感を高めるため
会社は、社員同士が顔を合わせることで、仕事の連携がスムーズになり、チームとしての一体感が生まれると考えています。
テキストメッセージやビデオ通話だけでは、相手の細かい表情や声のトーンが伝わりにくく、ちょっとした認識のズレが生まれることがあります。ですが、同じ空間にいれば、隣の席の先輩に「これってどう思いますか?」と気軽に聞けたり、チーム全体で雑談を交えながら和やかな雰囲気で会議ができたりします。
このような日々の小さなコミュニケーションの積み重ねが、いざという時のチームワークにつながり、仕事全体の効率を上げると期待されているのです。
新人や若手社員への教育体制を整えるため
特に社会人経験の浅い若手社員にとって、先輩の仕事を間近で見られることは、何よりの学びになります。
リモートワークだと、分からないことがあっても「こんなことで連絡していいのかな…」とためらってしまい、質問のタイミングを逃しがちです。ですが、オフィスにいれば、先輩が電話で取引先と話している様子や、パソコンで資料を作成する手順などを自然と目にすることができます。
また、困った時にすぐに隣の先輩に質問できる環境は、成長のスピードを大きく加速させます。会社としては、こういった環境を整えることで、将来を担う人材をしっかりと育てていきたいという思いがあるのです。
何気ない会話から新しいアイデアを生み出すため
会社は、予期せぬ雑談から生まれるひらめきを大切にしています。
休憩室でのコーヒーブレイク中の会話や、廊下ですれ違った時の短いやり取りなど、仕事とは直接関係のない何気ない雑談が、新しい商品やサービスのヒントになることは珍しくありません。リモートワークでは、目的のある会議や連絡が中心になるため、こういった偶発的なコミュニケーションは生まれにくいのが現実です。
様々な部署や立場の人たちが顔を合わせることで、思いがけない化学反応が起きる。会社は、オフィスをそうしたイノベーションが生まれる場所として期待しているのです。
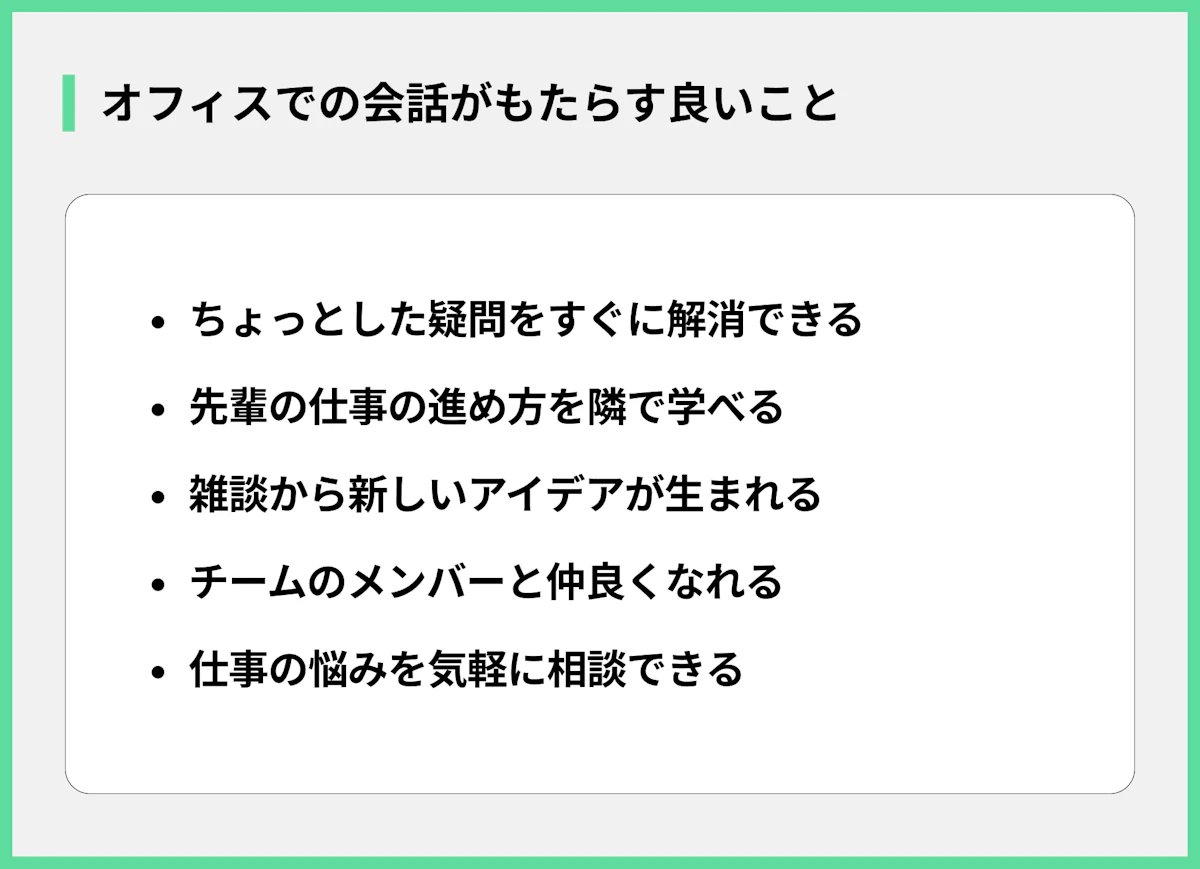
勤怠管理や情報漏洩のリスク管理を徹底するため
会社には、社員の働き方をしっかり管理する責任があります。出社していれば、誰がいつ来ていつ帰ったのか、きちんと休憩を取っているかなどを把握しやすくなります。これは、社員の健康を守り、長時間労働を防ぐためにも重要です。
また、会社のパソコンで扱う情報には、お客様の個人情報やまだ公開されていない新商品の情報など、外部に漏れてはいけないものがたくさん含まれています。オフィスという限られた空間で作業することで、こうした大切な情報が外部に流出するリスクを最小限に抑えたいという、セキュリティ上の理由も大きいのです。
公平性を保ち社員の不満をなくすため
職種によっては、どうしてもリモートワークが難しい仕事もあります。例えば、工場で製品を作る仕事や、店舗でお客様に対応する仕事などは、現場に行かなければ成り立ちません。
もし、一部の部署だけがリモートワークを許可されると、「どうしてあの部署だけ楽をしているんだ」といった不満が生まれ、社員の間に不公平感が広がってしまう可能性があります。
全ての社員を同じ条件にすることで、そうした不満の声をなくし、社内の和を保とうとするのも、会社が出社を原則とする理由の一つです。
なぜ上の世代は出社にこだわる傾向があるのか?
経営者や上司といった上の世代が出社にこだわる背景には、彼らが経験してきた時代背景や価値観が関係しています。具体的には以下の3つの背景について解説します。
- 対面でのコミュニケーションを重視する価値観がある
- 部下の働きぶりを直接見ないと管理しにくいと考える
- 自分が若手だった頃の常識が基準になっている
各項目について、詳しく見ていきましょう。
対面でのコミュニケーションを重視する価値観がある
上の世代の多くは、顔を合わせて話すことが最も重要だと考えて育ってきました。ビジネスチャットやWeb会議がなかった時代には、直接会って話をすることが、相手への誠意を示す方法であり、信頼関係を築くための第一歩でした。
熱意や人柄は、文章だけでは伝わりきらないと感じているため、大切な話ほど直接会って話したいと考える傾向があります。この価値観は、仕事だけでなく、部下との関係づくりにおいても同じです。画面越しではなく、同じ空間で時間を共有することで、本当の意味でのコミュニケーションが取れると信じているのです。
部下の働きぶりを直接見ないと管理しにくいと考える
管理職の立場からすると、部下が目の前にいないと不安になるという気持ちもあります。リモートワークでは、部下が本当に仕事をしているのか、何か困っていることはないか、進捗は順調か、といった状況を把握するのが難しくなります。
部下の様子を直接見ることで、「少し元気がないな」「仕事に集中できているな」といった変化に気づき、声をかけることができます。部下の成長をサポートし、チームとして成果を出す責任があるからこそ、全員の顔が見える環境で仕事をしたいと考えるのです。これは、部下を信頼していないというよりは、管理職としての責任感の表れともいえます。
自分が若手だった頃の常識が基準になっている
誰しも、自分が経験してきたことを基準に物事を判断しがちです。上の世代にとって、会社に行って仕事をするのは当たり前の日常でした。朝は満員電車に揺られて出社し、夜遅くまで同僚と仕事をするという働き方が、社会人としての常識だったのです。
そのため、リモートワークという新しい働き方に対して、どこか「楽をしている」「本気で仕事をしていない」といったイメージを持ってしまうことがあります。悪気があるわけではなく、自分たちが若かった頃の「常識」や「当たり前」が、今の働き方に対する考え方のベースになっているのです。
フル出社で働くことのメリット
出社に対してネガティブなイメージを持つかもしれませんが、実は良い面もあります。フル出社で働くメリットについて、以下の3つのポイントを解説します。
- 仕事とプライベートのメリハリがつけやすい
- 職場の人間関係を築きやすく相談もしやすい
- 会社の設備や環境が整った中で仕事ができる
各項目について、詳しく見ていきましょう。
仕事とプライベートのメリハリがつけやすい
フル出社の大きなメリットは、仕事モードと休息モードの切り替えがしやすいことです。家を出て会社に向かうことで、自然と「これから仕事だ」という気持ちになり、逆に会社を出て家に帰ることで「今日は終わり」と気持ちをリセットできます。
自宅で仕事をしていると、ついダラダラと夜遅くまで作業してしまったり、休日に仕事のメールをチェックしてしまったりと、オンとオフの境界線が曖昧になりがちです。物理的に場所を変えることが、心のスイッチを切り替えるきっかけになり、結果としてプライベートの時間をしっかり確保できるという利点があります。
職場の人間関係を築きやすく相談もしやすい
毎日顔を合わせることで、職場の同僚や先輩と自然と仲良くなれるのも出社のメリットです。一緒にランチに行ったり、休憩中に雑談をしたりする中で、相手の人柄を知り、信頼関係を築くことができます。
仕事で行き詰まった時も、隣にいる先輩に「ちょっといいですか?」と気軽に声をかけて相談できます。リモートワークだと、わざわざチャットや通話で連絡する必要があるため、少ししたことでは聞きづらいと感じることも多いでしょう。
良好な人間関係は、働きやすさに直結します。困った時にお互いに助け合える仲間がいることは、仕事をしていく上で大きな心の支えになります。
会社の設備や環境が整った中で仕事ができる
会社には、仕事に集中できる最高の環境が整っています。自宅の小さなノートパソコンとは違う、大きなデュアルモニターや、人間工学に基づいて設計された椅子、高速で安定したインターネット回線などは、作業効率を格段に上げてくれます。
また、必要な資料がすぐ手に取れる書庫や、高性能な複合機、静かな会議室など、自宅では用意するのが難しい設備も自由に使うことができます。
自分で仕事環境を整えるための費用や手間をかけずに、最高のパフォーマンスを発揮できる環境が用意されているのは、出社ならではの大きなメリットと言えるでしょう。
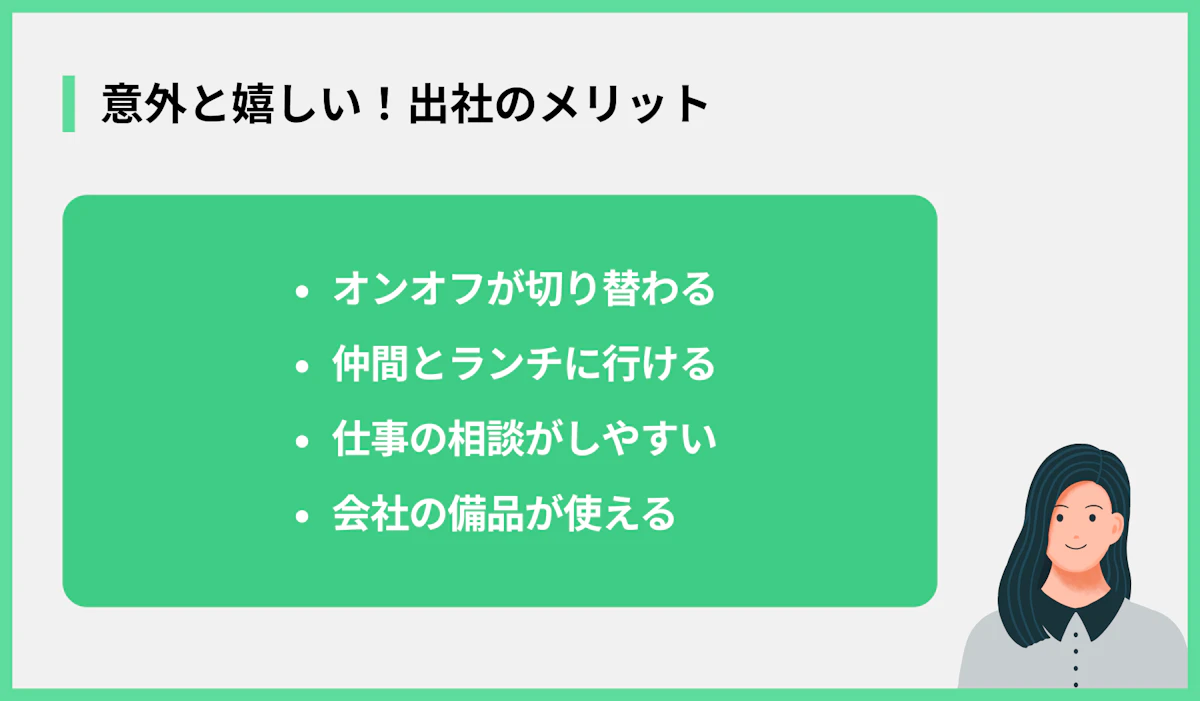
フル出社で働くことのデメリット
もちろん、フル出社にはメリットばかりではありません。多くの人が「無理だ」と感じるデメリットもあります。ここでは、以下の3つのデメリットについて解説します。
- 通勤による時間的・身体的な負担が大きい
- 人間関係のストレスを感じる場面が増える
- 集中を妨げられて自分のペースで仕事をしにくい
各項目について、詳しく見ていきましょう。
通勤による時間的・身体的な負担が大きい
フル出社の最も大きなデメリットは、毎日の通勤にかかる大きな負担です。朝の満員電車に揺られ、多くの人に押しつぶされそうになりながら会社に向かうだけで、仕事が始まる前に心身ともに疲れ果ててしまう人も少なくありません。
もし往復で2時間かかるとしたら、1週間で10時間、1ヶ月で約40時間もの時間を移動だけに費やしていることになります。この時間があれば、趣味や勉強、家族との時間など、もっと有意義なことに使えるはずです。この通勤時間がなくなるだけでも、生活の質が大きく向上すると感じる人は多いでしょう。
人間関係のストレスを感じる場面が増える
職場には様々な考え方を持つ人がいるため、どうしても苦手な人や合わない人がいるのは仕方のないことです。リモートワークであれば、必要な連絡だけを取れば済みますが、出社となるとそうはいきません。
常に同じ空間にいるため、苦手な上司の機嫌をうかがったり、合わない同僚と無理に会話を合わせたりと、人間関係によるストレスを感じる場面が増えてしまいます。仕事そのものよりも、こうした人間関係に悩んでしまい、会社に行くのが憂鬱になるケースは非常に多いです。
集中を妨げられて自分のペースで仕事をしにくい
オフィスは、自分の仕事に集中しづらい環境でもあります。集中して資料を作成している時に、周りの電話の音や話し声が気になったり、上司や同僚から急に声をかけられて作業が中断されたりすることが頻繁に起こります。
一度途切れた集中力を取り戻すのは、簡単ではありません。自分のペースで黙々と作業を進めたい人にとっては、周りの環境に左右されやすいオフィスよりも、一人で静かに作業できる自宅の方が生産性が上がると感じるでしょう。
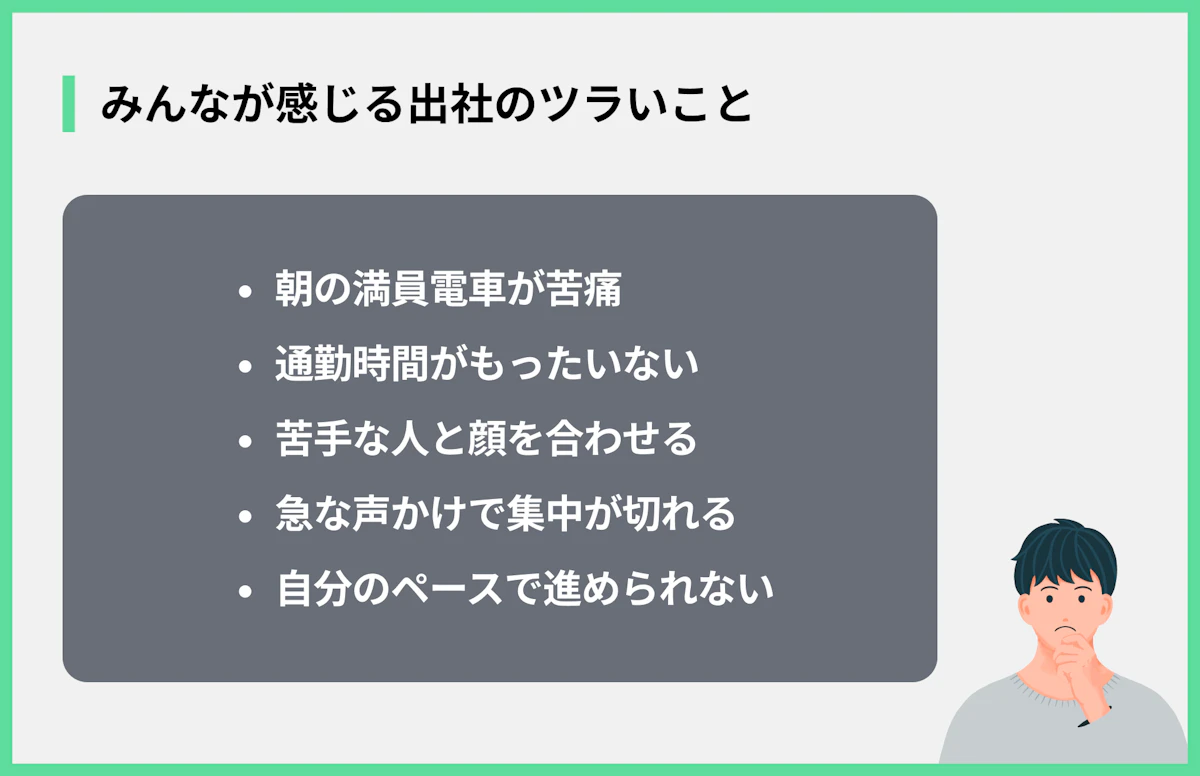
どうしてもフル出社が無理だと感じた時の対処法
会社の言うことにも一理ある、でもやっぱりフル出社は無理だ、と感じた時にはどうすれば良いのでしょうか。いくつか試せる対処法があります。以下の4つの方法を解説します。
- 上司にリモートワークの必要性を具体的に相談する
- リモートワークが可能な部署への異動を願い出る
- 副業を始めてリモートで働くスキルを身につける
- 働き方が合わないなら転職を本格的に検討する
各項目について、詳しく見ていきましょう。
上司にリモートワークの必要性を具体的に相談する
まずは、今の会社で状況を改善できないか試してみましょう。その際は、リモートワークで成果を出せることを示すのがポイントです。
ただ「出社したくない」と伝えるだけでは、わがままだと思われてしまうかもしれません。「週に2日リモートにすれば、通勤時間がなくなる分、この業務に集中できて生産性が上がります」といったように、会社側にもメリットがあることを具体的に伝えましょう。
また、家族の介護など、やむを得ない事情がある場合は、正直に伝えることで配慮してもらえる可能性もあります。自分の希望を冷静に、そして前向きに提案することが大切です。
リモートワークが可能な部署への異動を願い出る
今の部署では出社が必須でも、社内の他の部署ではリモートワークが認められているケースがあります。例えば、営業職から企画職へ、といったように、職種が変われば働き方も変わる可能性があります。
会社の就業規則や、社内公募制度などを確認してみましょう。もしリモートワークを導入している部署があれば、そこに異動できないか上司や人事部に相談してみるのも一つの手です。
会社を辞めずに働き方を変えられる可能性があるため、転職活動を始める前に、まずは社内でできることがないか探してみる価値は十分にあります。
副業を始めてリモートで働くスキルを身につける
将来的にリモートワーク中心の働き方をしたいと考えているなら、今のうちからリモートでできる仕事の経験を積んでおくことをおすすめします。例えば、Webライティングやデータ入力、簡単なデザインなど、未経験からでも始められる副業はたくさんあります。副業を通じて、チャットツールでのコミュニケーション方法や、時間管理のスキル、自己PRできる実績などを身につけることができます。
こうした経験は、転職活動の際に「リモート環境でもしっかり成果を出せる人材だ」という強力なアピール材料になります。まずは小さな一歩から始めてみましょう。
働き方が合わないなら転職を本格的に検討する
色々と試してみても会社の出社方針が変わらず、どうしても自分には合わないと感じるなら、思い切って環境を変えるのが最善策かもしれません。
働き方の価値観は人それぞれです。フル出社が合う人もいれば、フルリモートが合う人もいます。無理に自分を会社のやり方に合わせようとすると、心や体を壊してしまうことにもなりかねません。
世の中には、多様な働き方を認めている会社がたくさんあります。自分らしく、いきいきと働ける場所を求めて転職活動を始めることは、決して逃げではなく、未来のための前向きな選択です。
リモートワークができる会社への転職を成功させるコツ
転職を決意したら、次は成功させるための準備が必要です。入社後に「思っていたのと違った」と後悔しないために、以下の3つのコツを押さえておきましょう。
- 応募条件で勤務形態をしっかり確認する
- 面接でリモートワークの実態について質問する
- 自己管理能力やコミュニケーション能力をアピールする
各項目について、詳しく見ていきましょう。
応募条件で勤務形態をしっかり確認する
求人票を見る際は、「リモートワーク可」という言葉だけに飛びつかないように注意が必要です。この言葉には、様々な意味合いが含まれていることがあります。
例えば、「フルリモートOK」の場合もあれば、「基本は出社で、週に1〜2日だけリモート可」「入社後半年間は出社必須」といった条件付きの場合もあります。求人票の募集要項や待遇欄を隅々まで読み込み、どのような勤務形態が想定されているのかを正確に把握しましょう。
少しでも曖昧な点があれば、安易に応募せず、次のステップである面接でしっかり確認することが大切です。
面接でリモートワークの実態について質問する
面接は、会社のリアルな情報を知る絶好の機会です。入社後のギャップをなくすためにも、リモートワークの実態について具体的に質問しましょう。
例えば、「リモートワークと出社の割合はどのくらいですか?」「チームの皆さんは普段どのようなツールでコミュニケーションを取っていますか?」「リモートワークでも質問しやすい雰囲気はありますか?」といった質問が有効です。
こうした質問をすることで、働き方に対する自分のこだわりを伝えられるだけでなく、本当に自分に合った環境かどうかを見極めることができます。
自己管理能力やコミュニケーション能力をアピールする
リモートワークでは、自分で自分を律して仕事を進める力が求められます。上司や同僚が近くにいない環境でも、自分でスケジュールを管理し、責任を持って業務を遂行できることをアピールしましょう。
また、文章でのコミュニケーションが中心になるため、チャットやメールで要点を分かりやすく伝えたり、こまめに報告・連絡・相談をしたりする能力も重要です。
これまでの経験の中で、どのように自己管理をしてきたか、どのように周りと連携を取ってきたか、といった具体的なエピソードを交えて話せると、採用担当者にもあなたの魅力が伝わりやすくなります。
働き方の悩みはプロに相談してみよう
「転職も考えたいけど、何から始めたらいいか分からない…」そんな時は、一人で抱え込まずに転職のプロに相談してみましょう。具体的には以下の3つのメリットがあります。
- 今の会社に残るべきか客観的な意見をもらえる
- 自分の希望に合う会社の求人を紹介してもらえる
- Zキャリアのエージェントに相談してみよう
各項目について、詳しく見ていきましょう。
今の会社に残るべきか客観的な意見をもらえる
自分一人で悩んでいると、「本当に転職して良いのだろうか」「今の会社に残った方が安全なのでは」と、堂々巡りになってしまいがちです。
転職エージェントは、客観的な視点からアドバイスをくれる心強い味方です。あなたのキャリアプランや希望する働き方を丁寧にヒアリングした上で、「今の会社で働き方を変える交渉をしてみては?」「いや、思い切って転職した方が希望が叶いますよ」といったように、プロの視点から最適な道を一緒に考えてくれます。第三者の意見を聞くことで、自分の考えが整理され、納得のいく決断ができるようになります。
自分の希望に合う会社の求人を紹介してもらえる
転職サイトには載っていない「非公開求人」を紹介してもらえるのも、エージェントを利用する大きなメリットです。企業が非公開で求人を出す理由には、「人気の職種で応募が殺到するのを防ぎたい」「事業戦略に関わる重要なポジションを極秘で募集したい」などがあります。エージェントは、こうした表には出てこない優良企業の求人を多数抱えています。
また、「フルリモート可能」「残業が少ない」といった企業の内部情報にも詳しいため、あなたの希望にぴったり合った、働きやすい会社を見つけてくれる可能性が高まります。
Zキャリアのエージェントに相談してみよう
「原則出社」の方針に悩み、自分らしい働き方を見つけたいと考えているなら、ぜひZキャリアの転職エージェントに相談してみてください。Zキャリアは、特に若年層の転職サポートに強く、未経験から新しいキャリアに挑戦する方々を応援しています。
経験豊富なキャリアアドバイザーが、あなたの悩みや希望を親身に聞き、一人ひとりに合った求人の紹介から、履歴書の添削、面接対策まで、転職活動をトータルでサポートします。相談は無料ですので、「ちょっと話を聞いてみたい」という気軽な気持ちで大丈夫です。今の働き方にモヤモヤを感じているなら、まずは一歩踏み出して、プロに相談することから始めてみませんか。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)