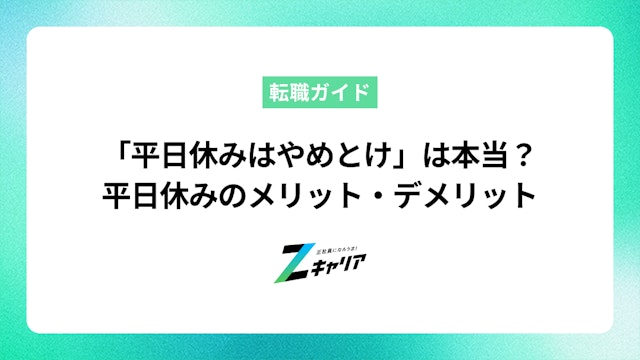- フレックスタイム制での出社の意味
- フレックスタイム制の基本ルール
- フレックスタイム制のメリット・デメリット
- フレックスタイム制が向いている人の特徴
- フレックスタイム制の仕事探しのポイント
フレックスタイム制における出社とはどんな働き方?
「フレックスタイム制」と聞くと、自由な時間に働けるイメージがあるかもしれません。では、フレックスタイム制における「出社」は、具体的にどのような働き方を指すのでしょうか。ここでは、その基本的な考え方について解説します。
- 出退勤の時間を自分で決められる働き方
- コアタイムには出社する義務がある
- リモートワークと組み合わせる場合も
各項目について、詳しく見ていきましょう。
出退勤の時間を自分で決められる働き方
フレックスタイム制の最も大きな特徴は、始業時間と終業時間を自分で決められる点にあります。例えば、「今日は朝早く仕事を始めて、夕方早めに帰ろう」「午前中に用事を済ませてから、お昼に出社しよう」といった働き方が可能です。毎日決まった時間に会社へ行くのではなく、自分の都合やその日の仕事内容に合わせて働く時間を調整できるのが、この制度の魅力です。ただし、完全に自由というわけではなく、会社ごとに定められたルールの中で時間を決める必要があります。この柔軟性が、仕事とプライベートの両立をサポートしてくれます。
コアタイムには出社する義務がある
フレックスタイム制を導入している多くの会社では、「コアタイム」という時間が設けられています。これは、全社員が必ずオフィスにいて仕事をしなければならない時間帯のことです。例えば、「11時から15時まで」のように設定されています。このコアタイムがあることで、会議やチームでの打ち合わせなどをスムーズに行うことができます。つまり、フレックスタイム制であっても、コアタイムが設定されている場合は、その時間は必ず出社して働く必要があるのです。求人情報を見る際は、このコアタイムの有無や時間帯をしっかり確認することが大切です。
リモートワークと組み合わせる場合も
最近では、フレックスタイム制とリモートワーク(在宅勤務)を組み合わせた働き方も増えています。この場合、出社するか自宅で働くかを日によって選べることがあります。例えば、「週に2日は出社して、残りの3日は自宅で働く」といったスタイルです。この働き方を「ハイブリッドワーク」と呼ぶこともあります。チームでの共同作業が必要な日は出社し、集中してひとりで進めたい作業は自宅で行うなど、仕事の効率を最大限に高めることができます。ただし、会社の方針によっては出社が基本で、リモートワークは許可制という場合もあるため、事前に確認が必要です。
フレックスタイム制での出社に関する基本ルール
フレックスタイム制で働くためには、いくつかの基本的なルールを理解しておく必要があります。具体的には、以下の3つのポイントが重要になります。
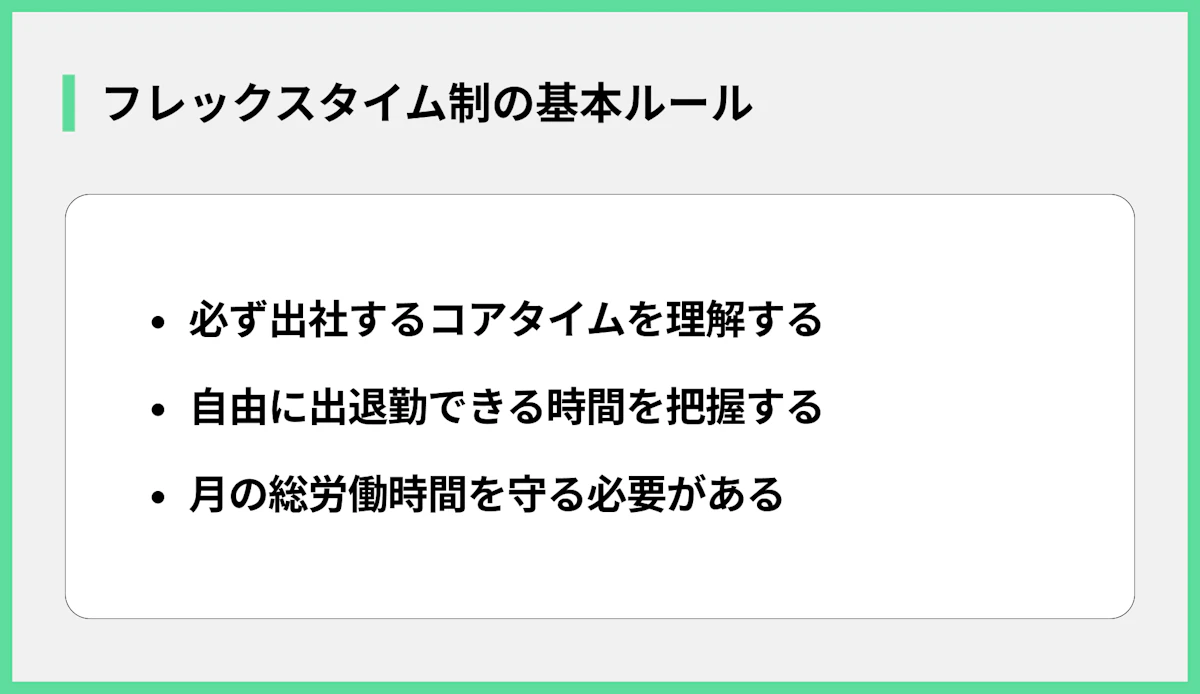
詳しく解説していきます。
必ず出社するコアタイムを理解する
先ほども触れましたが、コアタイムはフレックスタイム制の重要なルールの一つです。このコアタイムは必ずオフィスにいる必要があるため、自分の都合で休んだり、遅刻したりすることはできません。例えば、コアタイムが「11:00〜15:00」と定められている会社で働くとします。この場合、10時に出社しても、12時に出社しても問題ありませんが、11時から15時の間は必ず会社にいなければなりません。この時間を守ることが、チームワークを円滑にし、会社全体の生産性を保つ上で不可欠です。逆に、コアタイムが設定されていない「スーパーフレックス」という制度を導入している会社もあります。
自由に出退勤できる時間を把握する
コアタイム以外の、いつ出社・退社しても良い時間帯を「フレキシブルタイム」と呼びます。例えば、会社の勤務可能時間が7時から22時で、コアタイムが11時から15時の場合、7時から11時までと、15時から22時までがフレキシブルタイムにあたります。この時間内であれば、自分の裁量で働き始める時間と終える時間を決められます。「朝はゆっくりしたいから10時半に出社しよう」「夜に予定があるから16時に帰ろう」といった調整が可能です。このフレキシブルタイムを上手に活用することが、フレックスタイム制のメリットを最大限に活かす鍵となります。
月の総労働時間を守る必要がある
フレックスタイム制は自由な働き方ができますが、決められた労働時間分はきちんと働く必要があります。多くの場合、1ヶ月単位で「総労働時間」が定められています。例えば、「月間の総労働時間160時間」といった具合です。1日の労働時間が短かった日があれば、別の日に長く働くなどして、月全体で帳尻を合わせる必要があります。もし総労働時間に満たなければ給料が減ってしまったり、逆に超えすぎると残業代が発生したりします。日々の労働時間を自分でしっかりと管理し、月間の目標時間をクリアすることが求められます。
フレックスタイム制で働くメリット
自由な働き方ができるフレックスタイム制には、多くのメリットがあります。ここでは、代表的な3つのメリットについて見ていきましょう。
- 朝の通勤ラッシュを避けることができる
- プライベートの予定と両立しやすくなる
- 自分のペースで仕事を進められる
各項目について、詳しく見ていきましょう。
朝の通勤ラッシュを避けることができる
フレックスタイム制の大きなメリットの一つが、毎朝の満員電車や交通渋滞を避けられることです。多くの人が移動する時間帯をずらして出勤できるため、通勤によるストレスを大幅に減らすことができます。例えば、一般的な9時始業の会社が多い中、10時や11時に出社することで、座って通勤できる可能性も高まります。通勤だけで疲れてしまうということがなくなり、心身ともに余裕を持って一日をスタートできます。これは、日々のモチベーション維持にも繋がり、仕事のパフォーマンス向上にも良い影響を与えるでしょう。
プライベートの予定と両立しやすくなる
働く時間を調整できるため、仕事とプライベートの両立がしやすくなるのも魅力です。役所や銀行、病院など、平日の日中にしか開いていない場所へ行く用事も、仕事を始める前や途中で済ませることができます。例えば、「午前中に通院してから出社する」「仕事を早めに切り上げて、夕方から趣味の習い事に通う」といった生活が可能になります。家族との時間を大切にしたり、自己投資のための勉強時間を確保したりと、ライフスタイルに合わせた時間の使い方ができるため、生活全体の満足度が向上します。
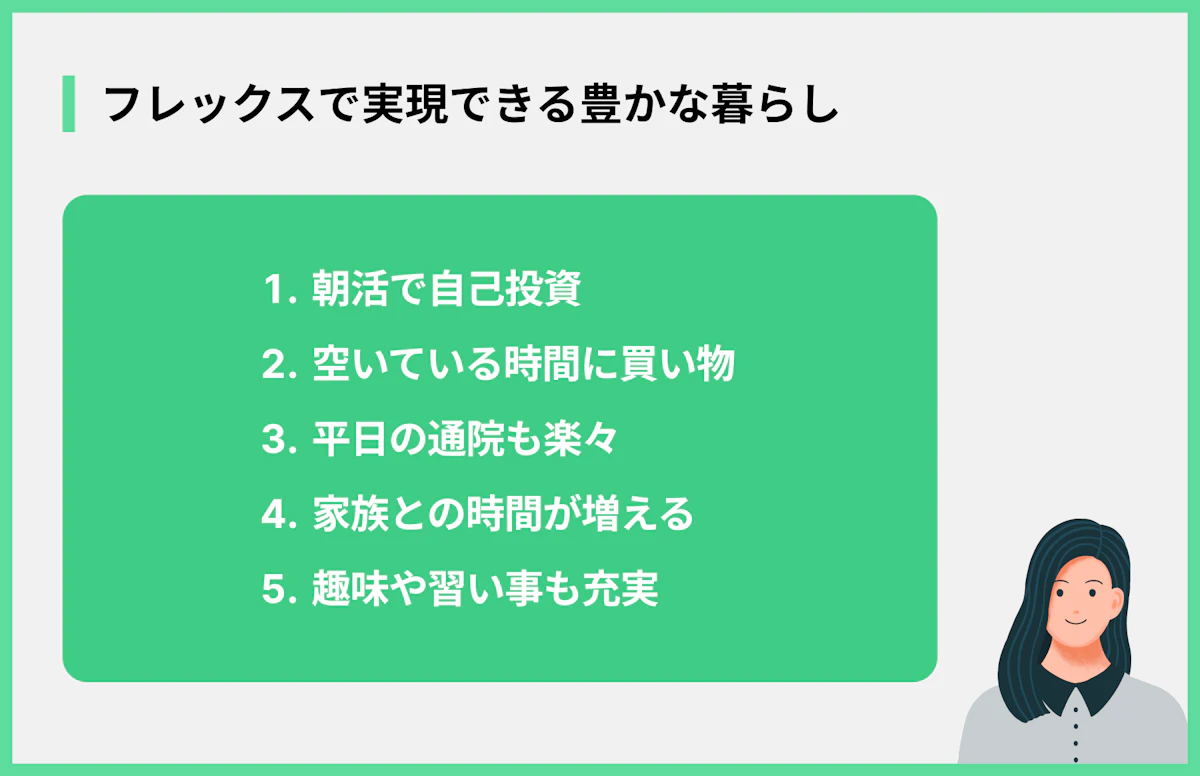
自分のペースで仕事を進められる
人にはそれぞれ、集中しやすい時間帯があります。「朝型」の人もいれば、「夜型」の人もいるでしょう。フレックスタイム制は、自分の集中力が高まる時間帯に仕事ができるため、生産性を高めやすいというメリットがあります。頭が冴えている午前中に集中力が必要な作業を終わらせ、午後は比較的簡単なタスクをこなす、といった効率的な働き方が可能です。他人に合わせるのではなく、自分のリズムで仕事を進められるため、ストレスが少なく、より質の高い成果を出すことにも繋がります。
フレックスタイム制で働くデメリット
多くのメリットがある一方で、フレックスタイム制には注意すべきデメリットも存在します。良い面だけでなく、難しい面も理解しておくことが大切です。
- 自己管理能力が求められる
- 社員同士で顔を合わせる機会が減る
- 導入している企業はまだ多くない
詳しく解説していきます。
自己管理能力が求められる
フレックスタイム制では、日々の労働時間を自分で管理する必要があります。いつ働き、いつ休むかを自分で決める自由がある分、責任も伴います。つい楽な方に流されてしまい、月末に総労働時間が足りなくなってしまう、という事態も起こり得ます。また、納期や締め切りを守るためのスケジュール管理も重要です。誰かに指示されなくても、自分で計画を立てて仕事を進める姿勢が求められます。「自由=楽」というわけではなく、むしろ高いレベルの自己管理能力が成功の鍵を握っていると言えるでしょう。
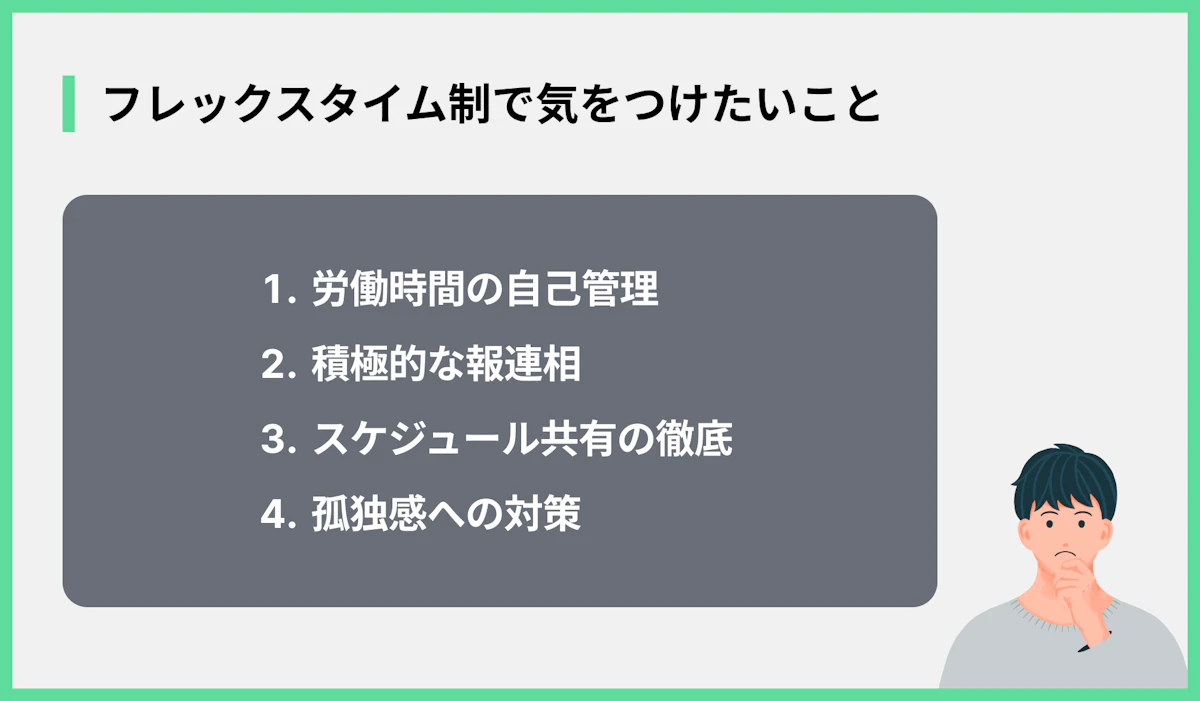
社員同士で顔を合わせる機会が減る
社員それぞれが異なる時間帯で働くため、オフィスにいるメンバーが揃いにくくなります。これにより、チーム内のコミュニケーションが不足しがちになるというデメリットがあります。ちょっとした相談や雑談から生まれるアイデアや、一体感が生まれにくくなる可能性があります。認識のズレが生じたり、情報共有が遅れたりしないように、チャットツールを積極的に活用したり、定期的にミーティングの時間を設けたりといった工夫が必要です。特に、新しく入社したばかりの頃は、周りの人に質問しにくい状況が生まれる可能性も考えられます。
導入している企業はまだ多くない
魅力的な働き方であるフレックスタイム制ですが、すべての企業で導入されているわけではありません。特に、工場でのライン作業や店舗での接客業など、全員が同じ時間に働く必要がある職種では、導入が難しいのが現状です。そのため、フレックスタイム制で働きたいと思っても、求人の選択肢が限られてしまう可能性があります。IT業界や企画職、事務職など、個人の裁量で仕事を進めやすい職種に導入されることが多い傾向にあります。自分の希望する業界や職種で、この制度があるかどうかを事前にリサーチすることが重要です。
フレックスタイム制が向いている人の特徴とは?
ここまで見てきたメリット・デメリットを踏まえると、フレックスタイム制はどのような人に向いているのでしょうか。ここでは、具体的な3つの特徴を解説します。
- 自分でスケジュールを管理できる人
- ひとりで集中して作業するのが得意な人
- 仕事と私生活のバランスを重視する人
詳しく見ていきましょう。
自分でスケジュールを管理できる人
フレックスタイム制で成果を出すためには、計画的に仕事を進める自己管理能力が不可欠です。誰かに指示されなくても、自分でタスクの優先順位をつけ、納期から逆算してスケジュールを立てられる人が向いています。例えば、「今週中にこの資料を完成させるために、今日はここまで進めよう」「明日は外出があるから、今のうちにこの作業を片付けておこう」といったように、先を見越して行動できる能力が求められます。自分のペースで仕事を進められる反面、その進捗に責任を持つ必要があるため、自律性の高い人に向いている働き方と言えます。
ひとりで集中して作業するのが得意な人
この制度では、周りに人が少ない環境で仕事をする時間も増えます。そのため、他人の目を気にせず、ひとりで黙々と作業に集中できる人は、フレックスタイム制で高いパフォーマンスを発揮しやすいでしょう。オフィスが静かな早朝や、人が少なくなった夜の時間帯を有効活用して、集中力が必要な作業を一気に片付けることができます。逆に、常に周りとコミュニケーションを取りながら仕事を進めたい人や、少し寂しさを感じてしまう人にとっては、物足りなさを感じる場面もあるかもしれません。
仕事と私生活のバランスを重視する人
仕事だけでなく、プライベートの時間も大切にしたいと考えている人にとって、フレックスタイム制は非常に魅力的な働き方です。この制度を活用すれば、仕事と生活の調和、いわゆる「ワークライフバランス」を実現しやすくなります。例えば、子育てや介護との両立、趣味や資格取得のための勉強、通院など、個々の事情に合わせた柔軟な働き方が可能です。決められた時間で働くのではなく、自分の人生設計に合わせて仕事の時間を組み立てたいという価値観を持つ人には、最適な選択肢の一つとなるでしょう。
フレックスタイム制の仕事を探す際のポイント
フレックスタイム制の仕事を希望する場合、求人を探す際にいくつか押さえておきたいポイントがあります。ここでは、失敗しないための3つのチェックポイントを紹介します。
- コアタイムの時間帯を確認する
- 制度が実際に利用されているか調べる
- どんな職種で導入されているか見極める
詳しく解説していきます。
コアタイムの時間帯を確認します
求人票に「フレックスタイム制導入」と書かれていても、その詳細は会社によって様々です。まず確認したいのが、コアタイムの有無とその時間帯です。コアタイムが長いと、実質的に働ける時間の自由度は低くなります。例えば、コアタイムが「10時〜17時」のように設定されている場合、一般的な勤務時間とあまり変わらないと感じるかもしれません。一方で、コアタイムが「11時〜14時」のように短ければ、それだけ柔軟な働き方がしやすくなります。自分の理想とする働き方と、その会社のコアタイム設定が合っているかを必ず確認しましょう。
制度が実際に利用されているか調べます
制度として存在していても、実際に社員がどの程度利用しているかは重要なポイントです。「制度はあるけれど、周りが使っていないので利用しづらい…」というケースも残念ながら存在します。面接の際に、「フレックスタイム制は、皆様どのくらい活用されていますか?」といった質問をしてみるのがおすすめです。社員の利用率や、会社全体で制度の活用を推奨している雰囲気があるかどうかを確認することで、入社後のミスマッチを防ぐことができます。利用実績が豊富であれば、気兼ねなく制度を活用できる可能性が高いでしょう。
どんな職種で導入されているか見極めます
前述の通り、フレックスタイム制はどんな職種でも導入できるわけではありません。一般的には、個人の裁量で仕事を進めやすい職種で導入されることが多いです。例えば、ITエンジニア、Webデザイナー、企画・マーケティング職、一部の事務職などが挙げられます。一方で、工場の製造ライン、店舗の販売スタッフ、建設現場の作業員など、チームで一斉に動く必要がある仕事や、お客様対応が特定の時間帯に集中する仕事では導入が難しい傾向にあります。自分の希望する職種が、フレックスタイム制になじむかどうかを見極めることも大切です。
自分に合った働き方を見つけたい方へ
ここまで、フレックスタイム制における出社の考え方や、メリット・デメリットについて解説してきました。自分に合った働き方を見つけるために、最後にできることを考えてみましょう。
まずは理想の働き方を考えてみよう
フレックスタイム制に限らず、世の中には様々な働き方があります。まずは、自分がどんな働き方をしたいのかを具体的に考えることが第一歩です。「時間や場所に縛られずに働きたいのか」「安定したリズムで働きたいのか」「プライベートの時間を最優先したいのか」など、仕事に求めるものを整理してみましょう。自分の価値観が明確になることで、数ある求人の中から、本当に自分に合った会社を見つけやすくなります。理想の働き方を思い描くことが、後悔しない転職活動のスタートラインです。
Zキャリアのエージェントに相談してみよう
自分ひとりで理想の働き方を見つけたり、求人情報を吟味したりするのは大変な作業です。そんな時は、転職のプロであるキャリアエージェントに相談するのがおすすめです。Zキャリアでは、ノンデスクワーカーの仕事に詳しいエージェントが、一人ひとりの希望や適性を丁寧にヒアリングします。その上で、フレックスタイム制を導入している企業はもちろん、様々な働き方ができる求人の中から、最適なものを紹介します。求人票だけでは分からない社内の雰囲気や制度の利用実態といった情報も提供できる場合があります。少しでも興味があれば、まずは気軽に相談してみてください。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)