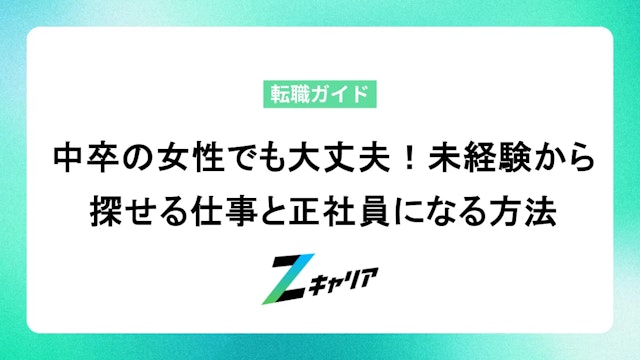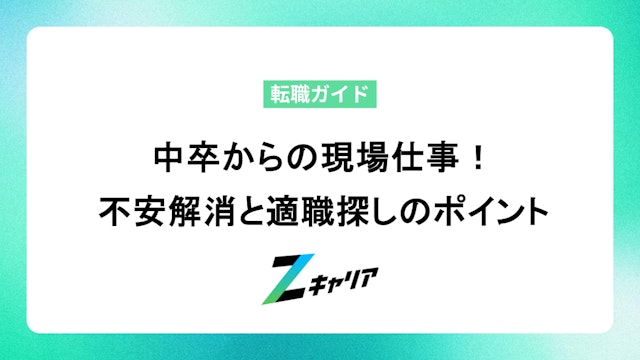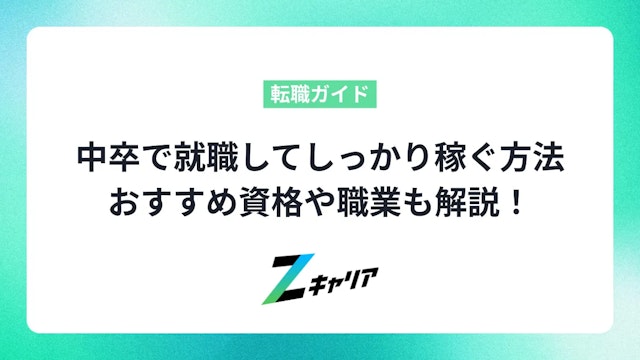- 中卒から取得できる資格
- 中卒から取れる国家資格
- 中卒から資格を取るポイント
中卒でも独学で取れる資格は結構ある!学歴不問の資格一覧!
「中卒でも資格を取って就職につなげたいけど、学歴がハードルになりそうで不安」という方には民間資格の取得がおすすめです。国家資格は受検にあたって厳しい要件が設けられているものもあるため、中卒からの取得はハードルが高いかもしれません。
その点、民間資格であれば学歴や年齢が不問のものも多いため、中卒から比較的気軽にチャレンジしやすい点が魅力です。
ここでは、「中卒から独学でも取得しやすい主な民間資格」を解説します。
- フードコーディネーター
- 食品衛生責任者
- トリマー
- 動物看護助手
- ペットシッター
- 保育補助者
- ベビーシッター
- 医療事務(民間資格)
- 調剤薬局事務(民間資格)
- メンタルヘルス・マネジメント検定
- 心理カウンセラー(民間団体の認定資格)
- ネイリスト技能検定
- 色彩検定
- パーソナルカラー検定
- 販売士(リテールマーケティング検定)
- 日商簿記
- マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト(MOS)
- Webデザイナー検定
- CAD利用技術者試験
- 運転免許
- SEO検定
- 介護事務
- 介護職員初任者研修
フードコーディネーター
フードコーディネーターはフードビジネスの最前線で仕事をしたい方にはおすすめの資格であり、料理の栄養や見た目を調整しつつ食生活を豊かにする専門職です。調理だけでなく、献立や食材の提案など、食に関する幅広い知識とセンスが求められます。飲食業界、メディア、商品開発の分野で活躍しているほか、最近では介護施設などでも採用が進んでいます。フードコーディネーターの運営団体は、「日本フードコーディネーター協会(JFCA)」です。資格は3級、2級、1級の3つの区分があり、それぞれのレベルで必要とされる知識とスキルが定められています。資格の取得ルートとしては、協会が認定する講座の受講と、実務経験を積んだうえで受検するルートの2つがあります。講座では、食品の栄養や衛生、撮影時のスタイリング技術、食空間の演出といった幅広い知識が習得可能です。フードコーディネーターを取得することで、飲食店のプロデュース、レシピ本の出版、料理教室の運営など、活躍できる分野が広がります。
食品衛生責任者
食品衛生責任者は飲食業に関心がある方にとってはおすすめの資格と言えるでしょう。食品を取り扱う施設において衛生管理を担い、飲食店、給食施設、食品工場、介護施設など、食品を扱う現場では配置が義務づけられている専門職です。食品衛生責任者は国家資格ではなく、各都道府県の保健所が実施する講習を修了することで取得できます。講習を受けることで食品衛生法、食中毒予防、施設の衛生管理、手洗いや調理器具の取り扱いなど、実務に直結する専門的な知識・スキルを習得可能です。食品衛生責任者は指定の講習(おおむね6時間程度)を受けることで取得できます。特別な試験はありませんが、実務で求められる高度な専門知識を身につける必要があるため、受講には集中と責任感が必要です。
トリマー
トリマーは、ペット、特に犬や猫などの体毛の手入れを専門とする職種です。そのほかにシャンプー、カット、ブラッシング、爪切り、耳掃除などを行い、ペットの健康と清潔感を保つ役割を担います。トリマーは国家資格ではなく、民間団体が運営する認定資格が主流です。「日本動物専門学校協会」や「ジャパンケネルクラブ(JKC)」などが代表的な認定団体として知られています。資格取得のルートとしては、動物系の専門学校が一般的です。専門学校で2年間学ぶことで受検資格が得られます。通信講座もありますが、トリミングは実技が中心となるため、対面で学んだほうがよりスムーズに習得できるでしょう。講義では動物看護学やペットの行動学、犬種ごとのトリミング技術などが学べます。トリマーの資格はペットサロンへの就職で必要です。また、個人で開業する際もトリマー資格を持っていることで信頼性が高まるでしょう。ペットブームの中でトリマーの需要は増しており、スキルの高いトリマーは高く評価されています。
動物看護助手
動物看護助手は、動物病院や動物クリニックで獣医を補助する職種です。動物看護助手の資格を取得することで必要な知識を証明でき、動物病院への就職がスムーズになるでしょう。診療の準備や後片付け、飼い主への対応、清掃や記録管理など、業務内容は多岐にわたります。民間認定資格で、「日本動物看護職協会」や「全国動物専門学校協会」などが運営する講座を受講することで資格の取得が可能です。取得ルートとしては通信講座を受講しつつ実務経験を積むスタイルが一般的と言われています。講座では、動物の体の構造、栄養管理、薬の投与方法、心肺蘇生法など、専門知識の習得が可能です。働くうえで資格は必須ではないため、実務経験を通してより実践的なスキルを身につけられます。
ペットシッター
ペットシッターは、飼い主が外出している間にペットのお世話を代行する専門職で、通信教育や短期講座で取得できるため、「動物関連の資格を取得したい」人におすすめです。食事の準備やトイレの掃除、散歩、遊び相手など、ペットの生活を維持するためのサポートを行います。民間資格であり、「日本ペットシッター協会」や「日本ペット技能検定協会」などが主な認定団体です。講座を受講することで、動物行動学、応急処置法、飼い主との信頼関係構築のメソッドなどを身につけられます。資格取得後は協会に登録することで仕事を紹介してもらえるケースもあります。動物看護助手の資格を取得すれば、ペットサービス業への就職や副業としての開業に有利です。
販売士の資格を取得することで販売現場での実務スキルを証明できるため、小売業界や流通業界では、ステップアップの面で特に有利にはたらくでしょう。販売士は、販売に関する知識や接客技術、マーケティング理論の応用スキルなどの専門性を認定する資格です。この資格を取得することで小売業・サービス業などへの就職で有利になります。運営団体は「日本商工会議所」です。
1級から3級までの3段階で構成されており、3級では基本的な小売業の知識や接客技術が問われます、2級ではマネジメントや経営管理の視点もくわわり、1級では店舗経営の全体像を理解したうえでの部下の育成や商品戦略など、より高度な理論と実践力が必要です。資格の取得には専門学校や通信講座、書籍を活用した独学など、複数のルートがあります。最近ではオンライン受検にも対応しており、自宅からの資格取得も可能です。接客スキルだけでなく、顧客心理の理解やマーケティングを総合的に分析する力も養えるため、将来的に事業を展開したい方にもおすすめです。
日商簿記
日商簿記は、簿記会計の知識とスキルを証明する資格です。簿記の基礎から始まり、財務諸表の作成、原価計算、経営分析に至るまで、ビジネスに欠かせないスキルを体系的に学ぶことで経理スキルを身につけます。日商簿記は日本商工会議所が主催しており、区分は1級から3級までの3段階です。2級以上になると工業簿記が加わり、製造業の会計処理にも対応できる力が身につきます。税理士や公認会計士を目指すなら、1級相当の知識が必要です。取得ルートとしては、商業高校や専門学校、または通信講座などが用意されています。
近年では、オンライン講座の動画配信も充実しているため、在宅での学習はもちろん、通勤・通学の合間を利用しての資格取得も可能です。日商簿記はあくまでも民間資格であり、経理職として働くうえで必須ではありません。しかし、簿記を取得しておくことで企業会計についての専門的な知識を証明できるため、就職・転職で有利にはたらきます。
マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト(MOS)
MOS(マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト)は、Excel、Word、PowerPoint、Outlook、Accessなど、Microsoft Office製品の操作スキルを客観的に証明できる国際資格です。MOSはマイクロソフト社公認の専門資格であり、「株式会社オデッセイコミュニケーションズ」によって運営されています。試験は世界共通の基準で行われるため、資格の保有者は日本国内だけでなく海外でも評価される点が魅力です。
取得ルートとしては、民間の資格学校や通信講座のほか、市販の教材による独学などがあります。試験は定期的に開催されており、PCの操作に慣れていない方でも3ヶ月〜半年程度で取得を目指せます。MOSを取得すると、事務職や営業アシスタントなどの事務職で優遇されるため、転職時の大きなアピールポイントになるでしょう。今の時代、PCの操作スキルはほぼすべての職種で必要とされるため、非常に汎用性の高い資格と言えます。
Webデザイナー検定
Webデザイナー検定は、Web制作に必要な知識や技術、クリエイティブな表現力を評価する資格です。ここ数年、質の高いWebデザインのニーズは年々高まっており、現場では即戦力としてのスキルが求められます。Webデザイナー検定を管轄するのは公益財団法人「画像情報教育振興協会(CG-ARTS)」です。試験は「ベーシック」と「エキスパート」の2つのレベルに分かれており、フリーランスとして本格的に活動するならエキスパートがおすすめです。資格取得のルートには、Web制作の専門学校や通信講座によるカリキュラム修了があり、最近では独学も増えています。また、Webデザイナーとしての実務経験を積んだうえでの資格取得も可能です。Webデザイナー検定を取得することでWeb制作会社への就職が有利になるだけでなく、フリーランスとして独立する際の信頼性向上にもつながります。検定自体はデザインの知識を問う設問がメインです。ただ、実務ではPhotoshopやプログラミングなど、幅広い知識が求められるため、Webデザインの世界で本格的に活躍したい方はできるだけ幅広いジャンルの知識を吸収しておくことで仕事の幅が広がります。
CAD利用技術者試験
CAD利用技術者試験は、建築、土木、機械設計などの分野で活用されるCADソフトウェアの操作技能を評価する資格試験です。CADを活用して製図作業を効率化し、正確な設計図を作成するスキルが求められます。運営団体は一般社団法人「コンピュータ教育振興協会(ACSP)」です。試験は2次元・3次元のそれぞれに対応しており、1級・2級のレベルに分かれています。CADの専門スクールや資格学校の修了が主な取得ルートです。就職にあたって資格の取得は必須ではないため、実務経験を積んだうえで受験すれば、学習がよりスムーズに進むでしょう。この資格を取得することで設計職やエンジニア職としての信頼性が向上し、就職や転職で有利になるほか、専門性が高まるため収入アップにもつながります。
運転免許
運転免許は、日常生活から仕事まで幅広く活用される、もっとも実用的な資格のひとつです。普通自動車免許をはじめ、二輪、大型、二種免許など、用途に応じて多様な種類があります。運転免許の管轄は、各都道府県に設置された公安委員会です。自動車教習所での学科と実技講習を修了し、試験に合格することで取得できます。通学制の教習所や短期集中の合宿免許などが主な取得ルートです。近年では、自動車学校によるオンライン学科も普及しています。
運転免許はトラック運転手などの運送業、配達業務で必須です。そのほか、利用者の送迎が必要な介護業界でも取得を勧められるケースがあります。
SEO検定
「Web制作会社や企業のサイト制作でスキルを発揮したい」「できるだけ取得のハードルが低い資格を探している」という方は、SEO検定の取得を検討しましょう。
SEO検定は、一般社団法人「全日本SEO協会」が管轄する検定試験です。取得することで主にGoogle向けのSEO対策についての知識及び実践的なスキルを証明できます。1級から4級までの4つに分かれており、受検にはランクに合わせた受検料がかかります。受検にあたって特に制限はなく、希望すれば基本的に誰でも受験可能です。試験は筆記試験のみのマークシート方式で、80%以上の正答率で合格となります。東京会場では原則として月に2回試験が実施され、日程も柔軟に選べるため、社会人でも比較的受検しやすい点が大きな魅力です。
SEO検定は国家資格ではないため、取得したからと言って直接的に就職や転職が有利に進められるわけではありません。ただ、小規模な企業でもSEO対策に力を入れているところが増えており、SEOの技術が活かされる領域は広がりつつあります。最近では、ChatGPTをはじめとする生成AIがますます進歩し、「SEO対策の仕事を奪うかもしれない」という懸念点があるのも事実です。ただ、AIの進歩を恐れるのではなく、アシスタントとして有効活用しつつ、共存するルートを考えたほうが生産性向上につながるでしょう。Web制作の業界に少しでも興味関心がある方にはSEO検定がおすすめです。
介護事務
介護職としての経験や介護保険の専門知識を活かしたい、という方は、介護事務の資格を取得することで活躍の幅が広がるかもしれません。介護事務は、介護事業所や老人ホームなどの施設に在籍し、主にレセプトの作成(介護報酬請求業務)を担当します。書類処理などの事務作業がメインの仕事ですが、窓口での受付も大切な業務です。
資格取得にあたって、特別な条件はありません。主な取得ルートとしては、資格学校の講座や独学などが挙げられます。社会人でも受検できるため、すでに介護職や介護保険の現場で実務経験を積んでいる方は有利かもしれません。また、介護事務としての採用にあたって資格は必須ではなく、最近では実務経験を通して必要な知識を吸収し、タイミングを見て試験を受けるパターンが増えています。介護事務として長く働くのであれば、ケアクラークや介護事務管理士、介護保険事務管理士などの関連資格を合わせて取得することでスキルが証明でき、将来的なベースアップにつながるでしょう。
医療事務
育児・介護と両立させたい方におすすめの資格としては医療事務が挙げられます。医療事務は、病院やクリニックなどの医療機関で事務的な業務を担当する職種です。患者の受付対応、診療報酬請求業務(レセプト作成)、カルテ管理などが主な業務内容に含まれており、医療従事者が治療に専念できるよう、事務職として医療現場を支える重要な役割を果たしています。
国家資格ではなく、学歴不問の民間資格です。代表的な運営団体としては「日本医療事務協会」「ニチイ学館」「日本医療教育財団」などが挙げられます。認定団体によって具体的なカリキュラムや出題範囲は多少異なるものの、医療保険制度の基礎や診療報酬請求に関する知識が求められる点は共通しています。独学でも取得できますが、講座を受講してから受検するパターンが一般的です。ここ数年はオンライン学習の環境も整っており、働きながらでも学びやすくなっています。未経験者でも比較的チャレンジしやすく、働きながら取得を目指せるため、比較的ハードルの低い資格と言えるでしょう。
医療事務の資格を取得することで、医療現場での事務職としての就職・転職でも大きなアピールポイントになります。また、専門性の高い資格のため全国的に安定した需要があり、「一生使える資格」としてもおすすめです。さらに、資格取得後も実務経験を積むことで、診療情報管理士など上位資格へのステップアップにもつながるでしょう。体力をさほど必要としない職種のため、子育てや介護と両立しながら働きたい方にも向いています。
ケアマネジャー
介護職からさらなるステップアップを目指したい方におすすめの資格としては、ケアマネジャーが挙げられます。ケアマネジャーは正式には「介護支援専門員」と呼ばれる公的資格です。高齢者や障害者が介護保険サービスを適切に受けられるよう、ケアプランの作成やスケジュールの調整を担います。より具体的には、介護サービスの利用者本人と家族の要望を聞き取り、必要なサービスを提案し、事業者との連携を図るのが主な役目です。介護や保険など、幅広い専門知識が求められるため、介護職としての実務経験があれば中卒でも十分にチャレンジ可能です。 各都道府県が資格を管轄・運営しており、試験は原則として年1回実施されています。
試験内容は介護保険制度や医学・福祉に関する知識など広範囲に及ぶため、時間をかけた準備が必要です。また、受験には「介護福祉士」「看護師」などの資格を有し、原則として5年以上(900日以上)の実務経験を積んでいることが条件です。この実務要件を満たせば、学歴は不問のため、中卒でも受験資格を得ることが可能です。 カリキュラムを修了して受験資格を得た後、試験に合格し、さらに都道府県管轄の実務研修を修了することで登録が完了します。
ケアマネジャーの資格を取得すれば、将来的なベースアップも可能です。業務の責任が重い職種のため、給与面でも優遇されることが多いでしょう。さらに、施設や地域包括支援センターなど、活躍の場が広がる点も魅力です。また、制度や法律に基づいて業務を行う必要があるため、常に最新の知識を学びつづける姿勢が求められます。
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修は、介護業界への第一歩として位置づけられる基礎的な資格であり、中卒からエントリーしやすい資格としてもおすすめです。以前の「ホームヘルパー2級」にあたる資格で、介護に必要な基礎知識と実践的なスキルを証明できます。高齢者や障害者の日常生活を支える介助技術を学び、介護の現場で即戦力として働ける力を身につけることが主な目的です。介護職員初任者研修を持っていなければ、介護施設において利用者の介護業務に携わることができません。都道府県及び厚生労働省の認可を受けた研修機関が管轄し、試験を実施しています。講座は、座学と演習が組み合わされたカリキュラムで構成されており、最長で130時間の課程を修了し、修了評価に合格することで資格が得られます。取得にあたって特別な要件はないため、年齢や経験を問わず誰でもチャレンジ可能です。そのため、特に未経験者や異業種からの転職者にとってハードルの低い資格と言えるでしょう。資格取得後は、訪問介護や介護施設など、幅広い職場で採用されやすくなります。くわえて、利用者の体に直接触れる「身体介護」を行うためには、さらに上位の資格が必要です。介護業界では長らく人材不足が慢性化しており、資格保有者の需要がよりいっそう高まっています。
中卒でも取れる国家資格を一覧で紹介
「中卒であってもより高収入の職種を目指したい」という方は国家資格の取得を視野に入れましょう。国家資格は民間資格と比較して受検にあたっての要件が厳しいものが多く、取得までに時間がかかるのも事実です。ただ、その分だけ取得後は信頼性が向上し、将来的なベースアップを実現しやすくなります。中卒で取得できる主な国家資格は以下の通りです。
- 施工管理者
- 危険物取扱者
- 第二種電気工事士
- 消防設備士
- 建設機械施工技士(2級)
- 浄化槽管理士
- 海技士
- 小型船舶操縦士
- 調理師
- 理容師
- 美容師
- 運行管理者
- 毒物劇物取扱責任者
- 登録販売者
- 宅地建物取引士
施工管理者
施工管理者は、建設現場における品質・工程・安全・原価の4つのステップを管理する専門職として知られています。正式な呼称は「施工管理技士」です。土木・建築・電気・管工事など、分野ごとに必要な資格が分かれており、現場の作業員や設計者、施主などと連携しつつ、工事が円滑かつ安全に進むように全体を統括するスキルが求められます。これは国土交通省が指定する国家資格であり、分野ごとに設けられた国の指定試験機関が試験の管理・運営を行っています。資格取得のルートは経験によって異なり、最終的な資格取得には実務経験が必要な点が特徴です。資格は1級と2級があり、それぞれ第一次検定、第二次検定に分かれています。
近年、受験資格が見直され、第一次検定は実務経験がなくても一定の年齢(例:2級17歳以上、1級19歳以上)で受験可能になりました。最終的に資格を取得するには、第二次検定の合格と所定の実務経験が必要です。また、1級の取得者は現場の主任技術者や監理技術者としての業務を担えるため、就職後の幅が広がるでしょう。また、施工管理者を取得することで、建築現場における管理職やリーダーポジションなど、より上位の職種へのステップアップにつながります。建設業界では常に人材不足が課題となっており、資格を持っているだけで全国どこの現場でも重宝されるでしょう。
さらに、施工管理者として経験を積むことでインフラ整備や再開発プロジェクトなど、より大規模なプロジェクトに関わるチャンスも広がります。実務を通してさらなるキャリアアップが期待できる分野でもあるため、現場経験を活かしてキャリアを形成したい、という方にとっては価値のある資格と言えるでしょう。
参照:「令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります/国土交通省」
危険物取扱者
危険物取扱者は、消防法に基づいて定められた国家資格であり、ガソリンや灯油、アルコールなどの引火性の高い物質を安全に管理・取り扱うために必要とされる専門資格です。化学工場やガソリンスタンド、塗料会社など、危険物を日常的に扱う業種では取得が義務づけられています。危険物取扱者の資格を取得することで、火災や爆発などの重大事故を未然に防ぐための知識と技術を証明可能です。
資格試験は一般財団法人「消防試験研究センター」によって管轄されています。試験は全国各地での定期実施です。資格には「甲種」「乙種」「丙種」の3種類があり、それぞれに取り扱える危険物の種類や量に制限があります。
丙種はもっとも基礎的な資格で、主にガソリンや灯油などの取扱いに限定されます。受験資格に制限がないため、初心者でも取得しやすいのが特徴です。乙種には1類から6類までの区分があり、特定の危険物に関する専門知識が問われます。甲種はすべての危険物を取り扱うことが可能です。ただし、理系大学での化学系カリキュラムの履修など、受験資格には一定の条件があります。乙種・丙種は受験資格が緩やかで、学歴不問のため中卒からでもチャレンジ可能です。ガソリンスタンドでのアルバイトなどであれば丙種のみでも充分ですが、将来的なキャリアアップを視野に入れているのであれば甲種まで取得しておいたほうが役に立ちます。資格の保有者を必須としている職場も多く、転職においても大きな強みとなるでしょう。
第二種電気工事士
第二種電気工事士は、一般住宅や小規模な店舗などの電気設備の配線工事や修繕を行うために必要とされる国家資格です。法律により、電気の配線やコンセント、スイッチ、照明設備などの設置や修繕などの業務では第二種電気工事士の保有が義務づけられています。一般財団法人「電気技術者試験センター」によって運営されており、試験は年に2回、全国各地からの受検が可能です。また、年齢や学歴などによる受検資格の制限もありません。
試験は筆記試験(学科)と技能試験(実技)の2部構成で行われ、学科では電気理論や配線図、安全管理など、基礎的な電気の知識が問われます。一方、技能試験では、実際の配線作業を模した課題が中心となり、実務レベルのスキルが必要です。実技に関しては、工具の扱いや配線の経験が主に問われるため、実務経験を積んだうえで受検すると合格可能性が高まるでしょう。
電気関係の職種に就きたいのであれば、早い段階で第二種を取得しておくことで第一種電気工事士へのステップアップにもつながります。また、第二種電気工事士は国家資格であるため社会的な信頼が非常に高く、資格手当が支給される企業も少なくありません。また、個人事業主として開業する道も開かれており、自らの技術を活かして安定した収入を確保することも可能です。最近では、高齢化社会の加速に伴って住宅のリフォームやバリアフリー化などの需要が高まっており、電気工事士の活躍できる範囲は今後ますます広がるだろうと見込まれています。
消防設備士
消防設備士は、建物に設置される消防用設備の工事や点検、整備を行うために必要な国家資格です。火災などの緊急時に備えた設備を適切に管理するために欠かせない専門職であり、消防法に基づいた国家資格として定められています。
試験は甲種と乙種に分かれており、主な違いは扱える設備の種類や業務範囲です。甲種なら工事・整備・点検が可能で、乙種では整備と点検のみが許可されています。乙種(整備・点検のみ)は学歴等を問わず受験できますが、甲種(工事も可能)は業務範囲が広い分、受験資格に実務経験や関連資格などが求められる場合があります。
資格の管轄及び試験の実施は、一般財団法人「消防試験研究センター」が行っています。全国各地で試験が開催されるため、地方に住んでいても取得可能です。取得ルートは、実務経験や学歴によって異なっており、受験種別によっても要件が変わってきます。独学のみでも資格の取得は可能ですが、専門のスクールのほうがより体系的に学習が進められるでしょう。
消防設備士の資格を取得しておくことで、消防設備会社やビルメンテナンス会社などへの就職に有利になります。専門性が高まるため、長期的なキャリアアップにおすすめの国家資格と言えるでしょう。
浄化槽管理士
浄化槽管理士は、商業施設やマンションに設置された浄化槽の点検や保守管理を専門に担当する職種です。最近では環境保全の観点からも注目されています。公益財団法人「日本環境整備教育センター」が指定する講習を修了し、修了試験に合格することで取得可能です。講習は全国で実施されており、5日間程度のカリキュラムへの参加が義務づけられています。学歴要件を満たしていれば実務経験がなくても受検可能ですが、専門的な知識と実践的なスキルが求められるため、数年程度の実務経験があると有利です。
環境衛生や治水業界に携わる予定の方にとっては、取得しておくことで専門性を証明でき、長期的な収入アップにもつながります。取得後は浄化槽の保守業者や自治体関係の職場で活躍できるでしょう。
海技士
海技士は、航海の安全管理や船内の機器メンテナンスを行うための国家資格です。船の運航責任者や機関士として働くうえで必須とされています。資格には等級があり、最上位の1級海技士を取得することで大型船舶での指揮が可能です。
試験は国土交通省が管轄しており、筆記試験及び口述・実技試験の2部で構成されています。資格取得にあたっては長期間の乗船履歴が必須です。海上技術学校や専修学校を経由して取得するルートが一般的で、学歴や職歴によって受講期間が短縮される場合もあります。海技士の資格を取得することで、商船やフェリー、海洋調査船など、多様な船舶での管理業務が可能になります。
小型船舶操縦士
小型船舶操縦士は船や海が好きな人にはおすすめの国家資格です。取得することでプレジャーボートや小型の漁船、観光用のボートなど、20トン未満の船舶の操縦が可能になります。日常的に利用されるさまざまな小型船舶の操縦に対応しています。操縦できる範囲や航行区域、船舶の種類によって「一級小型船舶操縦士」「二級小型船舶操縦士」「特殊小型船舶操縦士」の3つの区分があり、いずれも中卒から取得可能です。ただし、学歴不問ですが、年齢要件があります。1級は18歳以上、2級・特殊は16歳以上が免許交付の年齢要件となっています。
国土交通省の所管で、実際の試験運営や講習の実施は、公益財団法人「日本海洋レジャー安全・振興協会(JML)」が担当しています。JMLは海洋レジャーの普及と安全性向上を目的に設立され、全国に教習所や試験会場を所有する大規模な組織です。資格を取得するルートとしては、「登録小型船舶教習所」での講習受講と修了試験を受ける「教習ルート」と、独学で直接国家試験を目指す「直接受験ルート」のふたつがあります。教習ルートのほうは学科と実技を含むカリキュラムを修了すれば国家試験の一部(または全部)が免除される点がメリットです。一方、独学は時間や費用を抑えたい人に向いています。ただ、独学では実技の習得が難しいため、すでに基礎知識を持っている方に向いていると言えるでしょう。
小型船舶操縦士を取得することで、マリンスポーツのインストラクターなど、業務の幅が広がります。また、海上での自由な移動が可能になるため、釣りやクルージング、マリンレジャーなどの趣味にも役立つでしょう。また、観光業や運輸業など、海に関わる業種に就職する際にも有利になります。特に観光地では、操縦士の資格を持つ人材の需要が高く、資格手当を支給する企業も少なくありません。
調理師
調理師は、飲食店やホテル、病院、学校給食などの調理現場において、安全でクオリティの高い料理を提供するための国家資格です。単に料理が得意なだけでなく、食中毒予防や栄養バランス、衛生管理などの専門知識も問われるため、食のプロフェッショナルとしての知識を証明できます。
厚生労働省が管轄しており、各都道府県の知事が免許を交付します。取得方法は大きく、ふたつに分かれます。ひとつは、調理師養成施設を卒業するルートです。この場合、卒業と同時に資格が取得でき、国家試験を受ける必要がありません。もうひとつは、飲食店などで2年以上の実務経験を積んだ後に、都道府県が実施する調理師試験に合格するルートです。試験内容は、食品衛生、栄養学、公衆衛生、食品学、調理理論など多岐にわたり、実務経験と専門知識の両方が問われます。
調理師免許を持っておくことでファミレスはもちろんのこと、ランクの高いレストランにも採用されやすくなるでしょう。さらに調理師免許を取得することにより現場で責任ある立場に就くことができ、衛生管理者や指導者としての活躍が期待されます。特に学校などでは調理師免許保有者の配置が法令で定められているため、就職においても大きなアドバンテージとなるでしょう。また、将来的に独立をする際にも、お客さんから信頼されやすくなります。
理容師
理容師は長期的に需要が安定した職業であり、手に職をつけたい人におすすめの資格です。理容師法に基づき、厚生労働大臣が指定する国家資格とされています。理容業を営むには国家試験への合格が必要です。
試験は公益財団法人「理容師美容師試験研修センター」が管轄しており、衛生面や技術面に関する基準も同団体によって定められています。数ある国家資格の中でも、制度全体の整備と運用は公的機関が担っている点が大きな特徴です。理容師になるにはまず、理容師養成施設で必要なカリキュラムを修了する必要があります。中卒だったとしても、養成施設(通信課程含む)を修了すれば国家試験の受験が可能です。国家試験に合格すれば資格が取得できます。また、通信課程も用意されているため、働きながら資格取得を目指すことも難しくはありません。試験では、実技試験と筆記試験の両方にパスする必要があります。
資格を取得することで全国の理容室で勤務できるほか、個人として理容室を開業することも可能です。独立の道が開けるため、将来性が高い資格と言えるでしょう。また、最近では、介護施設や医療機関での訪問理容のニーズも高まっており、活躍の場はますます広がっています。
美容師
美容師は、髪のカットやカラー、パーマなどを通じてお客さんのスタイリングを行う専門家です。ヘアメイクだけでなく、まつ毛エクステやネイルに対応する人も増えています。美容師法に基づいた国家資格であり、プロとして働くには国家試験への合格が必要です。
試験と資格の認定は、厚生労働省および「理容師美容師試験研修センター」が行っています。理容師と同じく、国家資格として全国統一の基準が設けられているのが特徴です。また、公衆の内容や衛生管理の基準も同団体によって厳格に定められています。公的機関によるチェック制度が整っているため、社会的な信頼性の高い国家資格と言えるでしょう。美容師免許の取得には、厚生労働省が管轄する「美容師養成」を修了した(中卒だったとしても、養成施設(通信課程含む)を修了すれば国家試験の受験が可能)うえで、美容師の国家試験に合格する必要があります。養成講座には日中の課程もありますが夜間課程、通信課程などもあるため、社会人として働きながら取得を目指すことも可能です。国家試験では実技試験と筆記試験があり、総合的な知識・スキルが求められます。美容師のアシスタントとして働くうえでは資格は必須ではありません。ただ、美容師として独立するには美容師資格が必要です。
運行管理者
運行管理者は、時間に几帳面で責任感が強く、運送業で独立を考えている人にはおすすめの資格です。バスやトラックなどの事業用自動車の運行に関する安全管理を行うための専門資格であり、実際の運転業務以上に、過労運転の防止や点呼の実施、運転者の健康状態の確認などを担います。道路運送法により定められた国家資格で、一定数の車両を持つ事業所においては1人以上の配置が必須です。安全運行を支える重要なポジションであるため、責任の大きな職務と言えるでしょう。
資格の運営及び管轄を担っているのは国土交通省です。試験の実施は、公益財団法人「運行管理者試験センター」が担っており、業務内容のガイドラインの発行も担当しています。資格の取得には、指定の講習を受けたうえで試験をパスするルートがあります。また、1年以上の実務経験がある場合、講習を省略して国家試験を受験することも可能です。試験は原則として、年2回実施されています。平均の合格率は30〜40%前後です。運行管理者の資格を取得することで、運送業界での信頼性が高まります。また、昇進や転職にも有利に働くため、キャリア形成にも意味があるでしょう。
毒物劇物取扱責任者
毒物劇物取扱責任者は、死を招く毒物・劇物を処理・加工するための専門資格です。毒物や劇物を取り扱う事業所では配置が義務づけられており、主に薬品の販売や製造、管理業務において安全性を確保する役割を担っています。化学分野の専門職は将来的にも需要が安定しており、長期的に活用できる資格です。
「毒物及び劇物取締法」に基づく国家資格であり、専門性の高い資格のひとつです。厚生労働省が管轄及び運用を行っており、全国の自治体ごとに試験が行われています。試験内容や日程が自治体によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。資格の取得にあたっては、大学で指定の化学系科目を修了するか、自治体が実施する国家試験に合格する必要があります。独学での受験も可能ですが、専門的な化学知識が求められるため、ハードルが高いと言えるでしょう。
登録販売者
登録販売者は、一般用医薬品の中でも第二類・第三類医薬品を販売できる、専門性の高い国家資格です。薬剤師が不在であっても一定の範囲で医薬品の販売が可能なため、薬局だけでなく、コンビニやドラッグストアなどで重宝されています。
登録販売者は、2009年に施行された改正薬事法によって新設された、比較的新しい資格です。薬剤師の職域をカバーする専門職として国民の健康を支える存在となっています。厚生労働省管轄の国家資格であり、実際の試験を運用するのはそれぞれの都道府県です。実務経験の登録や届出についても、所管の自治体が管理しています。
国家試験は原則として誰でも受験可能で、学歴や年齢の制限は特にありません(※一部の都道府県では「満18歳以上」などの年齢制限があり)。試験は年1回の実施で、合格率は40〜50%前後とされています。働きながらでも受験できるため、社会人でもチャレンジしやすい資格と言えるでしょう。資格取得後は、ドラッグストアやスーパーの薬品売場での勤務が可能です。また、医薬品販売の責任者として信頼性が高まるため、将来的なベースアップにもつながるでしょう。地域医療に貢献できる点も、大きな魅力です。
宅地建物取引士
宅地建物取引士は、不動産取引に関わる重要事項の説明や契約書類への記名押印などを行う国家資格です。不動産業界において、必ず一定の資格保有者を配置することが義務づけられています。「宅地建物取引主任者」から名称が変更されており、より専門性の高い資格として認識されるようになりました。不動産取引の公平性・安全性を守る役割を担っており、社会的信頼性も高い資格です。
国土交通省が管轄する国家資格であり、毎年20万人以上が受験しています。試験を実施しているのは一般財団法人「不動産適正取引推進機構」です。問題作成や合格基準の設定も、公的機関の監修のもとで行われています。受検にあたって学歴や実務経験の制限はなく、誰でも資格の取得が可能です。独学でも取得できますが、通信講座やスクールを活用して合格を目指す人も少なくありません。宅地建物取引士を取得することで、不動産会社での業務範囲が広がります。また、独立開業や転職にも非常に有利です。また、副業やフリーランスとしても活かせるため、不動産業界でのキャリア形成を目指している方に適しています。
中卒から資格を取るメリット・デメリット
中卒から資格を取るメリットは以下の通りです。
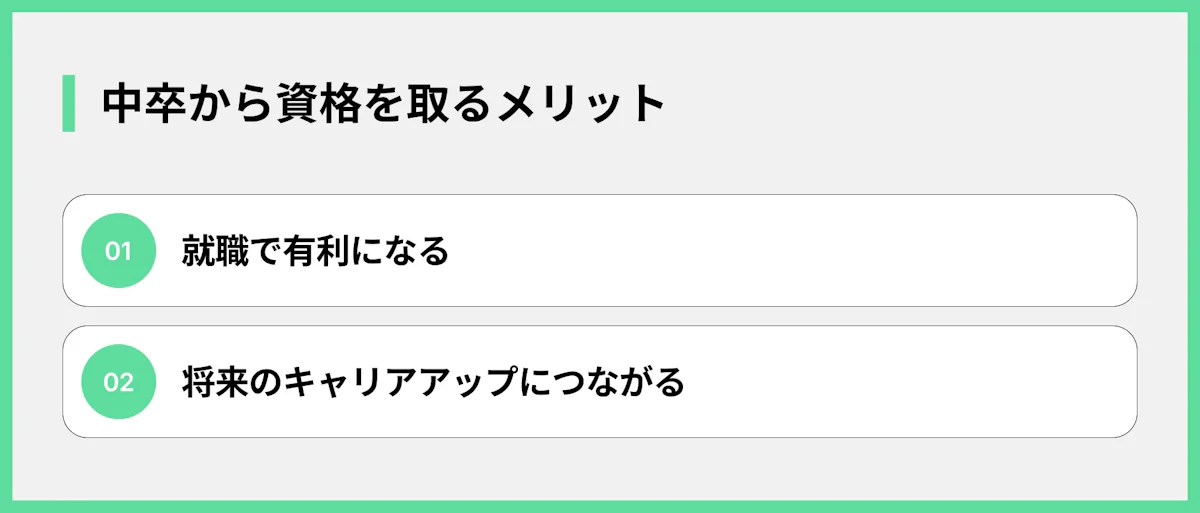
中卒で資格を取ることで、持っているスキルを証明できます。中卒の場合、高卒・中卒と比べると学歴の面では不利です。ただ、中卒であっても資格を取っておくことで大卒と同等のスキルや専門性を示せるため、就職におけるハンディを解消できるでしょう。また、資格を活用して早い段階で就職をすることでより多くの経験を積めるため、将来的なキャリアアップにつながります。資格の専門性が高いほどベースの収入が上がり、昇給の幅も大きくなるでしょう。一方で、中卒での資格取得には以下のようなデメリットがあります。
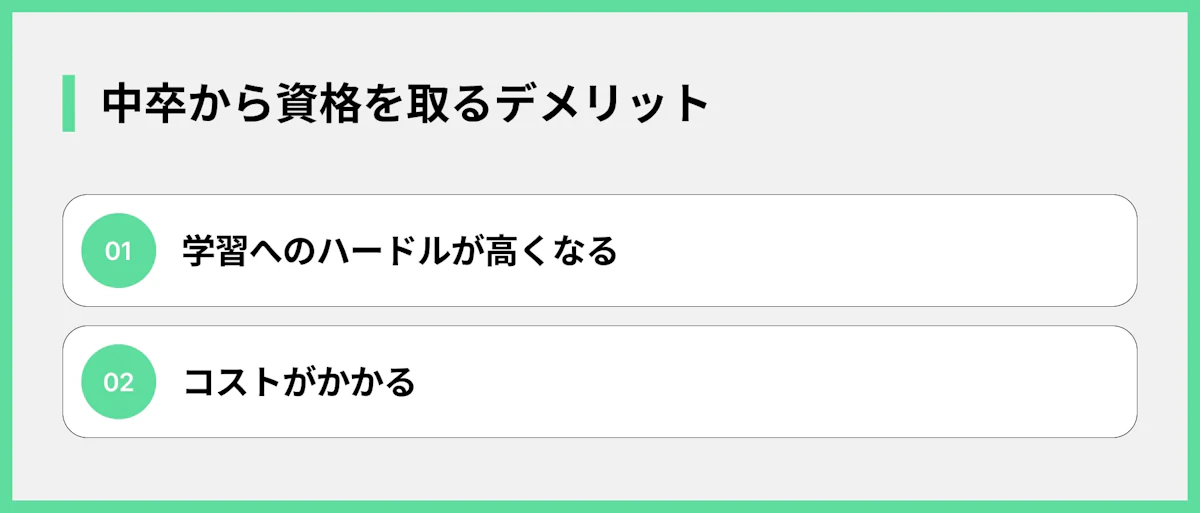
資格の中には高卒、大卒レベルの知識を前提としているものも少なくありません。そのため、中卒での取得を目指す場合、その分の知識のギャップを埋める必要があり、学習に時間がかかります。結果として資格取得までにコストがかかる点もデメリットの1つです。
中卒から資格を取るなら独学のほうがいい?
中卒で資格を取る方法としては独学と資格学校があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、資格の種類やライフスタイルに合わせた選択が必要です。
ここでは以下の内容を解説します。
- 独学のメリット・デメリット
- 資格学校のメリット・デメリット
独学のメリット・デメリット
中卒から独学で資格を取る主なメリットとデメリットは以下の通りです。
独学のメリット
独学での資格取得は、資格学校に通うパターンと比べてコストがかかりません。資格学校の場合、毎月の学費が必要ですが、独学であればほぼテキスト代だけでおさまります。経済的な余裕は精神的なゆとりにもつながるため、学習を長いスパンで続けやすいでしょう。
また、資格学校のようにカリキュラムが決められないため、自分のペースで学習を進められます。そのため、苦手な部分を何度も復習でき、プレッシャーを気にせず知識を積み上げられる点がメリットです。学習時間を自分で決められるため本業とも無理なく両立でき、経済的な負担も軽減できます。
独学のデメリット
独学の場合、教材選びから始めなくてはなりません。資格について予備知識がほとんどない場合、どのテイストのテキストを選ぶべきかがわからず、スタートからつまずいてしまう可能性もあります。
また、専任の講師がいないため、途中でわからないことがあったとしても質問することができません。今の時代、ネットを通して豊富な情報を得ることができますが、「講師と直接コミュニケーションを取れない」状況は資格学校と比較しても大きなハンディになるでしょう。
独学で資格を取るなら、無理のないペースを守りつつモチベーションを維持することがポイントです。
資格学校のメリット・デメリット
資格学校のメリット
資格学校の場合、取得までのカリキュラムがあらかじめ用意されているため、必要な知識を段階を踏んで無理なく積み上げられます。また、独学のように教材選びで悩む必要もありません。
また、プロの講師がレッスンにあたるため、不安点や疑問点があればすぐに質問でき、学習のフィードバックもスムーズです。最近では、オンラインであっても講師とマンツーマンでコミュニケーションを取れる環境が整っています。オフラインの資格学校なら、同じ空間で複数のメンバーと学習できるため、同じ目標を持つ仲間と交流を深められるでしょう。丁寧なフィードバックや仲間の存在は学習のモチベーションになります。
スケジュールに余裕があり、「プロの講師から学習をフォローしてもらいたい」という人には資格学校が向いているでしょう。
資格学校のデメリット
一般的に、資格学校に通うには独学以上のコストが必要です。専門性の高い資格の場合、学費だけで数十万円単位になることもあるでしょう。また、資格学校によってカリキュラムや教え方に特色があるため、相性が合わなければ学習のモチベーションが下がってしまうかもしれません。多くの資格学校では3カ月~1年のスパンでカリキュラムが組まれるため、万一途中で「別の道に進みたい」と思っても路線変更が難しい面があります。
すでに将来のビジョンが具体的に見えており、必要な資格がきちんとわかっている人には資格学校がおすすめです。
中卒から資格を取るポイント
中卒から資格を取得する際は、以下のポイントに留意しましょう。
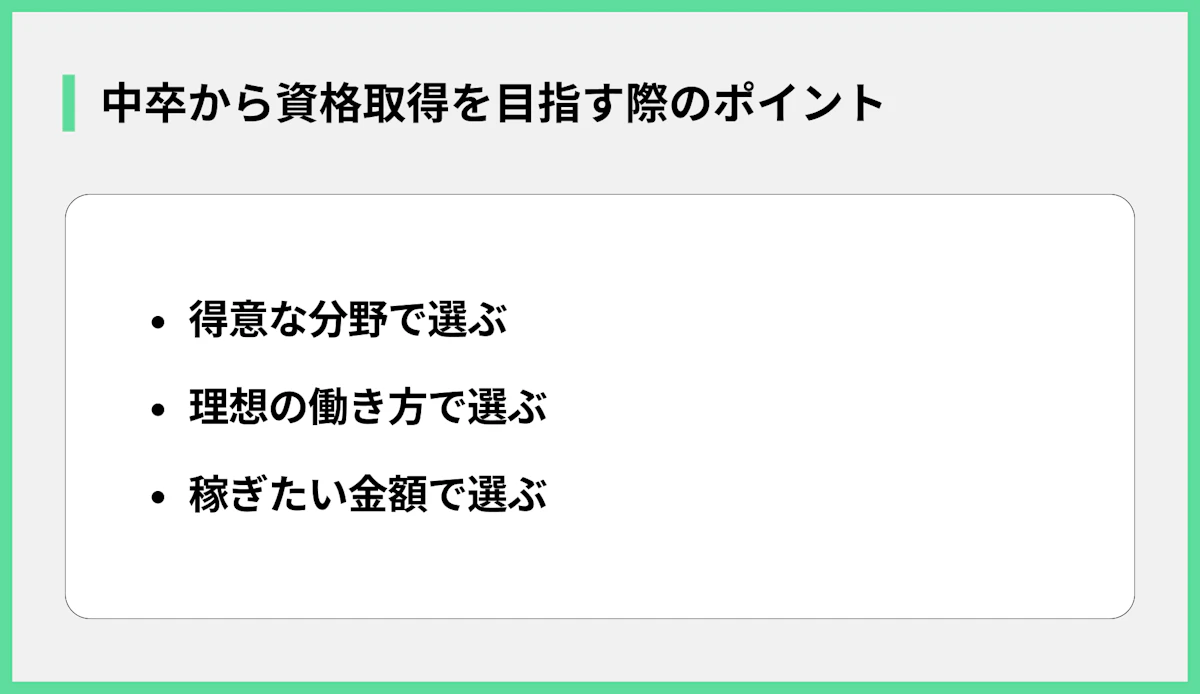
得意な分野で選ぶ
資格を選ぶ際に重要なのが「自分の得意なこと」や「興味のあること」を中心としたプランニングです。誰でも得意なことに取り組むと、自然とやる気が湧きますし、努力を続けることも苦にならないでしょう。反対に、苦手な分野に無理やりチャレンジしても、途中で投げ出してしまったり、結果が出にくくなったりして、かえってモチベーションが下がってしまうかもしれません。
たとえば、ものづくりが得意な方には、調理師、建築系技能士、電気工事士といった実技中心の資格がおすすめです。こうした資格は学力よりも「技術力」が重視されるため、中卒でも充分に活躍できる余地があります。特に電気工事士は、安定性と将来性の両方が期待できる資格として人気です。美的センスを活かした活動が得意な方には、美容師、ネイリスト、エステティシャンなど、美容系の資格が向いています。これらの業界も理論だけでなく技術がより評価されるため、感覚やセンスが活かせる場面が広がるでしょう。
文章を書くことやSNSでの発信が得意な方なら、Webライター検定やマーケティング系の資格を取ることで収入アップの可能性が高まります。あるいは、動画編集系の資格もチャンスが広がるでしょう。これらは在宅ワークでも充分に活かせるスキルであり、場所や時間に縛られず、自由なスタイルで収入を得ることが可能です。
長く続けられる仕事を選ぶためにも、自分の「強み」をしっかりと見きわめたうえで無理なく働ける資格を選びましょう。
理想の働き方で選ぶ
資格を選ぶ際は、働き方のビジョンも欠かせません。近年は働き方がますます多様化し、正社員だけでなく、契約社員、パート・アルバイト、在宅ワーク、フリーランスなど、多様な選択肢が用意されています。だからこそ、ビジョンに見合った資格を取得することは、理想に近い働き方を実現するうえで大切です。
例えば、「安定した収入を得たい」「福利厚生が整っている会社で働きたい」というビジョンを持っているなら、正社員で有利となる資格がおすすめです。特に、医療事務、介護職員初任者研修、調理師、宅建士(宅地建物取引士)などは、正社員の求人も多く、比較的安定した収入が期待できます。
一方で、「子育てや家事と両立したい」「短時間で働きたい」といったビジョンを持っているのであれば、柔軟な働き方が可能な資格が向いています。たとえば、Webデザイナーなどはリモートワークがしやすいため、子育て中の方にもおすすめです。最近では、時短勤務やフルフレックスなど、働き方のバリエーションも広がっているため、年齢とともにライフスタイルが変化したとしても無理なく働きつづけられます。
最近では、副業解禁の流れもあり、複数の仕事を組み合わせて収入を安定させる「パラレルワーク」もおすすめです。
このように、自分にとって無理のない働き方を選ぶためにも、ビジョンに沿った資格取得は有力な手段と言えるでしょう。
稼ぎたい金額で選ぶ
資格を有効に活用するうえで大切なのが「収入の目標ライン」をはっきりさせることです。「月にいくら稼ぎたいのか」「本業にするのか、副業にするのか」などのポイントを明確に設定しておくことで、資格選びの方向性が定まるでしょう。
たとえば、年収300万円以上を目指すなら、国家資格を視野に入れるのが近道です。電気工事士、宅地建物取引士、介護福祉士などは、一定の経験と技術が必要ですが、その分だけ収入も安定しており、将来性も期待できます。特に介護福祉士は、今後の高齢化社会に向けて需要が高まっている分野で、求人が安定しているのが大きな魅力です。
看護師や歯科衛生士などの医療系の資格も高収入が期待できる職種ですが、取得までに時間と費用がかかるというデメリットがあります。特に中卒から取得を目指す場合は、通信制高校や専門学校への進学が必要になるケースもあるため、長期的なプランニングが必要です。
反対に、「月5万円程度の副収入があれば充分」というビジョンを持っている方であれば、ハードルの低い資格を取得しておくこともひとつの方法として挙げられます。たとえば、Webデザイナー検定やSNSマーケティング検定などは、在宅での副業にも適しており、趣味を活かして収入を得ることも可能です。さらに実務を通してスキルを磨き、こつこつと信頼を積み重ねていけば、収入アップも充分に期待できるでしょう。
むやみに高収入を目指すと心身ともに無理をしてしまい、長続きしません。理想のビジョンを具体化しつつ、キャパシティに見合った働き方を組み立てることが大切です。
まとめ
中卒から取得できる資格は珍しくありません。学歴がなかったとしても、実務経験を積み重ねることで必要な知識・スキルを身につけ、合格率を高めることができます。もちろん、取得後のビジョンも大切です。中卒というハンディを不安に感じる方も多いかもしれませんが、資格という武器を手に入れることで、人生の可能性は大きく広がります。自分の能力を無理なく活かせる資格を取得して、将来のキャリアアップにつなげましょう。
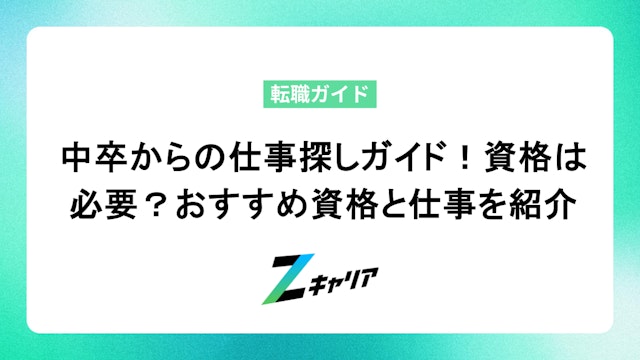
.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)